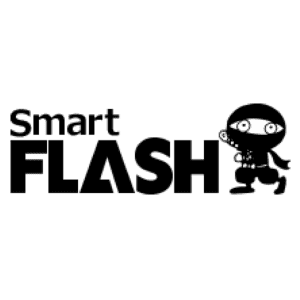感想戦で振り返る伊藤匠新叡王(左)と藤井聡太七冠(右)
将棋界の若き絶対王者・藤井聡太の八冠独占を崩したのは、同じ21歳の大器・伊藤匠だった。新たな時代の「宿命のライバル」の物語が始まった――観る者にそう思わせるような、劇的な名勝負の幕切れだった。
藤井聡太叡王がタイトル戦敗退なしのまま突き進むのか。それとも伊藤匠七段が初タイトルを獲得するのか。藤井に伊藤が挑戦する叡王戦五番勝負は2024年4月に開幕した。
下馬評は藤井ノリの声が圧倒的だった。八冠を達成した藤井は、古今無双とも思える強さを誇っている。藤井は昨年10月、王座を獲得して八冠を達成。続く竜王戦七番勝負と棋王戦五番勝負では、伊藤の挑戦をどちらもストレートで退けていた。
叡王戦が始まるまでの通算対戦成績は藤井の10連勝(1引分)。伊藤は藤井の「ライバル候補」の本命ではあった。しかし、藤井を相手に内容的には善戦していたものの、結果という点ではまだ及ばなかった。
しかし五番勝負が始まってみると、伊藤は大方の下馬評をくつがえし始めた。第1局は敗戦。しかし第2局に勝ち、第3局にも勝って、藤井をカド番に追い込んだ。
2020年、藤井は初タイトル(棋聖)を史上最年少17歳11カ月で獲得して以来、タイトル戦の番勝負で敗退したことがなかった。それも多くの場合は、圧倒的なスコア。先にカド番に追い込まれたことは、いままで一度もなかった。
叡王戦第4局では藤井が地力を発揮して、完勝。叡王位のゆくえは、フルセットの最終戦に持ち込まれた。
6月20日、運命の第5局。朝9時の対局開始に先立って、あらためて先後を決める振り駒がおこなわれた。記録係が歩兵(ふひょう)の駒を5枚振った結果、表の「歩」が3枚、裏の「と」が2枚出て、先手は藤井と決まった。
将棋はわずかではあるが、先手が有利なゲームだ。公式戦の統計上では、その差はほんの数パーセント。ただし藤井が先手を持つと、無敵に近い結果が残されている。
完全情報ゲームの将棋では理論上、運の要素は介在しない。しかし振り駒だけは運だ。藤井が先手番をにぎったことで、八冠防衛の流れと感じた人も多かっただろう。
藤井は得意の角換わり腰掛け銀を選んだ。伊藤も事前準備は十二分に積んできた。それでもリードを奪ったのは、やはり藤井だった。一方的に攻める展開を作り、相手の歩頭に銀を立ち、タダで捨てる妙手を織り交ぜながら、鮮やかな攻めで伊藤玉を追いつめていく。形勢ははっきり、藤井が優位に立った。
伊藤は苦戦に陥った。しかも相手は最強の藤井だ。心が折れても不思議ではない場面にも見えた。しかし棋士の真価が問われるのは、こうしたところなのだろう。伊藤は折れることなく、粘り強くしのぎ続ける順を探った。自陣に銀を1枚打ちつけ、さらにはもう1枚の銀を引いて退路を開き、大事な飛車を藤井に取らせる間に、自玉は小康を得た。
このあたりの攻防について、両者は対局後、次のように語った。
「自信のない展開が続いたんですけど。なんとか辛抱強く指すことができたかなと思います」(伊藤)
「指されるまで気づいていなくて」(藤井)
我慢を重ねていた伊藤は、そこで反撃に転じる。
「少し指せている可能性もあるかなと思っていたんですけど」(藤井)
局後にそう振り返った通り、藤井は形勢リードを自覚していたし、その判断は正しかった。
一般的に将棋は、優勢な局面から勝ち切るまでが大変だ。だからこそ、驚くような逆転劇が起こる。とはいえ、藤井はいつもそうしたところから、快刀乱麻を断つがごとく、観戦者が驚くような、明快で鮮やかな勝ち筋を見つけ、盤上に示し続けてきた。
その藤井が、すっきりした勝ちに至るルートを見つけられない。それはもちろん、伊藤がそうした複雑な状況に導いていたためだ。
コンピュータ将棋(AI)が示していた最善手は、俗筋のような王手だった。しかしあまりに俗すぎて、かえって人間の上級者には指しづらい。
藤井は納得のいく手順を見つけられないまま、残り時間が削られていく。最近の藤井にしては珍しく、音を立て、右手でももを叩くようなしぐさも見せた。
言うまでもなく、藤井は将棋の大天才だ。才能がなければ、八冠など取れるはずがない。そのうえで、人一倍負けずぎらいな精神が、藤井という奇跡の存在のバックボーンとなっている。
幼いころの藤井は、負けると大泣きすることで有名だった。史上最年少の14歳で棋士になって以降はもちろん、公式戦でたまに負けることはあっても、大泣きする姿などは見せたことはない。しかしそれでもごくまれに、負けずぎらいの顔を、ちらりとのぞかせることがある。
藤井少年を泣かせたひとりは、ほかでもない、同い年の伊藤少年だった。小学生のとき、両者の対戦はその一度きり。その後の歩みでは、藤井が大きくリードした。伊藤はずっと、藤井を意識し続けてきた。そしてこの叡王戦五番勝負においては、ついに伊藤が藤井に追いつこうとしていた。
気づいてみれば形勢は藤井優勢から、ほぼ互角にまで引き戻されていた。ならば流れは伊藤にある。
観戦者から「名局」の声が上がるなか、勝敗不明の最終盤が続いた。最後は両者ともに残り時間が切迫。そこで競り勝ったのは、伊藤のほうだった。
自玉が受けなしに追い込まれた藤井は最後、相手玉に王手をかけていく。伊藤の玉が詰めば藤井の勝ち。詰まなければ藤井の負けだ。
世界でもっとも詰将棋を解くのが速い藤井は、時間はなくとも、結論は瞬時にわかっていたのだろう。すなわち、伊藤の玉に詰みはない。藤井は悄然とした表情で、ときおり宙を見上げる。詰まないとは知りながら、藤井はしばらく、王手をかけ続けた。
155手目。藤井は桂馬を打って、伊藤玉に王手をかける。上がってくれれば詰む。しかし引かれれば詰まない。
156手目。伊藤は間違えない。しっかりとした手つきで、玉を引いた。
18時32分。藤井は潔く、頭をさげた。
「負けました」(藤井)
「ありがとうございました」(伊藤)
両対局者は深く一礼。伊藤は五番勝負を3勝2敗で制し、叡王位を獲得した。
「全体的に苦しい将棋が多かったと思うので。まあ、なんというか、運がよかったかなと思っています」「対藤井八冠戦では苦しい戦いはずっと続いていたので。やはり、ひとつ結果が出せてよかったという気持ちです」(伊藤)
伊藤は謙虚に、シリーズを振り返った。相応の実力がなければもちろん、藤井から3勝も挙げられるはずがない。伊藤の戴冠を「まぐれ」だと見る人は、ひとりもいないだろう。
藤井よりも3カ月あとに生まれた伊藤は、現在21歳8カ月。タイトル初獲得の年少記録としては史上1位の藤井(17歳11カ月)には及ばないものの、8位で十分に早い。
四段昇段から初タイトル獲得までの期間に着目してみれば、藤井は3年9カ月、伊藤は3年8カ月で、伊藤のほうが早い。伊藤もまた藤井と同様に、大棋士への道を歩み始めたといってよさそうだ。
藤井がタイトル戦初登場以来ずっと続けていた、番勝負の連覇記録は22で止まった。八冠独占もまた、ここで一区切りとなった。記者からその点について問われると、藤井は穏やかな笑みを浮かべて、次のように語った。
「それは時間の問題だと思っていたので」
八冠を達成する以前と同様、藤井の興味関心は、そうした点にはないのだろう。
「まずは(伊藤に)終盤戦で上回られてしまったというところが多くあったかなと思っています」「やっぱり叡王戦でも伊藤さんの実力を本当に感じるところがすごく多かったので。やっぱり私自身も実力を高めていけるようにがんばらなければいけないと思います」(藤井)
藤井がこの先、八冠に復帰するチャンスはめぐってくるかもしれない。一方でそれを阻止する一番手は、伊藤の可能性が高い。
藤井の「ライバル候補」だった伊藤は、これで名実ともに「ライバル」に昇格したと言ってもよさそうだ。今後は確実にそう呼ばれる機会も増えるだろう。しかし伊藤自身はまだ、藤井をライバルの関係にあるとは思っていない。
「まったくそういう認識はないんですけれども。まだまだ自分の方が実力が不足しているかなと感じているので。今後も引き続き藤井さんとタイトル戦で戦えるようにがんばりたいと思っています」(伊藤)
「宿命のライバル」という常套句は、じつは将棋界で生まれた。観戦記者である倉島竹二郎(1902-1986)が、木村義雄14世名人(1905-1986)と金子金五郎九段(1902-1990)の関係を表すのに、初めて使ったものだ。
升田幸三と大山康晴。中原誠と米長邦雄。羽生善治と森内俊之。年代が近い、それらの大棋士の関係は「宿命のライバル」と表現されてきた。もしかしたらこの先、時を経たあと、藤井聡太と伊藤匠の2人は、宿命のライバルと呼ばれるようになっているのかもしれない。
文・松本博文