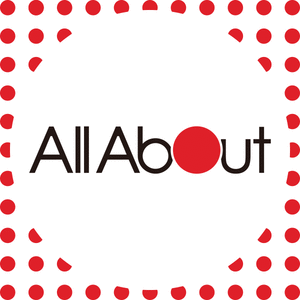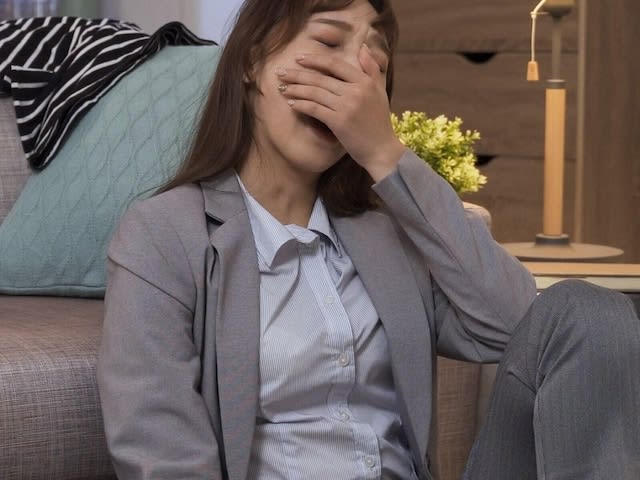
Q. 面倒でお風呂に入る気力もわきません。どうすれば治せますか?
Q. 「最近、お風呂に入るのが面倒で仕方ありません。嫌なことがあったりして気持ちが落ち込むと、お風呂に入れず、そのまま眠ってしまうこともあります。 友達もよくあると言っていますが、落ち込んだだけで、日常的なことすらできなくなるものでしょうか? うつ病経験がある友だちは、1週間もお風呂に入れないことがあったそうです。自分で治すコツや考え方はありますか?」
A. 日常生活は「生体」への負荷の連続。疲れているときは面倒で当然です
最近のSNSで「風呂キャンセル界隈」といった言葉がトレンド入りしたようで、それに関連したご質問かと思いますが、脳や体の健康を専門とする筆者としては、何を議論しているのか今一つ理解しがたい話題です。 そもそも体や心が疲れているときは、たいてい大きなストレスが脳内で生じています。過度のストレスが続くと、記憶障害など脳へのダメージが残ることもありますので、それ以上ストレスがかからないようにすることが大切です。 生物学的なストレスとは、「寒冷、感染、心労など、体外からかかる刺激に応じようとして体の内部で生じる様々な『体や心の反応』」のことを指します。 お風呂に入ると気持ちよくなったり、食べ物を摂るとおいしく感じたりするので、そうした行為はストレスと関係ないことで、むしろストレスを軽減してくれるものと思われるかもしれませんが、実はお風呂や食事などの日常的な行為も、すべて生体にストレスを生じるものです。 「熱いお湯や水にさらされる」「高湿度の空気を吸い込む」「食べ物を口に運んで咀嚼し飲み込む」……私たちが何気なくしている普段の行動も、生体にとっては大きなエネルギーを消費する大変な行為なのです。 その証拠に、高齢になったり重い病気にかかったりすると、サポートを受けたとしても、お風呂や食事も簡単には済ませられなくなりますね。 それだけ日常的な行為は、生体に負荷をかけ、ストレスを生じることだということを、正しく理解しましょう。 ストレスが続き、心や体が本当に疲れてしまったときは、何もしないで休むことが最善です。お風呂にも入らず食事もとりたくないという気持ちになるのは、生物の防衛本能として当然のことなのです。 極端な話ですが、仮に一週間くらいお風呂に入らなくても、命にかかわることはありません。休んで治りそうなのであれば、休むことです。 もし、やりたいことがうまくいかないなど、落ち込みの原因がはっきりしているのなら、信頼できる人に相談するなどして、原因となっている諸問題の解決を図ることも必要です。 とくに原因がないのに、落ち込んだ気持ちがずっと続いているのであれば、うつ病などの精神的な病気の可能性も考えられます。 何日かお風呂に入らないくらいでは解決しそうにないときは、一度専門医に診てもらってください。
阿部 和穂プロフィール
薬学博士・大学薬学部教授。東京大学薬学部卒業後、同大学院薬学系研究科修士課程修了。東京大学薬学部助手、米国ソーク研究所博士研究員等を経て、現在は武蔵野大学薬学部教授として教鞭をとる。専門である脳科学・医薬分野に関し、新聞・雑誌への寄稿、生涯学習講座や市民大学での講演などを通じ、幅広く情報発信を行っている。 (文:阿部 和穂(脳科学者・医薬研究者))