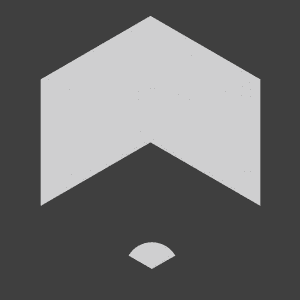東大は6月21日、授業料引き上げをめぐる「総長対話」を実施した。藤井輝夫総長らが引き上げを検討するに至った背景などを説明した後、学生が総長に質問をした。総長は、引き上げが検討段階であることを強調し、学生との「対話」の機会の再設置については「検討していく」と繰り返したという。「総長対話」は午後7時からZoomウェビナー上で開催され、予定を27分超過して実施された。24日にはアンケートを学務システムUTAS上に掲載し、総長対話で用いられた資料も共有されるという。
参加した学生に対して東京大学新聞社が実施した取材によると、大学側からは藤井総長の他に相原博昭、森山工、藤垣裕子各理事・副学長など6人の役員が参加した。参加者によると総長が15分程度話し、検討の過程で大学側の見落としや、教育活動で他に優先すべきものがないかについて学生から意見を聞きたいとした。学生からの質問は、まず学部生・大学院生の二つのグループに分ける形で受け付けた。さらに学部生と大学院生とを分けない形で質問が受け付けられた。のべ100人程度の発言希望者から無作為に選ばれた合計14人の学生が、総長に口頭で質問した。その他、文面での質問も募集された。
藤井総長の説明
藤井総長は、基盤的な収入である運営費交付金の減少や支出の抑制に関する取り組みに言及したという。体験活動プログラムに実施や拡充を断念をせざるを得ないものが出てきているとして「残念」な状況であるとした。教育・研究活動の改善に向けて、エンダウメント型への経営転換を目指していることを共有。寄付金などとは違い安定した財源で、教育活動のために用いることができる授業料の引き上げの検討が行われるようになったとした。その上で、引き上げ導入年度の入学者から学部および大学院の学生の授業料について2割を引き上げる案を検討していることを改めて提示。大学にとって増益分の約29億円はD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進のほか、実施を断念してきたプログラムに当てる方針だとした。TA(ティーチング・アシスタント)やRA(リサーチ・アシスタント)の手当ての拡充などの計画も示した。
国立大学は経済的に恵まれていない学生に対しても広く就学機会を提供する必要があるとして、支援制度を厚くし、支援制度の広報を強化することも明言。国の支援に加え、授業料の全額免除の体制を世帯収入400万円以下から600万円以下へ引き上げる案を示した。大学院生への適用拡充・学生個別の事情への配慮もするとしたとみられる。
学生からの質問と返答
質問した学生からは、学費減免措置に関する質問や在り方への疑念の声があったとされる。ある学生は、授業料引き上げが、藤井総長が本年度の入学式で言及した「構造的差別」の助長につながることを懸念。基準となる世帯収入を超えているが保護者から経済的支援を受けられない学生を心配する声も複数出た。藤井総長は、学生個別の事情に配慮した「きめ細かい措置」を継続すると発言。世帯収入600万円から900万円の世帯にも減免措置をとることも検討しているとした。進学などをためらう人が出ないよう、学生の意見を聞きながら詳しく見ていきたい旨も述べたという。
引き上げをめぐる意思決定プロセスに関しても複数の学生が疑問を呈したとされる。学生や大学執行部以外の教員が十分に巻き込まれず、トップダウンに決定していることへの不信感を示す声に対して、総長は、今回の総長対話などを通して構成員の意見を聞きながら議論しており「きちんと了承を得ながら前に進めている」という姿勢を強調。検討の早いタイミングで報道が出たことに当惑していると繰り返し述べた。授業料引き上げは学生の「交渉」の対象ではないとしつつも、学生の意見も聞きながらより良い方向性を探っていきたいとした。
ある大学院生は、すでに来年度の東大大学院の出願が始まっている専攻があることを指摘。引き上げの有無の決定時期を質問すると、藤井総長は、遅くとも学部出願の募集時期に間に合うようにしたいと示したという。一方で、その時までに決めるために議論を急ぐものでもないという認識を示し、大学院受験生への影響も検討したいとした。
授業料引き上げによる増額分が東大の全体の年間予算の約1%であり、予算の赤字を埋めるのには不足しているのではないかという質問も出されたが、藤井総長は「授業料値上げは赤字の補填(ほてん)ではなく、あくまで教育環境のさらなる拡大のためだ」と回答したという。その他にも、東大の経営状況やエンダウメント経営の在り方、授業料引き上げと東京大学憲章や東大確認書との整合性、日本も批准している「国際人権規約」で定められた高等教育の段階的な無償化を踏まえ、運営費交付金の増額を国に対して主張すべきとの意見や、学生寮が経済支援の一環として全ての学生を包摂できていると考えるかどうかなどについて質問された。
藤井総長は最後に、幅広い議論ができたとし、意見を踏まえながら次のステップに進んでいきたいと総括したという。
今回の「対話」では、学生が一人ずつ発言をする形式をとったが、学生にプレッシャーをかける形式になっているという指摘も複数あった。学生が指名されていないタイミングで発言をした場合に、司会からさえぎられて発言が妨げられることもあったという。
総長対話は日本語で行われ、英語と日本手話で通訳も行われた。東大の本部広報課への取材によると、総長対話には約750人の事前の参加申請があった。
学生の動き
教養学部と文学部、教育学部の学生有志が駒場Ⅰキャンパス13号館、本郷キャンパスの経済学研究科学術交流棟・小島ホール、赤門総合研究棟のそれぞれでパブリックビューイングを実施。東大側からは事前にパブリックビューイングの中止を求める要請があったとも言われているものの、各会場で100〜150人ほどの参加者がいたという。東京大学教養学部学生自治会が主催した駒場の会場では、対話終了後に「本日の総長対話は意見交換の場として不十分なものであった」などとする会場議決も行ったとされる。
東京大学教養学部学生自治会は21日に授業料引き上げをめぐる学生投票の結果を公表。13〜19日に行われた学生投票は、有権者(前期教養課程生)の36.6%に当たる2409票を得て有効だったことを公表した。「授業料値上げの検討の取止め」(賛成86.1%)など4項目すべてが可決されたとしている。「学生側との継続的な交渉に応じるよう総長に求める」は95.9%の賛成票が集まったとしている。
教養学部学生自治会は20日に駒場Ⅰキャンパスで、文学部連絡会らは21日の総長対話の前後に東京大学大講堂(安田講堂)でそれぞれ授業料引き上げに関する集会を開いた。20日の集会には國分功一郎教授(東大大学院総合文化研究科)や隠岐さや香教授(東大大学院教育学研究科)、21日の集会には隠岐教授や野島博之氏(塾講師)など、学生以外にも大学教員や教育関係者が参加した。
【記事修正】6月21日午後10時14分、誤字を訂正しました。
【学費問題】東大新聞オンライン掲載記事のまとめページはこちら(随時更新)
東京大学新聞社は多様なステークホルダーの声を発信し、日本の大学の未来を考える助けになることを願っています。東大内外問わず皆様の意見をお聞かせください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRlELQPbDDk9PbncP2DXEalxCBxnGv4cC4OqQTqU-1CZv0Iw/viewform
GoogleフォームのQRコードはこちら
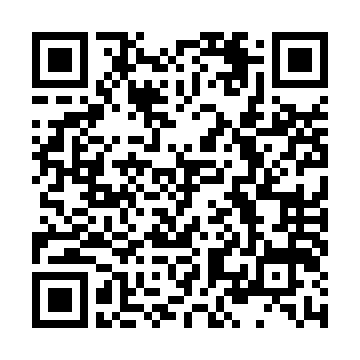
The post 【学費問題】総長対話、学生14人が発言 決定プロセスや使途の不透明性に関する質問相次ぐ first appeared on 東大新聞オンライン.