by 山田 祥平
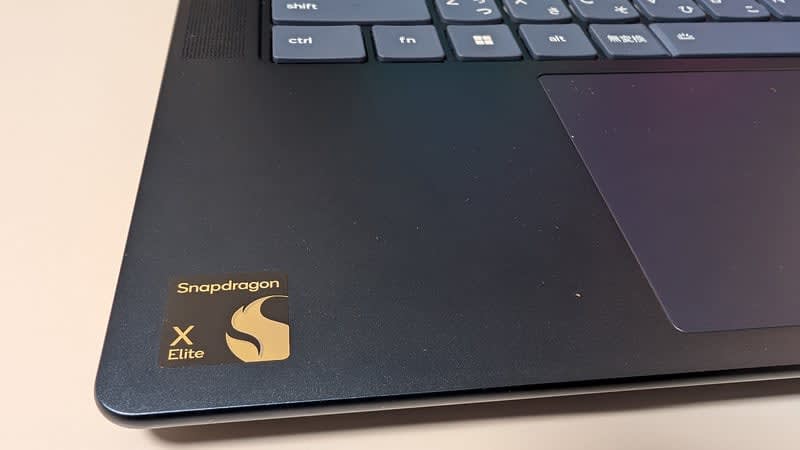
今週、2024年6月17日(月)にCopilot+ PCの発売が始まった。AIのために設計された新カテゴリのWindows PCであるという。これまでで最も高速でインテリジェントなWindows PCであるという。果たしてどんなPCなのか。各社にお願いして早速体験させてもらった。
PCローカルでAIを使えるようにするための最低限装備
MicrosoftからWindows OSの提供を受けたハードウェアOEMパートナー各社が、それをプリインストールして出荷するという点では、既存の市販PC製品と何も変わらない。だが、この新しいカテゴリのCopilot+ PCを名乗るためには、Microsoftの定めた最小要件をクリアする必要がある。
その要件は下記とされ、これはWindows 11の既存の最小システム要件への増分要件として規定されている。
- 承認されたリストのプロセッサまたはシステムオンチップ(SoC)。承認された一覧には、ニューラル処理ユニット(NPU)と40兆以上の1秒あたりの操作(TOPS)が組み込まれているプロセッサまたはSOCのみが含まれる
- RAM: 16GB DDR5/LPDDR5
- ストレージ: 256GB SSD/UFS以上のストレージデバイス
2と3については、今時のPCならすでに一般的と言ってもよさそうだ(後で書くが、真の意味で一般的になってほしい)。
だが、1ではプロセッサやSoCについて、NPUの統合と40TOPSが求められている。今のところ、この要件を満たせるプロセッサとして流通している製品は、QualcommのSnapdragon Xシリーズしかない。
同社はこのシリーズのプロセッサとして、12コアCPUのX Elite、10コアCPUのX PlusをWindows用プロセッサとして各社に供給している。そのNPUは45TOPSと、Microsoftの規定した最小要件を上回る。
TOPSはNPUの処理性能を示す単位として知られている。CPUやGPUのコアクロックはGHz単位で示されることが多かったがNPUはテラの単位、つまりゼロの数が3桁多く、それをTOPSという単位で表す。Trillions of Operations Per Secondの頭文字をとったもので、CPUなどの計算能力を示す浮動小数点演算能力を示すFLOPSとは異なる、製数演算の能力を反映した指標として使われる値らしい。
次世代のWindows PCには、CPUとGPU、そしてマシンラーニング向け専用に設計されAI処理(画像認識、音声認識、自然言語処理などの新しいAI体験)を高速に実行できるNPUの3種類のプロセッサが統合されていることが求められるというわけだ。
つまり、今回のCopilot+ PCは、PCというデバイスローカルでAIを使えるようにするための最低限装備を持っていることが保証された製品だということになる。
AI処理の多くはクラウドで行なわれることが多かったが、AI処理のために求められる処理性能を持つことで、ローカルでさまざまなAI処理ができるようになり、プライバシーとセキュリティ、応答速度の速さが確保でき、インターネット接続の有無などに関係なく、いつでもどこでもAIを利用できる環境が手に入る。それがCopilot PCだ。
だが、消費電力さえ気にしなければ現状のGPU処理でも40TOPSはかなうはずだ。今1つGPUの処理性能を生かし切れていなかった層のユーザーには、AIという新しいパートナーがその環境を駆使してくれるのはありがたいと思ったりもする。そのあたり、MicrosoftがNPU統合機だけに、Copilot+ PCを想定していることの真意がつかめない。
なお、今回のCopilot+ PCは、まず、コンシューマ向けの提供となり、OSはWindows 11 Homeとなっている。また、そのバージョンは24H2で、既存のWindows 11環境にはまだ配信されていない。
アプリやサービスがなければNPUも働けない
今手元にあるのは15型のMicrosoft Surface Laptop(第7世代)と、14.5型のLenovo Yoga Slim 7x Gen 9だ。どちらもSoCとしてSnapdragon X Elite X1E-78-100を搭載、GPUはQualcomm Adreno、NPUはQualcomm Hexagonとなっている。たまたまだが32GBメモリ、1TB SSDというのも同スペックだ。
現時点での、Copilot+ PCは、Windows Home Editionをベースとし、そこに、
- Cocreator : 標準アプリのペイント内で稼働し、テキストプロンプトと実際の描画をもとに画像を生成
- Windows Studio Effect : 内蔵Webカメラ映像のAI処理による制御、補正
- Live Captions : PCで再生される音声を英語に翻訳してリアルタイムで字幕表示する。他言語への対応は先
- Recall : PCでの行動を記録し、あとでさかのぼることができる機能。まだInsiderPreview段階で一般への開放は先になる
が追加で提供される。
具体的にはAI機能を提供する上記アプリを添付したWindows HomeがOEMパートナー各社に提供され、それをプリインストールして出荷されることになる。
これらのAI機能はCopilot+ PCであることがOSによって検知された環境でのみ有効となり、過去の製品がCopilot+ PCと同等にこれらの機能が使えるようになることはないそうだ。
つまり、今回のCopilot+ PCのNPUを生かせるアプリやサービスが続々と登場という状況が起こらない限りは宝の持ち腐れになる可能性だってある。そもそも、今回の追加機能のうち完全にローカルで行なわれるAI処理はそれほどでもなく、40TOPSを持て余しているかもしれない。
これは過去にGPUがPCの新しい当たり前になった当時の状況に似ていなくもないし、もっと言えば、マルチコアプロセッサがシングルスレッドアプリのためにあまり役に立たなかった時代も彷彿とさせる。
来春までのモラトリアムか
Copilot+ PCへの一番乗りはQuallcommのSnapdragon Xシリーズに先を譲ってしまったが、Windows PC用プロセッサの老舗として長く製品を提供してきたIntelもAMDもNPUに注力した新製品を準備中だ。
秋冬のOEM各社の新製品に間に合うかどうか、また、Windows 11 HomeではなくWindows 11 Proでの稼働はどうか、MicrosoftのクラウドAIとの併存はどうなるのかなど、いろいろと気になることは多い。
PCは必要なときが買い時だということは分かっていても、これだけ近い将来のロードマップが明確に見えていると、さすがに、相当な新しもの好きでも登場したばかりのSnapdragon搭載Copilot+ PCに飛びつくわけにはいかない。
特に、今回はWindows 11 Homeでの提供ということで、企業ユーザーにとっては、正式にWindows 11 Proをサポートしたビジネス向けのCopilot+ PCを待ちたいという意向もありそうだ。
ビジネス向けCopilot+ PCとしては、すでにHPがHP EliteBook Ultra G1q AI PCを発表済みで、同様にSnapdragon Xシリーズ搭載で準備が進められている。こちらは発売前の試用機をさわらせてもらっている最中だ。
今回の重要なポイントは、AIというトレンディな要素が人々の暮らしや仕事で一般に使われるPCのハードウェアスペックを底上げしそうなことだ。
Windows 11のシステム要件に対して、
- メモリは4GBから16GB以上へ
- ストレージは64GB以上から256GB以上へ
という増分がある。AIがAIらしく仕事をするための必要なスペックであると同時に、AIを使う人間にとっても役に立つ、というか、そのくらいないと困ることが経営側に分かってもらえず困っている現場も少なくない。
そのような現状では、AIがなくては組織が成り立たないといったこじつけでも通して高スペックのPCを調達することに貢献するかもしれない。
AI PCの世代では、これまでのWindows PCを牽引してきたIntel、そしてそれを追いつけ追い越せで健闘してきたAMDに加え、さらにQualcommというキャストが加わる。その三つ巴の行方はいかに。
きっと来年の春頃には方向性が見えているだろうけれど、脇目もふらずに走り続けてきたPCの世界ではこんなに長いモラトリアムは珍しい。
