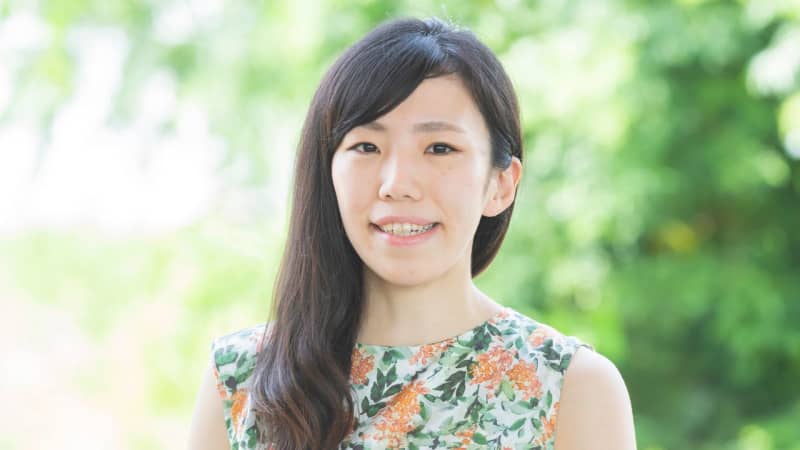
住まいがなく、やむを得ずインターネットカフェなどに宿泊している人がいる。その中には、20代などの若者も…。
ホームレス状態といっても路上生活をしているとは限らず、生活困窮者の在り方は多様化している。
そんな中、「ホームレス」を支援する団体が、幅広い生活困窮者を受け入れる“シェルター(宿泊施設)”を2023年に設立した。ホームレス問題の現状や、シェルター設立の経緯などを聞いた。
■近年は相談者の半数近くが30代以下
生活困窮者を支援する「認定NPO法人Homedoor(ホームドア)」。
「ホームレス状態を生み出さない」を理念に、大阪でシェルターの運営や就労支援などを行っている。シェルターとは、帰る場所がない人に無料で宿泊できる個室を提供する施設のこと。
14歳の頃にホームレス問題を知り、以来20年近く問題に取り組んできた理事長の川口さんは、「誰でもホームレス状態になる可能性があると思う」という。
ホームレス状態になる理由は人それぞれだが、家庭環境のような自分では選べない要因が絡んでいたりして、自ら望んでそうなる人はいない。
一度ホームレス状態に陥ると、住居や電話がないことで就職活動が難しくなり、仕事がないと住居や携帯電話を確保できないという状況になるため、自力で抜け出すのはほぼ不可能だといえる。
そうした中で、行政の支援だけではあらゆる生活困窮者に細やかに対応しきれないため、民間の支援団体の存在はとても重要だ。
2010年から活動する「Homedoor」には、毎年1000人以上の人が相談に訪れている。
当初、相談者は高齢男性が多かったが、2017年頃からは、30代以下が増えてきたそう。
Homedoor 理事長 川口加奈さん:2022年度は、当団体への相談者の半数近くを10~30代が占めています。団体の認知度の向上や、個室の宿泊場所を提供していて、若い人が来やすくなったことも理由だと思います。
生活に困った時、一般的には親に頼る人が多いと思うが、団体が支援する若者は、頼れる存在がいない人が多いという。
Homedoor 理事長 川口加奈さん:2018年に設立した『アンドセンター』というシェルターの利用者のうち、10~20代の約25%が虐待経験者、約10%は児童養護施設や里親家庭の出身だと分かりました。親に頼れない人が多いんです。あくまで自己申告なので、実際はもっといるのではないかと思います。そもそも頼れる人がいるなら、相談に来る必要がないですし。
例えば、児童養護施設の出身者が抱える問題とはどのようなものなのだろうか。
まず、施設で暮らせるのは通常、18歳まで。20歳や22歳まで暮らせる施設もあるが、本人が居心地の悪さを感じていたり、施設の人手不足などで、成人後もケアするのは難しいという実情もある。
施設を出る際は、就職や住居確保などの支援を受けられても、転居時は保証人などを頼める人がおらず、賃貸契約が難しくなることも。
さらに、大学に進学していない人が多く、学歴が就業の障壁になるケースもある。
施設出身者に限らず、“頼れる親がいない”という状況の厳しさは、想像に難しくない。
■相談者層の変遷と長期支援の必要性
「Homedoor」が2018年から運営しているシェルター「アンドセンター」では、相談者に無料で宿泊場所を提供している。
大阪市には行政が設置したシェルターもあるが、個室がないため、個室で安心して宿泊できる環境を提供するために設立された。
「今日寝るところがない」人に部屋を貸す、主に緊急対応に特化した施設。原則2週間の滞在中に、仕事・住居探しなどをサポートしてきた。
以前は、路上生活をする高齢男性が支援対象の中心だったが、徐々に若者や女性、親子で相談に訪れる人も増えてきた。
さらに長期滞在・長期支援のニーズも増加し、シェルターでは新規の受け入れが困難になった。施設内にはエレベーターがないため障害者や高齢者は利用しづらく、住所が公開されていて、DV被害者などには不安があるといった課題も…。
そこで「幅広い相談者を長期的に支援する施設」として生まれた、新たなシェルターが「アンドベース」。対象者は大きく以下の3つだ。
①頼れる人がいない若者
②母子世帯やDV被害者
③高齢者など体が不自由な方
DV被害者などに配慮し、住所は非公開。エレベーターやオートロックが完備された物件を5億円で購入し、2023年春から運営を始めた。
新施設は現在すでにほぼ満床状態だそう。利用者は10~60代で、20代が最多。施設内で若者向けの就労支援セミナーなども実施予定とのこと。
実際にアンドベースを利用している相談者の方にも話を聞いた。
Q.どういった経緯でHomedoorを訪れたのですか?
Aさん(60代女性):路上生活をしていた2023年にHomedoorの方にお弁当をもらい、ここに頼ることにしました。区役所に紹介してもらった施設にお世話になったこともありましたが、集団生活が辛く、飛び出してしまったんです。こちらに相談した頃から体調の異変がありましたが、現在は個室で生活し、施設から通院しています。感謝しかありません。
同団体では、路上生活者に弁当を配るなど、団体の認知度を高めるための活動も積極的に行っている。
■多様な「選択肢作り」を大切に
活動を行う上での課題や、今後についても尋ねた。
Homedoor 理事長 川口加奈さん:シェルターを運営していくには、寄付をしていただく“サポーター”が必要です。サポーターが集まり次第ですが、心理的なケアが必要な相談者のために心理カウンセラーを配置したいです。行政の課題を民間として担っていく上で、法人・個人の寄付に頼らざるを得ませんが、思うように集まらないこともあり、経済的な問題は大きいです。
アンドベースでは、毎月1000円の寄付をする「サポーター」を募っている。目標は3000人だが、現時点では900人ほど(2024年6月現在)。
事業や講演会などの収益もあるが、寄付の必要性が大きいため、ホームレス問題の啓発にも積極的に取り組んでいる。
取材した中で、川口さんの「ホームレスをゼロにすることが目標ではない」という言葉が印象的だった。
Homedoor 理事長 川口加奈さん:“選択肢作り”を大切にしています。『ホームレス状態から脱出したい』と思ったら脱出できる、そのための選択肢が多様にある状態を目指しています。
自己責任論や、『本人が悪いのでは?』という考え方もあるかもしれませんが、困窮した状態から脱したいと思った時に脱する方法があるのか、ないのか。どちらがいいか考え、脱出の方法をたくさん作れるよう活動しています。賛同いただける方は応援していただけたらうれしいです。
支援団体の存在を知っても、自らの状況に諦めている当事者もいるという。
それぞれに複雑な思いを抱えている人たちに支援を押しつけず、多様な「選択肢」を用意する。「やり直したいと思ったらやり直せる社会」を目指すHomedoorの活動に、これからも注目したい。
