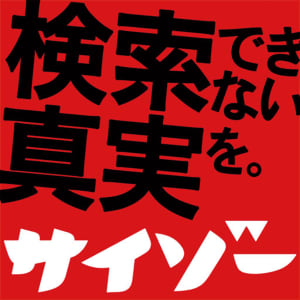──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・NHK「大河ドラマ」(など)に登場した人や事件をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく自由勝手に考察していく! 前回はコチラ
前回の『光る君へ』、「忘れえぬ人(第24回)」には、困惑のあまり「どうして」とテレビ画面に語りかけてしまうシーンがけっこうありました。「日本との貿易を公式に再開する」というミッションを宋の朝廷から与えられた宋人たちの手先の周明(松下洸平さん)が(自分に好意を抱いているらしい)まひろ(吉高由里子さん)を抱きしめたり、キスしようとしたものの、まひろからは「(あなたは)嘘をついている。私を好いてなぞいない」と本心を見透かされ、叩き割った壺の破片を彼女の首元に突きつけて「左大臣(道長・柄本佑さん)に交易再開を求める手紙を書け」などと脅迫した一幕には、たいそうガッカリさせられました。
それでも毅然と対応したまひろに、周明は「宋はお前が思っているような国ではない」「宋は日本を見下している」「民に等しく機会を与える国などこの世のどこにもない」と言い捨て、その場から逃げ去っていったのですが、まひろ同様に視聴者の中でもジワジワと高まってきていた周明の好感度が一瞬にしてゼロ以下になるという、まさかの展開の数々に驚愕させられました。
しかもその後の場面での宋人の上司・朱仁聡(浩歌さん)のセリフから推測すると、周明は本心ではまひろが好きだったらしく、我々は何を見せられていたのだ……というさらにガッカリな結末を迎えてしまいました。要するに「ハニートラップ」にかこつけるしか、自分の好意もまひろに伝えられないチキン野郎だったのか、という話です。
たしかに宋王朝時代の中国においては「生まれた身分にとらわれず、才能ある者を国家の役人として取り立てる」という名目で「科挙」が行われていましたが、この厳しい試験に合格するには優秀な家庭教師を雇い、子どもたちを勉強にだけ専心させ得る富裕層が圧倒的に有利でした。当時の日本以上に、あるいは現代日本同様に、宋での「科挙」合格には「親ガチャ」要素が重要だったというわけです。
また、宋の時代から上流階級の女性には、不自然なまでに小さな足が要求されるようになったといわれ(諸説あり)、幼女時代から足を布できつく縛るなどの「纏足(てんそく)」という悪習が根づきつつありました。纏足とは、男性が女性の身体を自分の「おもちゃ」のように公然と弄ぶための準備です。仮にまひろが宋に行くことがあれば、彼女は「日本人」で「女性」であるということに加え、「纏足」をしていないため、日本以上に生きづらい日々が待っていたのではないでしょうか……。
まひろと周明のロマンスが不発に終わる一方、京都では一条天皇(塩野瑛久さん)による中宮・藤原定子(高畑充希さん)への妄執がすさまじく、ついには内親王を産んだばかりの彼女を宮中に帰還させることになりました。史実でも「宮中復帰」後の定子が滞在したのは、宮中・内裏の建物から見て北東方にあった「中宮職(中宮に関する仕事を任せられた役人)」の政庁という意味の「職御曹司(しきのみぞうし)」という建物だったので、出家した定子を厳密には宮中に戻らせたわけではない……という、まことに苦しい言い訳つきの帰還ではありました。
そのような「配慮」をしたところで、すべてに対して公明正大でいなくてはならない現役の天皇が、出家した女性と復縁するなど完全なタブー破りで、当時の倫理的ルールを無視したとんでもない行為でしたから、世間の批判の的になってしまったようです。ドラマ同様、藤原実資(秋山竜次さん)は批判めいたことを日記『小右記』にサラッと書き込んでいます。
『小右記』の「長徳三年六月二十二日の条」によると、彼が体調不良の藤原詮子(東三条院・吉田羊さん)のお見舞いに出かけたという記事に続き、「今夜、中宮が職御曹司の建物にお移りになった」と記し、「天下甘心(かんしん)せず」と批判しています。興味深いのは、「彼宮(中宮定子の周辺)」の人々が「(定子さまは)出家せずと称し給う云々」という部分です(原文を書き下し)。
実資は『小右記』の「長徳二年五月二日の条」において、「后昨日出家給云々」――「中宮定子さまは昨日、出家なさった」という中宮職の役人の談話を書き記しており、職御曹司にいる定子の取り巻きが、「本当は定子さまは出家していない」などと嘘を喧伝していることに不審の念を抱いていることがわかります。
定子が滞在した職御曹司とは、『枕草子』によると「木立は古びて建物も恐ろしげ」な廃屋同然の建物だったようです。同書には「初めて官職にありついた六位の蔵人が、職御曹司の壁板をはがして笏(しゃく)にする」という驚きの風習についても触れられています。職御曹司が普段は使われていなかったのをいいことに、建物の一部(具体的には辰巳の方角にある壁の木材)が新米役人たちの手でこそぎ取られ、当時の官僚たちが現代のメモ用紙の代わりに手にしていた笏の材料にされていたわけですね。
しかし、そんな廃屋同然の建物にもかかわらず、天皇は頻繁に定子を訪ねてきたようですし、定子もお産などの時に別の建物に移動する以外は、2年以上を職御曹司で過ごしていたのです。
ただ、中宮とその側近たちという大人数がスムーズに移り住むことができるような規模の「空き家」が、なぜ存在していたのかを疑問に感じる方がおられるかもしれません。職御曹司の建物が使われていなかった本当の理由は、そこが「鬼」が住む家だとされていたからのようです(斎藤雅子『たまゆらの宴―王朝サロンの女王藤原定子』文藝春秋)。現代とは比べ物にならないくらい迷信深かった平安時代に、いくら一条天皇から強く求められたとはいえ、「鬼」の住処に移住してしまう藤原定子、そして彼女に付き従った清少納言(ファーストサマーウィカさん)などの女房たち、そして一条天皇もかなり「強気」だったことが推察できますね。
ちなみにドラマでは一条天皇が定子におぼれて政務がおろそかになってしまうという描かれ方でしたが、史実の一条天皇は若年ながら(当時20代前半)、政務に熱心な帝だったと知られています。
長保元年(999年)には一条天皇そして道長による主導で、深刻な社会不安を鎮めるべく、「制美服行約倹事(服装の贅沢禁止)」などが定められました。同時に「仏神事違例(仏事・神事における違反)」も戒められたのは、いかにも平安時代ですが、天皇みずから自分が定めた「新制(新しい制度)」を役人たちが厳密に守っているかを監視し、不満な場合は蔵人を通じ、注意していたことまでがうかがえるのです(藤原行成の日記『権記』)。
ドラマに描かれていた定子との情事に溺れる一条天皇のイメージについては、平安時代後期成立の歴史物語『栄花物語』などに、中国・唐王朝時代の玄宗皇帝と楊貴妃の悲恋を重ねているのでしょう。玄宗皇帝と楊貴妃のエピソードをまとめた『長恨歌(ちょうごんか)』は、平安時代の人々の間でも広く親しまれている書物でした。
『光る君へ』の道長はあくまで情け深い「正義のヒーロー」ですが、史実では天皇と定子の前に立ちふさがる存在であった道長をどのようにドラマの中では美化していくのか、大石静先生の脚色が楽しみというしかない状況です。
また、ドラマでは中宮定子の職御曹司入りを、藤原行成(渡辺大知さん)が発案するという描かれ方でしたが、史実における発案者はよくわからないものの『枕草子』では、清少納言の同僚たちが行成のことをあまりよく言わないのに対し、清少納言だけは彼を弁護して「なほ奥ふかき心ざまを見知りたれば」――私は、彼(行成)の心の奥深い部分までをよく知っているから……などと書いている部分があるのです。こういう人間関係を、ドラマでは「発案者・行成」という形で反映したのかもしれませんね。
<過去記事はコチラ>