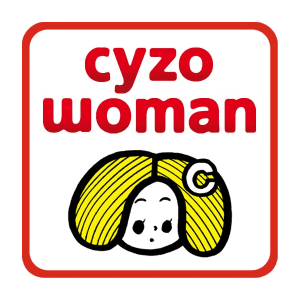歴史エッセイスト・堀江宏樹氏が今期のNHK朝のテレビ小説『虎に翼』を歴史的に解説します。
目次
・家庭裁判所の創設が急務だったワケ
・少年による「殺人」は戦前の2~3倍にまで増加
・戦災孤児にならなくても……
・ヒロポンが田舎の子どもにまでまん延、覚醒剤中毒も
家庭裁判所の創設が急務だったワケ
NHKの朝ドラ『虎に翼』も、第12週目に入りました。先週=第11週から「愛の裁判所」こと家庭裁判所の設立が描かれていますが、戦後の日本社会の大問題となっていた戦災孤児たちが、まるで捕獲されるかのように「保護」される姿に衝撃を受けた視聴者もおられると思います。戦災孤児が描かれた「朝ドラ」は、記憶するだけでも『なつぞら』(2019)などがあったと思いますが、『虎に翼』での描写はなかなかにシビアですね。
ドラマにも戦災孤児たちを率いて、窃盗集団を結成していた道男(和田庵)など問題を抱えた新キャラクターが登場しました。道男のやさぐれ加減が、ドラマ『3年B組金八先生』時代の近藤真彦さんみたいだという声もありました。道男を演じる和田庵さんは現在18歳だそうですが、すでにさまざまな新人賞を受賞しているホープだとか。よくあれだけ「戦後の空気」を身にまとうことができるなぁ……と、彼の才能には驚いてしまいました。
今回のコラムのテーマは戦災孤児の問題、そして戦後日本の治安は実際にはどうだったのかというお話です。犯罪史をひもとくと、戦争をした国の犯罪増加率は急増するものだと相場が決まっているそうですが、戦後日本も例外なくその通りになってしまいました。
とりわけ急増するのが少年犯罪だそうです。日本軍の敗色が濃厚になってきていた昭和18年(1943年)の少年犯罪発生数を「100」とすると、終戦の翌年にあたる昭和21年(1946年)には「182」――つまり少年犯罪は3年前より82%ほど増加してしまったという驚がくの数値が出ているのです(法務省矯正局『戦後における矯正の歩み』、昭和30年・1955年)。
さらにその2年後、昭和23年(1948年)には少年犯罪の発生数を示す数値が「202」にまで達してしまい(つまり戦中の2倍)、その後も「高止まり」したままでした。
ドラマでは具体的な背景までは触れられませんでしたが、昭和24年(1949年)1月1日の家庭裁判所の創設が急務だったのは、少年犯罪の発生件数が激増したまま落ち着く気配がないという深刻な社会不安があったからでしょう。
少年による「殺人」は戦前の2~3倍にまで増加
ドラマの道男同様、当時の少年犯罪のうち、7〜8割程度がスリや置き引きといった「窃盗」だったという報告もあります。しかし「窃盗」だけでなく「強盗」にまで手を染める子どもたちもおり、さらに少年による「殺人」は戦前の2~3倍にまで増加してしまい、なかなか数値が低下しないままだったそうです。
少年犯罪だけでなく、成人による犯罪も戦前以上に増加していたのですが、もっとも増加した昭和25年(1950年)でも4割程度の増加にとどまりました。
また、当時の少年犯罪の大半が、戦争によって家庭を失ってしまった戦争孤児たちによるものだったという事実を考えると、戦争による生活の変化と、その悪影響を直接被ってしまったのは大人ではなく、子どもたちだったのです。
ちなみに戦勝国だったアメリカ国内でも犯罪件数――とりわけ少年犯罪が激増したという興味深い報告があります。日本はアメリカから何度も空襲を受けたり、手ひどくやられてから敗戦したがゆえに、少年犯罪などの問題がいっそう激化した側面はあるでしょうが……。
戦災孤児にならなくても……
またドラマではいくら家庭裁判所とはいえ、裁判所職員であるはずの虎子たちが、現在の市役所の福祉課の職員のような仕事をしているのを見て驚いた方もおられるでしょうが、ドラマの虎子のモデルである三淵嘉子さんも戦災孤児たちのために、必死で仕事に取り組んでいたそうです。
戦災孤児にならなくて済んだ子どもたちも、戦争中の空襲で家を焼き払われてしまい、狭い貸家に家族で住むことになり、あまりの狭さにストレスを感じて家出するケースが多かったし、狭い部屋で雑魚寝していたはずの両親が夜の営みを始めてしまい、それを何度となく目撃するうちに羞恥心がマヒして、売春などの問題行為に走る子どもなども多発したとか……。
何らかの理由で家庭から居場所を奪われた子どもたちが家出して、集団で暮らすようになる構図は、最近の日本社会でも社会問題になっている「トー横キッズ」などと似ているように感じられます。安易な比較はできませんが、現代日本の(一部の)家庭内の治安は戦後すぐのレベルにまで落ちてしまっているのかもしれません。
戦前日本では、家庭の父親が家長であり、父親がいない家庭では長兄などが実質的な家長として「正義」や「道徳」を体現できていたとされるのですが、そうした家長制度が名実ともになくなってしまった戦後では、自由が訪れた半面、道徳の崩壊に歯止めが利かなくなった時期が続き、それが子どもたちに悪影響したといえるでしょう。
まっとうな父親、そして母親(もしくはそれに類する存在)たちが子どもたちを指導監督するという「伝統的な家庭」の構図が名実ともに崩壊していると、それが少年犯罪の温床となることを立証してしまったのが、戦後すぐの日本社会だったのですね。
戦後の混乱期では、子どもたちの前でどのように振る舞うことが、まっとうな父(あるいは母)の証しになるか、誰にもわからなくなっていた部分も悪影響したのかもしれません。
第10週でのシーンだったと思われますが、相続法など民法改正のための議論の席上で「戦敗国だからこそ、戦前日本の家庭道徳を守り抜かねばならない!」などと主張していた神保教授(木場勝己さん)は、ドラマでは悪役めいた描かれ方でしたが、神保教授もたんなるガンコな保守主義者というわけではなく、社会の問題に法律家として向かい合わねばならないと考えぬいた末の発言だったのでしょう。またドラマでは描かれませんでしたが、史実ではそれほど「伝統的な家庭の崩壊」が原因と思われる犯罪が多発し、社会不安が増大していたのだとも考えられます。
ヒロポンが田舎の子どもにまでまん延、覚醒剤中毒も
なお、戦後日本を覆っていた最悪の経済状態は、昭和25年(1950年)、朝鮮戦争の勃発と共に大幅に改善されました。日本は新憲法で不戦をうたっていたので参戦はしなかったものの、アメリカの参戦を日本は「同盟国」として支えることになったので、軍事産業などを中心に経済が回り始めたのですが、金回りが良くなればなるほど、太平洋戦争に敗戦した後から続く社会不安は逆に悪化したという興味深い調査もあります。
要するに、道徳が荒廃した社会にお金だけが流れ込むと、なにも良いことは起きないということですね。
昭和26年(1951年)には「ヒロポン」と呼ばれ、気軽に市販されていた覚醒剤が、都市部だけでなく田舎の少年たちの間でもまん延し、少年犯罪のうちの1割が、覚醒剤中毒の子どもの手によるものになってしまったそうです。なかなか衝撃的な数値ですね。
「朝ドラ」ではとても描けないような社会不安が、戦後日本には蔓延していたのです。戦争の恐ろしさは、なにも戦時中だけの問題ではないのだな……と痛感してしまいました。