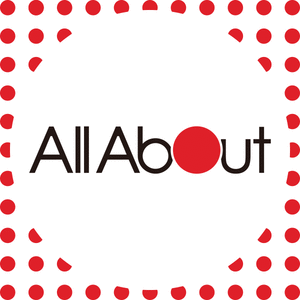最近、「反応閾値(はんのういきち)」というワードが話題になっています。「反応閾値」が違う人と関わるとイライラしやすいと言われます。どうすればいいのでしょうか?
「反応閾値」って何?
反応閾値とは、「どれだけの刺激があると、行動に移すようになるのか」の限界値のことです。例えば、「どれだけ部屋が散らかっていると、掃除しようとするのか」「どれだけ体重が増えると、痩せようと思うのか」とか。 掃除でいえば、床に髪の毛が数本落ちているだけで、ササッと掃除機をかける人もいれば、部屋がゴミだらけになっても、捨てようとしない人もいます。前者は、反応閾値が低く、後者は高いのです。言い方を変えれば、「反応閾値が低い=敏感」「反応閾値が高い=鈍感」とも表現できます。 ただし、反応閾値が低い人が、どんなことに対しても低く、逆に反応閾値が高い人が、何に対しても高い、というわけではありません。掃除は小まめにするけど(=反応閾値が低い)、LINEの返事は遅い(=反応閾値が高い)こともあります。 また、反応閾値が低いのと高いのとでは、どっちがいいのかというのは、ケースバイケースです。反応閾値の低い人は、敏感に反応するので、よく気付きますが、反応閾値の高い人は、鈍感な分、大らかさがあることもあります。ただし、極端に低かったり、高かったりする場合は、相性の合う人は限られてくるかもしれません。
「反応閾値の差」がけんかの原因に……
人と関わるときに反応閾値があまりに違うと、けんかになりやすくなります。 例えば、夫婦が部屋の清潔度において反応閾値が違うと、ストレスがたまることは多いでしょう。部屋の清潔度において、妻は反応閾値が高く、夫は低い場合だと、汚れが気になってしまう妻ばかりが掃除をすることになりかねません。 妻がしびれを切らして夫に掃除するのをお願いしても、夫にとっては散らかっていないと感じるので、「なぜ、この段階で掃除をしなくてはいけないのか。潔癖症の人との生活は疲れる」と思うこともあるでしょう。 LINEの返事も同様です。来たらすぐに返事をする人もいれば、未読のままずっと放置していても平気な人もいます。すぐに返事をするタイプの人は、いつまでも未読のままにする相手に対して、イライラしてしまうこともあるでしょう。
反応閾値が違う人とは「ルール」を設けるべし
結局、反応閾値というのは、「感覚」です。感じ方は人それぞれなので、相手に合わせてもらおうとしても、逆に自分が相手に合わせようとしても難しく、「感覚を頼りにした判断」に頼ったままでいると、仲違いしてしまいます。 だから、具体的にルールを設けた方がいいでしょう。例えば、部屋の清潔度においては、「2日に1回は掃除機をかける」「メールの返信は、できるだけその日中にする」など。 ただし、反応閾値が違う人とルール作りをする際には、苦労することも多いです。感覚に正解があるわけではないので、「自分の方が正しい、相手がおかしい」という態度をとってしまうと、必ずけんかになります。 どちらか一方が正しいわけではなく、「自分と相手で好みが違う」くらいの感覚で、話し合うようにした方がいいでしょう。 さらに、ある程度は、ルールを作ることで問題をクリアすることができても、あまりにルールが多くなってしまうと、互いにきつくなってきてしまいます。ルールはある意味、「制限を設けること」でもありますしね。 また、一方的にどちらかの反応閾値に合わせる形になってしまうと、もう片方が我慢の限界に達したとき、関係が壊れることも多いでしょう。だから、結局は、互いに“そういう人”だと思って、理想通りになることは諦め、折り合いを付けながら付き合うことが必要になってきます。
反応閾値の近さ=相性、付き合う上でのバロメーター
ルールを決めたり、折り合いをつけたりしても、あまりに反応閾値が違う場合は、互いにストレスを溜めてしまうことがあります。 その場合は、「相性が合わない」ということ。深い関係であればあるほど、互いに自分らしくいるためにも、関係を解消した方がいいケースもあります。別れなくても、別々に暮らすことでうまくいくこともありますしね。 結局、「いくら好きでも、相性が合わなくて一緒には生活できない相手」というのは存在します。反応閾値の近さは、相性の1つ。共に人生を歩める相手かどうかのバロメーターになることもあるでしょう。 (文:ひかり(恋愛・人間関係ガイド))