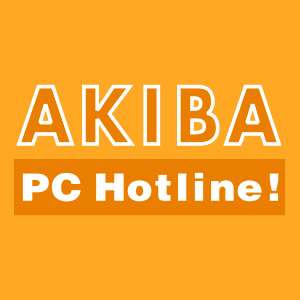by 佐々木 潤
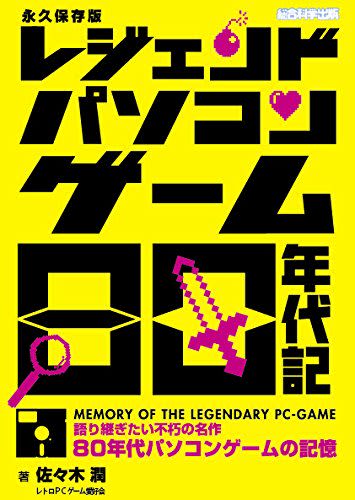
連載「ボクたちが愛した、想い出のレトロパソコン・ゲームたち」の番外編として、この記事では総合科学出版から発売されている「永久保存版 レジェンドパソコンゲーム80年代記」(著:佐々木 潤・レトロPCゲーム愛好会)の一部記事を抜粋し、紹介しよう。
今回取り上げるページは、“2スロット搭載というハードのメリットを活かしたROMカートリッジ2本挿しテクニック”だ。なお、書籍版では画像はモノクロだが、諸事情により本記事では一部カラーや別の写真を掲載している。
2スロット搭載というハードのメリットを活かしたROMカートリッジ2本挿しテクニック(?)
1スロット目に遊びたいゲームを、2スロット目にPACを挿してデータ保存

MSXには“スロット”と呼ばれる拡張手段が用意されており、どの機種でも最低1つは備えられていた。一時期を除けば2スロット装備のものがほとんどで、それを利用してROMカートリッジを2本挿して遊ぶタイトルが登場する。そのスタイルは大別すると2種類で、1つはゲームのセーブ先として使うもの、もう1つがゲーム単体では行えない部分を変更するためのものだ。
ゲームのセーブ先として使われる目的のものは、1987年に発売されたパナアミューズメントカートリッジ(PAC)と、その後継であるFMパナアミューズメントカートリッジ(FM-PAC)だ。スロット1にゲームを、スロット2にPACまたはFM-PACを挿入してプレイすれば、対応しているゲームならセーブデータをカセットテープではなくPACやFM-PACに保存できた。フロッピーディスクの一部のゲームでも、セーブ先にPACかFM-PACを指定できたため、一瞬でセーブし終わるという利点がある。当時の価格も、PACは3,800円、FM-PACでも7,800円と高くはなかったのと、FM-PACは名前の通りFM音源を搭載していたこともあり、大ヒットとなっている。データの保存にはSRAMが用いられていた。

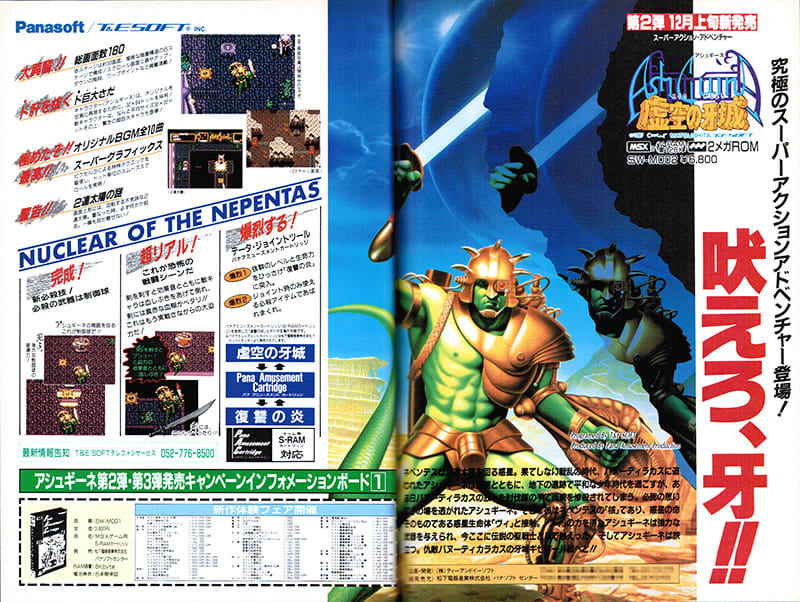

1スロット目に遊びたいゲームを、2スロット目に別のゲームを挿し各種メリットを享受
後者に関しては、ゲームカートリッジを挿すものと、パワーアップ専用のROMカートリッジを挿すものの2種類にわけられる。有名なのは、スロット1に『グラディウス』を、スロット2に『ツインビー』を挿して起動すると、『グラディウス』の自機がビックバイパーからツインビーに変わるというもの。これがきっかけで、のちに『パロディウス』が生まれたという話もあるほど。単なるキャラチェンジだけではなく、カートリッジの組み合わせ次第で各種の設定が変更(俗にいう裏技が使用)できた。


いくつか、有名な例を挙げてみよう。スロット1に『グラディウス2』、スロット2に『Qバート』を挿せば、ゲーム中にF1でポーズをかけて特定のキーワードを入力することで、無敵になったりフルパワーアップすることができた。
『ウシャス』では、スロット2に『魔城伝説II ガリウスの迷宮』『メタルギア』『F1 スピリット』を挿すことで、それぞれ有利にゲームを進めることが可能だ。スロット1に『魔城伝説II ガリウスの迷宮』を、スロット2に『魔城伝説』ならば、自機のストックを99にできる。しかし、これらパワーアップだけでなく、スロット1に『沙羅曼蛇』、スロット2に『グラディウス2』を挿し込んでおかないと、『沙羅曼蛇』で最終面をクリアしたとしても真のエンディングが見られないという酷いものもあった。さすがに、このような仕様はのちのゲームには見られなかったが、当時はかなり話題になったものだ。

一部の画像は、書籍版とは異なるものを掲載している場合がございます。