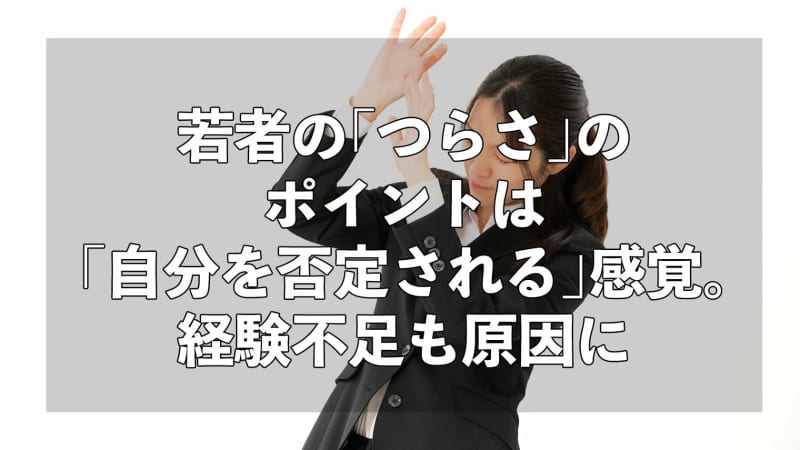
第5章 適応障害についての疑問・2
就職という変化
もうひとつは、この勉強の仕方と関連があると思います。勉強は親や教師が言うことをすればよい、自分で考えることではなく、従い、行えばよい。時として(多くはお金を支払えば)何度でもやさしく教えてくれますし、結果の責任もそのプログラムを提供する側が保証してくれます。うまく行かない場合は、教師なり塾講師なりの責任になるかもしれません。そして下にも置かない様相で勉強していただく。
就職戦線を勝ち抜いて就職し、「どうですか?」と聞いたら「上司が上から目線でモノを言う」と言ったツワモノもいたようですが、すべてを用意され勉強をしていただいていた延長線上に働くことはありません。
つらさのポイント
次に若者のエピソードから、彼らがつらいと感じていることを3つほど、他にもあると思いますが、ピックアップしてみます。
①注意される、叱られる
実際に大きなミスをしたのかまずいことをしたのかわかりませんが、指摘されたり注意されたり叱られたりしたことが、仕事がつらいと感じる契機になっていることが多いです。
注意や叱責は珍しいことではありませんが、その程度も重要です。たびたび𠮟られる、強烈に言われる、そうすると傷つき、すべてを否定されたように感じ、「自分は仕事ができない」「自分はダメだ」と思うかもしれません。
実際の能力やその状況についてはその場にいるわけではないのでわかりませんが、誰が見てもひどい言われ方をしたのか能力がないのかを別として、この注意される、叱られる、自分が否定されるということに強く反応していることがうかがえます。
誰だってイヤです。
程度の差もありますが、初めて仕事をする場合、ある程度仕方がないのです。しかしそれにつまずくと、そこから先には進みにくく、成功体験にもなかなかたどり着けないまま、不安とともに出勤することになるのでしょう。
②人間関係
そして注意した人叱った人に対し、どのように接したらよいのかわからなくなる。自分に一旦否定的な評価をした人にどのように接したらよいのか、どのように関係を再度構築していったらよいのかわからなくなるようです。
ましてや、きつく言われた、パワハラチックに言われた、もといパワハラだったということになると、回復はもっと難しくなります。
また適当な相談相手がいないことが多いです。先に触れたように就職後地元を離れ単身生活になった、新人が配属されても1人か2人、自分の状況を話す人もいないかもしれません。
本当にパワハラだったとしても「それはパワハラだよ」と言ってくれる人もいません。
自分が悪い、自分がダメなんだという結論に結びつきやすくなります。本人の能力の問題なのか過剰な業務量を押しつけてきているのか、相対的に判断することができません。もっとも若者自身も就労経験の少なさから判断のしようがありません。どう考えたらよいのかもわからないでしょう。
職場で、注意したり叱ったりする人以外のスタッフで、教えてくれたりサポートしてくれたりする人がいれば救われるかもしれません。それもやさしく。
また逆に、何かにつけて怒ったり文句を言ったりする若者も、この裏返しなのかもしれません。
(自分がちゃんとできるようにしてくれるのが、教えてくれるのが、当然だろう)言うなれば「不当な不当感」を抱いているのかもしれません。不当だと訴えることが、状況に合っているのかなという微妙な違和感です。
ただ自己防衛は強いのでしょう。仕事の進捗(しんちょく)状況を聞いただけでパワハラだと言ったケースもありますし、Aを指示したのに自分では難しいと判断したのか自分ができるBを提出したケースもあります。失敗すること、自分がダメだと言われることを恐れているのでしょう。
人間関係の築きにくさがつらさになる、ストレスになっているようです。
※本記事は、2022年9月刊行の書籍『仕事で悩む若者は適応障害なのか』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。
