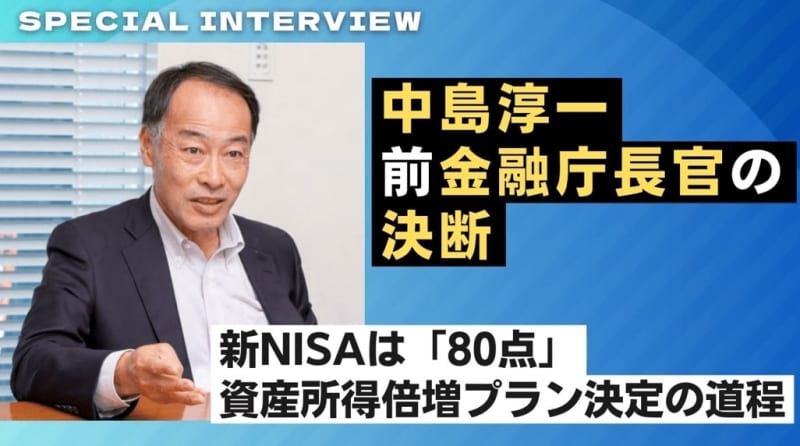
―― 1月から新NISAがスタートしました。中島さんから見て、新しいNISA制度の滑り出しは何点ですか。
合格点が70点だとすると、まずは、80点ぐらいだと思います。メディアの報道も盛り上がっており、いいスタートが切れていると感じます。
長らく金融行政に携わってきた身からすると、日本ではほんの十数年前まで、株に投資しても成功しにくい時代が続いていました。ところが最近の若い世代はアベノミクス以降の株高の恩恵を享受しやすい環境で育ってきたため、株式投資への抵抗感が薄いように見えます。そして新NISAが始まり、投資の熱気が若年層からそれ以外の層へと広がってきていますね。
残りの20点はと言うと、この先、長期的に地道にやっていくことで点数を獲得していくものだと思います。でも80点がずっと続いていく方が良いかもしれませんね。
―― いわばアベノミクスからの株高基調の上に、岸田文雄内閣によるNISA改革がのってきたと。
私が金融庁長官に就いて3カ月後、岸田内閣が発足しました。ついこの前のことなのに忘れられていますが、岸田氏は自民党総裁選で金融所得課税の強化を掲げていました。投資関連の税制でみれば、むしろNISA拡充とは正反対の方向を向いていました。われわれとしては政権発足後に与党税調が増税の具体案を出してくるのではないかと危惧していたのです。しかし、金融所得課税については首相が就任早々に打ち消していただいて安心しました。
NISA拡充の議論が始まったのは22 年の春以降です。6月に公表する「骨太の方針」に向けて官邸とやりとりする中でNISAの改革が論点に上っていたものの、4月時点では全く具体化していませんでした。すると首相が5月のゴールデン・ウイークにロンドンのシティで講演した際に「資産所得倍増プラン」を大々的に打ち出し、NISA を抜本的に拡充すると宣言したのです。金融庁としては寝耳に水の部分もあり ましたが、大きなチャンスでもありました。せっかくの首相のイニシアチブ を生かして、金融庁を挙げて良い制度を作ろうという雰囲気に包まれました。
われわれの根底には「分かりやすい制度にしたい」との強い思いがありました。従来だと「一般」「ジュニア」「つみたて」の3つのNISAが併存し、しかもそれぞれ期限つきで限度額もバラバラでした。こういう複雑さを一挙に解消して格段に使いやすくするまたとない機会だと考えました。
非課税期間の恒久化は当然である一方で、非課税枠の具体的な金額の線引きについては、金融庁から官邸側に案としては示しませんでした。税制の決定は与党税調の権限が大きいので、われわれが先に掲げた数字がひとり歩きして議論があらぬ方向へ向かうのを避けるため、あえて言及を控えたのです。
旧つみたてNISAの非課税限度枠は800万円ですから、官邸が「資産所 得倍増」を掲げた以上、新NISAの生涯投資枠も2倍の1600万円程度になる のが自然だと内心では思っていました。それがなんと1800万円で決着したものですから、われわれも大いに驚きました。
従来の一般NISAを発展させた年間240万円の成長投資枠に関しても、金融庁として強いこだわりをもって臨みました。若い人はつみたて投資枠で中長期の安定運用に励んでいただきたいですし、ある程度の資産を持っている中高年層は成長投資枠を活用することで、まとまった預貯金を株式投資などに移す「キャッチアップ投資」ができるようになっています。
ある自民党税調の幹部は「そもそも一般NISAを非課税にする必要があるのか」と懐疑的でしたが、われわれとしては個別株を買える枠が必要であるとの意図を込めて、一般NISA改め 「成長投資枠」と命名しました。ぜひ成長投資枠で国内株を買っていただき、ひいては日本企業の成長を後押ししていただければと思います。
―― S&P500やオールカントリーといった、海外株インデックス・ファンドが人気です。軽度のキャピタル・フライトが起きているとの指摘もあります。
NISAは「長期・積立・分散投資」とうたっており、世界の成長を取り込みながら資産形成を行います。確かに投資の段階では資金が海外に出ていきますが、老後は積み上げた資産を取り崩して国内で消費するので、いずれお金は日本に戻ってくると考えられます。 そういう大きな経済活動の中で捉える必要があるのです。
―― NISA口座を1人あたり1金融機関1口座に限るのは合理的でしょうか。
確かに、つみたて投資枠の対象となる投信であれば銀行のNISA口座で買えますが、成長投資枠を使って現物株に投資しようと思っても買えません。このような不都合が生じうるとの問題意識は以前から持っています。
ですから本来であれば、1人1口座である必要はなく、非課税枠の範囲内であれば NISA口座をいくつ持ってもいいと思います。 問題は、NISA口座が複数の金融機関で利用できるようにするために、さらに限度額管理のシステム費用が必要となることでしょう。今回は時間的な制約もあり「1人1口座」でのスタートとなりました。私はもう行政の立場から離れましたが、NISAをさらに使い勝手の良い制度へと磨き上げていく不断の努力に期待します。
後編に続く
finasee Pro 編集部
金融事情・現場に精通するスタッフ陣が、目に見えない「金融」を見える化し、わかりやすく伝える記事を発信します。

