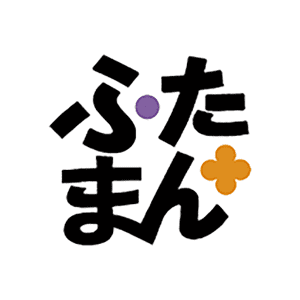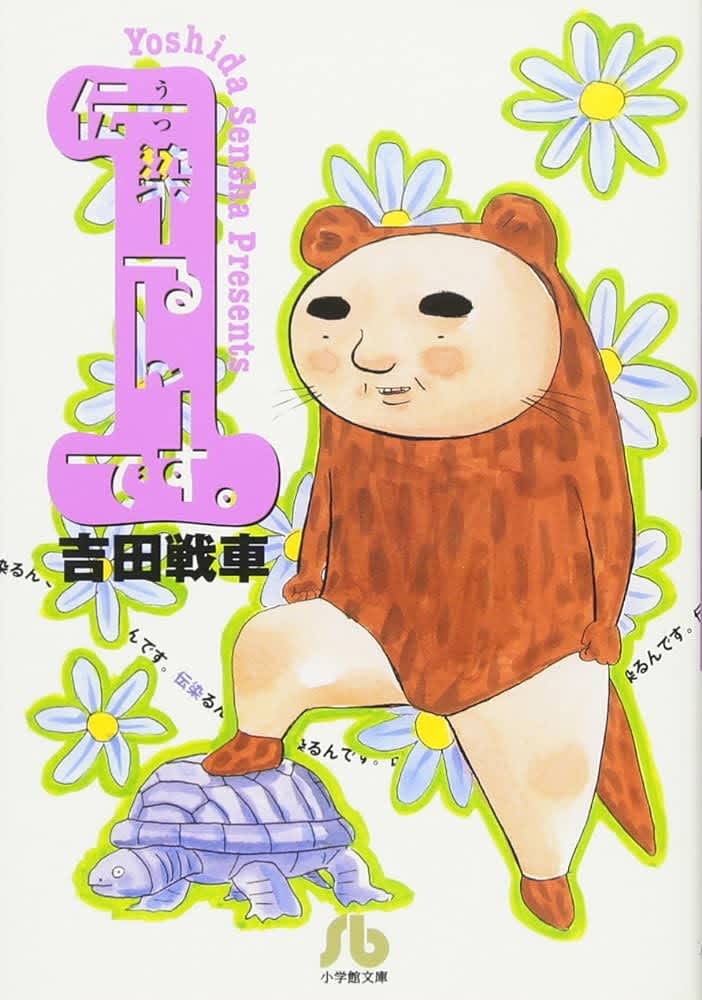
日常生活の中で何気なく使う言葉の中には、漫画やアニメから生まれたものだというケースは少なくない。もともとはキャラクターが使っていたセリフが、実社会で形を変えて新しい言葉として便利に使われるようになった。多くの人が夢中になって触れる人気作品だからこその、影響力の大きさのあらわれだろう。
■世代を超えて使われる「黒歴史」や「予想の斜め上を行く展開」の元ネタは意外にも…
たとえば、過去の消したい記憶や出来事を「黒歴史」と言ったりするが、このことばが、1999年の富野由悠季監督によるアニメ『∀ガンダム』発祥だということをご存知だろうか。
同作は全ての『ガンダム』シリーズの後の物語とされており、過去の作品で繰り広げた凄惨な戦いの歴史を作中で「黒歴史」と呼び、闇に葬ったのだ。ここから発展し、主にネットスラングとして広まった「黒歴史」という言葉。人に知られては困る消したい過去をあらわす言葉として使われるようになり、2021年に8年ぶりの改訂となった三省堂国語辞典第八版にもこの言葉が採用。「テレビアニメ『∀ガンダム』から出たことば」と説明されている。
同じく三省堂国語辞典で漫画・アニメによって広まった言葉として紹介されているのが、「斜め上」という言葉についての「予想の斜め上を行く展開」という用法だ。
想像していたのとははるかに違うことが起きて戸惑ったときに、ついこういった言い回しをすることがあるが、この「予想の斜め上」という言葉は、現在『週刊少年ジャンプ』で『HUNTER×HUNTER』を連載中の冨樫義博氏の過去作品『レベルE』に登場する。
同作は『幽☆遊☆白書』の終了後に「月イチ掲載」という異例の形でスタートした作品で、山形県を舞台に宇宙人が登場するオカルト的なアイデアが盛り込まれた内容。毎度毎度、予想のつかないハプニングを起こすバカ王子こと主人公のドグラ星第1王子に振り回される護衛隊長が、部下に放ったのが次のセリフ。
「あいつの場合に限って 常に最悪のケースを想定しろ 奴は必ずその少し斜め上を行く!!」が、予想外の出来事が起きたときに何気なく使ってしまう「予想の斜め上を行く」の元ネタだ。
実はこの「斜め上を行く」は、魔夜峰央氏の漫画『パタリロ!』が発祥説、松本人志氏の『遺書』が発祥説などもあり、議論を起こすネタではある。しかし、2021年に放送されたTBS系の報道番組『新・情報7daysニュースキャスター』(現:『情報7daysニュースキャスター』)にて、三省堂国語辞典第八版に載る新用法の出どころとして、国語辞典編纂者の飯間浩明氏が『レベルE』を紹介。実際の国語辞典でも「予想の斜め上を行く展開」という用法が使われるようになった経緯として、「漫画『レベルE』から出たことばで、二十一世紀になって広まった」と書かれているこの新用法はネットでも大きな話題を集め、Twitter(現:X)でトレンド入りを果たした。
「黒歴史」と「予想の斜め上を行く」。両方とも初めて聞いたとしても、何となくその意味が分かってしまう説得力がある。新しい日本語として定着するのも納得の、面白い日本語なのは間違いないだろう。
■アニメや特撮でおなじみ「中の人」
また、アニメの声優や、特撮番組や戦隊ショーでヒーロー役を務めるスーツアクターなどを「中の人」と呼ぶことも定着したが、これはもともとは吉田戦車氏の4コマ漫画に登場した言葉だ。
1989年から1994年にかけて『週刊ビッグコミックスピリッツ』で連載された吉田氏の漫画『伝染るんです。』では、主人公・かわうそ君が自分の背を高く見せるために黒覆面をした人物に肩車してもらい、その上にシャツを着るという描写がたびたびある。対面している人からは怪しさ満点のため「下の方は大丈夫ですか?」といった指摘が即座に入るが、そのたびにかわうそ君が「下の人などいない!」と怒るというシュールなオチだ。
この「下の人などいない」が、現在でも使われている「中の人」のルーツだが、吉田氏の漫画では「中の人」というストレートなセリフもあり、たとえば雑誌『週刊ファミ通』に連載された漫画『ゴッドボンボン』で描かれている。
アニメキャラの声優や、着ぐるみキャラクターに対してなど、すっかり定着したこの「中の人」という言葉。なお、吉田氏の妻である伊藤理佐氏によるエッセイ漫画『おかあさんの扉』では、両氏の中学生の娘がポロッと「このキャラの『中の人』がサー」とつぶやいたのを聞いた伊藤氏が「その『中の人』ってさ 昔お父さんが作ったコトバだって知ってる?」と自慢し、感慨に耽るというエピソードがある。当時4コマギャグ漫画から生まれたシュールなネタが、時代を越えて実用的に変化したものと言えそうだ。
以上、3つの言葉を振り返ったが、いずれも文字のイメージだけでも何となく意味が分かるものばかり。未来にまで残る言葉を思いつく、作者のワードセンスには脱帽せざるをえない。