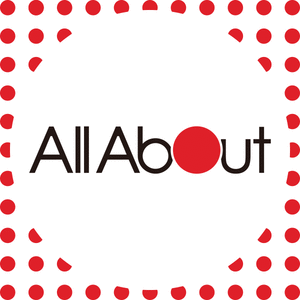Q. GABAにはどれくらいストレス軽減効果がありますか?
Q. 「GABA入りのお菓子を、仕事中によく食べています。『ストレスに効く』といったことが書かれているのですが、実際にはどれくらいのストレス軽減効果があるのでしょうか? 食べ過ぎがよくないことはわかっていますが、GABAの量としてはたくさん摂るほど、効果も高いですか?」
A. 食品からGABAを摂っても、残念ながら脳には届きません
「GABA」(ギャバ)は、食品に含まれる栄養素のようなものだと思っていませんか? GABAは自然界にもある成分ですが、脳で働く「神経伝達物質」の1つで、「γ-アミノ酪酸」というものの略称です。 「神経伝達物質」と総称される分子は、脳内の神経細胞どうしのつなぎめとなる「シナプス」と呼ばれる部分で、ちょうど会話するときの「声」のような役割を果たしています。 しくみを、なるべくわかりやすく解説してみましょう。神経伝達物質は、「興奮性のもの」と「抑制性のもの」の2つに大きく分けられます。 興奮性の神経伝達物質は車のアクセルのようなもので、伝わった先の神経細胞は興奮して活発になります。具体的には、「グルタミン酸」や「アセチルコリン」という物質が該当します。 一方、抑制性の神経伝達物質は車のブレーキのようなもので、伝わった先の神経細胞の活動が抑えられます。その1つが「GABA」なのです。 GABAは、脳の神経活動を抑える役割を果たすことで、睡眠や不安の軽減などに関わっています。 GABAは、私たちの脳内だけではなく、自然界に豊富にある物質で、チョコレートなどにも含まれています。 チョコレートを食べてGABAを摂取すれば、それが脳に達して抑制性神経伝達の代わりに作用し、さらに「リラックス効果」が得られるのではないか?と考える人もいるでしょう。 同様の考え方に基づいて、GABAを増量添加したチョコレート製品や、GABAそのものを錠剤のように加工したサプリが「ストレス低減」を打ち出して人気です。 しかし、科学的な効果としては実際には期待できるものではありません。 食事由来の成分が脳に作用するためには、血液脳関門(Blood-Brain Barrier、略してBBBと呼ぶ)というしくみが障壁になります。BBBの実体は、脳内の毛細血管です。 毛細血管は「内皮細胞」と呼ばれる細胞が集まってできているので、すこしだけ細胞どうしに隙間があり、小さな分子であればそこを通り抜けることもできます。 しかし、脳内の毛細血管の内皮細胞の周りは「グリア細胞」と総称される一群の細胞で取り囲まれており、血液中にある物質がそう簡単には脳実質中には移行しないようになっています。 異物が侵入しないように脳を守るしくみとしても機能していると考えられます。 そしてGABAは、実はこのBBBを通ることができないのです。なので、いくら大量にGABAを食べても、脳に到達することはできません。ちなみに、脳内で働いているGABAは、脳の中で作られています。 原料になるアミノ酸の一種であるグルタミンがBBBを通って脳内に入ると、神経細胞内でグルタミンがグルタミン酸に、グルタミン酸がGABAに、と作り替えられて、神経伝達物質として利用されているのです。 GABAが脳に入らないという事実を踏まえ、GABAの効果を打ち出している製品の中には、GABAが「腸内環境の改善や自律神経のバランス調整などを介し」て、「間接的にリラックス効果や睡眠の質の向上をもたらす」といった説明がされているものもあります。 しかし、それならばGABA以外のもの、たとえば腸内環境を整えてくれるヨーグルトなどを食べても、同様の効果が得られる可能性があるということです。 リラックスや睡眠の質向上のためにGABAを添加する必要は、実際にはないということになります。 なお、「科学的にはそうかもしれないが、GABA入りの製品を食べるとやはり効果がある」と実感していて、愛用されている方もいるでしょう。 その場合は、成分の効果というより、心理的な効果が高く、「お守り」のように役に立っている可能性があります。 GABA入りの製品が自分に合っていると感じるのなら、もちろん避ける必要はありません。ストレス対策という意味でも、好きなものをおいしく食べるのが一番です。
阿部 和穂プロフィール
薬学博士・大学薬学部教授。東京大学薬学部卒業後、同大学院薬学系研究科修士課程修了。東京大学薬学部助手、米国ソーク研究所博士研究員等を経て、現在は武蔵野大学薬学部教授として教鞭をとる。専門である脳科学・医薬分野に関し、新聞・雑誌への寄稿、生涯学習講座や市民大学での講演などを通じ、幅広く情報発信を行っている。 (文:阿部 和穂(脳科学者・医薬研究者))