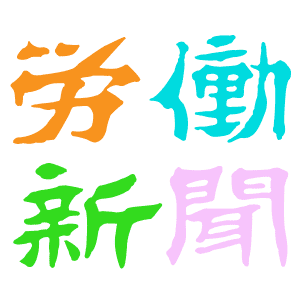7月、8月は死亡災害が増える傾向にある。令和5年の労働災害発生状況を見ても8月がトップで81人だった。7月は70人で3月、9月に続いて4番目ではあるものの、他の月と比べれば高水準であることに間違いはない。
夏は熱中症や感電など夏季特有の災害が懸念されるほか、暑さが原因で意識が散漫となったり、注意を怠りやすくヒューマンエラーが起こりやすい。全国安全週間が7月の初めに設定されているのは、こうした理由からだ。
6月の準備期間から本週間にかけて、安全パトロールによる職場の総点検が行われ、結果に基づく4S活動や職場改善が取り組まれる。安全大会では経営トップからの所信表明を通じた災害防止への意思統一が図られることになる。こうして現場を盛り上げていくわけだが、特別なイベントや行事を終えた後、ややもすると一息つきがちなところはないだろうか。
大過なく安全大会を終えたことで、逆にホッとして安心感を得てしまうようでは、せっかく高めた好ムードを薄めてしまう懸念がある。
労働災害防止に向け、意識を高めて安全の取組みを実施しなければならないのは、むしろ安全大会が終了した後といえる。せっかく熱気を高めたわけなのだから、持続させてこそ、安全大会を開催した意味があるというものだ。
モチベーションの維持に欠かせない要素のひとつに「トップの決意」がある。歴代の全国安全週間のスローガンをみても「トップ」という言葉は実に5回も使われており、安全衛生にとっていかに重要なのかがよく分かる。
「木は梢から枯れる(注:梢は木の幹の先端、木のてっぺんをいう)」といったのは数々の名言を残した経営学者のドラッカーだが、組織の文化が腐敗しているのはトップが腐っていることを指す。逆にいえば、組織の文化はトップマネジメントから形成されていく。士気はトップが高めて、ほどよい緊張感を職場全体に行き渡らせるものなのだ。
本格的な暑さを迎え、作業に危険が増えるのはこれから。高めた安全意識の熱気をすぐに冷ますことのないようにしたい。