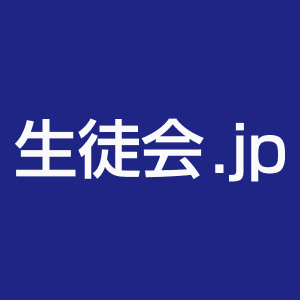2024年5月18日、学生団体「ミライエコール」主催のトークイベント「生徒会を君と語りたい!」が東京大学・五月祭にて行われた。
イベントに弊協会より専務理事の川名悟史と常任理事の猪股大輝が登壇した。
ミライエコールは2023年1月、東京大学文学部3年の山口世夏さんが設立した学生団体。活動のバックグラウンドには「ブラックボックス化」された学校組織・生徒会活動への問題意識があった。
___

山口さんは高校1年生の際に、校則の服装規定に疑問を抱いた。校則改定を行うため生徒会長への立候補を行おうとするが、生徒指導教員に止められたという。
その後、学校長への相談を経て、「意見箱の設置」と「服装規定の改定」を公約に立候補・選出された。
会長になってからまずは活動の透明化が必要と感じ、議事録の公開を行うも、断りなく剥がされてしまったという。
また、服装規定の改正に向けた動きをしようとした際には、他の生徒会役員からも止められることがあったと語る。
山口さんの任期満了後に服装規定の改正は実施されたが、そのプロセスは教員主導で一切開示されなかったという。
___
イベントに登壇した白梅学園大学学長で弊協会の顧問である小玉重夫氏は、生徒会の現状に関して、「生徒の市民性・主体性を醸成する機関であるべきだが、現状はそうなっていない」と指摘。また、生徒会の組織自体が学校内のヒエラルキーに組み込まれており、「官僚的」な組織になっていると分析し、さらに教員側が理不尽な対応をせざるを得ない縦割り組織の問題点も指摘した。
常任理事の猪股は、生徒会活動史の観点よりコメントした。そこでは、生徒会活動は元来、戦後GHQが発足を主導した「生徒自治会」が根底にあることを説明し、当時の「ごっこ遊び」から現在も抜け出していないという現状を指摘した。国立教育政策研究所が2016年にまとめた特別活動の指導資料では、校則改正は生徒会活動の範疇を超えるとしていたが、2023年版では特色的・自主的な活動として扱われていると語った。
専務理事の川名は、最近トレンド化している校則改正・ルールメイキングは、生徒が自身の学校のルールを主体的に見直し、改正することで「ルールは変わる」という成功体験を育む活動として一定程度の効果や意義があるとしつつも、そのムーブメントが単なる流行であったり、その発端が教員で、教員が主導して校則改正を行っている事例が増加傾向であることを指摘した。ルールメイキング活動に限らず、「目的と手段」を適切に認識・設定することが大事だと語った。
___
弊協会では、生徒会活動は長くても6年間しか活動することができず、中高時代に一生懸命活動に取り組んでもそれが持続しないことも現在の生徒会における課題の一つだと捉えています。その中で、大学生のサークルがこういった形で生徒会活動に焦点を当てて企画を主催されたことについて非常に重要かつ、こういった取り組みが全国各地で開催されることを切に願いつつ、今後も協力して参る所存です。
弊協会では登壇依頼等生徒会活動に関わる様々な依頼を広く受け付けておりますので、何かお困りのことなどございましたらお問い合わせフォームよりご連絡ください。