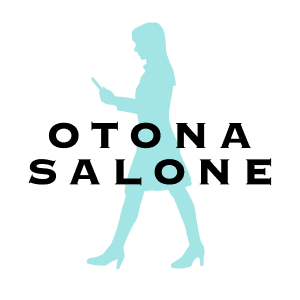「最近、なんだか耳の聞こえが悪くなってきた」と感じている人はいませんか?
難聴にはさまざまな原因があり、種類も分かれるため一概には言えませんが、更年期世代にも“聞こえ”に不調が出ることもあるようです。また将来的に、加齢性難聴という加齢が原因の難聴が起きることもあります。
今回は、認知症などの予防医療に詳しい産業医・内科医の森勇磨先生に、更年期に起き得る難聴についてご紹介します。“聞こえ”に不安がある方は確認してみてください。
◀「更年期と難聴」の記事◀
難聴かどうかのセルフチェック方法
40~50代のうちは、難聴のレベルがそれほど高くないため、「これって難聴なの?」と自分ではわからず、判断しにくいところがあるかもしれません。
そこで森先生に、難聴かどうかを探るためのセルフチェック方法を教えていただきました。
「一番は、聴力検査を受けていただくことがおすすめです。人間ドックでも、耳鼻科でも受けられます。セルフチェックの方法としては、
・自分の声が知らないうちに大きくなっている
・テレビの音が大きくなった
・聞き返すことが多くなってきた
などで判断できるかと思います」
その他、オンライン上で簡易的に無料でチェックできるオンライン聴力調査を提供しているページも多数あるので、ぜひ試してみましょう。
「難聴かも?」と思ったら?
自然と声が大きくなったり、聞き返すことが多くなったりと、「もしかして難聴かも?」と思うようなできごとが増えてきたら、どうすれば良いでしょうか。
「難聴のリスクは『85デシベル以上』の音といわれ、この音を長時間聞くことでダメージが大きくなるので、避けること。普通に生活していれば、あまりそのようなシチュエーションになることはないと思いますが、車の中などは騒音環境に長時間いないことが大事です。また、睡眠時間をしっかりとると多少のリスクは避けられるかもしれないですね」
ちなみに、「デシベル」とは音圧レベルのことで、日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会の公式ページ(※2)によれば、85デシベルは「街頭騒音」に該当するのだとか。目安として、掃除機が75デシベル、芝刈り機が90デシベル、オートバイが95デシベル、地下鉄車内の騒音とドライヤーが100デシベルだといいます。
※2 出典:一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会ホームページ
補聴器を使ったほうが良いの?
難聴といえば、補聴器をつけることで聞き取りやすくなることが知られていますが、もし聞こえにくくなったら、補聴器をつけたほうが良いのでしょうか? ちなみに補聴器とは、マイクから入ってきた音を人ぞれぞれの聞きやすい音に加工してイヤホンから出力して聞こえを補助する機器です。
「生活に支障があれば、使ったほうが良いでしょう。保険適用ではないので、相手に何度も聞き返すなどコミュニケーションに支障が出るのが嫌であれば使用すれば良いですし、自分がそんなに困っていないなら、あえて使用しなくても良いと思います。早期から補聴器を使ったからといって治りがよくなるということはありませんので。ケースバイケースだと思います。
更年期はさまざまなことがメンタルに影響しやすい時期でもあります。聞こえづらいことでメンタルが落ちていくのであれば、受け入れて、対策をとるのも選択肢のひとつかもしれません。補聴器は薬と違い、副作用があるものではないので、気になるなら使ってみてもいいと思います。50代からは徐々に聞こえが低下していくことを自覚していくので、補聴器を含めて加齢性難聴について正しい知識を身につけておくことが重要です」
●補聴器は脳の認知機能の低下を抑制させる可能性も
先日開催された新作補聴器の発表会では、森先生が登壇してトークセッションが行われました。そこで難聴と認知症との関係についてのお話も出てきました。
補聴器を早期装用することにより、脳の認知機能の低下を抑制させる可能性がある、という気になる話題が上がりました。
50~60代から補聴器を使うことで聞こえがよくなる上に、日々の仕事のパフォーマンスも上がるかもしれないとのことでした。
最新の補聴器はどこまで進化?
ところで、補聴器は最近、どんどん進化を遂げており、従来の騒音下では聞こえづらかった課題も最新技術によって解決しつつあります。また補聴器をつけていることに相手に気づかせないほど、スタイリッシュな補聴器も出てきています。最新事情をお届けします。
●最新AI搭載補聴器は人の動きに合わせて聞こえをコントロール

「フィリップス ヒアリンク 50(全4器種9050、7050、5050、3050)」オープン価格
フィリップス ヒアリングソリューションズが先日発売した新モデル「フィリップス ヒアリンク50」は、モーションセンシング技術と呼ばれる技術とAI(人工知能)を組み合わせた補聴器で、補聴器を使う人の動作や動きを検知・分析して、その情報を補聴器の聞こえに反映させる「サウンドガイド機能」が特徴です。
サウンドガイド機能をもう少し詳しくご紹介。例えば、補聴器を使う人は、会話をするときに耳を傾けるように「聞こう」としますが、そうした動きを感知して、さまざまなシーンに応じて聞こえをコントロールするのだそう。例えば、1対1の会話、複数人での会話、屋内での会話、屋外での会話などシチュエーションや環境に合わせてノイズを抑制し、よく聞こえるようにしてくれます。聞き返すこともなくなるため、コミュニケーションの問題も起こりにくくなりそうです。
小型で目立たず、カラーは7色あって好きなものを選べるのも良いですね。
●お試しレンタルを利用する方法も

「メディカルリスニングプラグ」(ナチュラルピンク)」99,800円(税込)(公式オンラインストア価格)
購入するのがちょっと不安という人は、補聴器のお試しレンタルを利用する方法もあります。
例えば、シャープの補聴器「メディカルリスニングプラグ」はフォーマルかつおしゃれなデザインとフィット感で人気の製品ですが、複数サービス経由でお試しレンタルが提供されています。
レンタルサービス「Rentio(レンティオ)」では月額3,280円(送料等込み)でレンタルして試すことができるので、試してみるのも良いかもしれませんね。
【取材協力】

森 勇磨 先生
東海高校・神戸大学医学部医学科卒業。研修後、藤田医科大学病院の救急総合内科にて救命救急・病棟で勤務。救急現場で数えきれないほど「病状が悪化し、後悔の念に苦しむ患者や家族」と接する中で、「病院の外」での正しい医療情報発信に対する社会課題を痛感。その後今や子どもから高齢者まで幅広く親しまれるようになったYouTubeでの情報発信を決意。 2020 年2月より「すべての人に正しい予防医学を」という理念のもと、「予防医学 ch/ 医師監修」をスタート。株式会社リコーの専属産業医として、「会社の健康プログラムの構成」「労災防止を目的とした作業環境の改善」など、 社員という『個人』へのアプローチ、そして会社システムという『集団』へのアプローチから予防医学の実践を経験後、独立。「MEDU株式会社 (旧:Preventive Room株式会社)」を立ち上げるほか、オンライン診療に完全対応した新時代のクリニック「ウチカラクリニック」を開設。
【Not Sponsored記事】