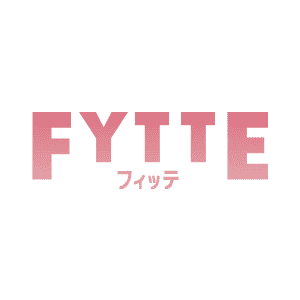By 姫野 友美

近年急増している5月病ならぬ“6月病”。自律神経の乱れから心身の不調が慢性化することも少なくありません。不調を感じたら食事や睡眠など生活を見直すよいタイミングです。「食事のなかでもこだわりたいのは“油”」と話すのは心療内科医の姫野友美先生。今回は6月病対策として自律神経を整える食事のポイントについて解説していただきました!
じつは油の質が大事

良質な油をとることが美容・健康に欠かせないということは一般的になりつつあります。そもそも、私たちの体を作っているひとつひとつの細胞の表面にある膜(細胞膜)の主成分は脂質。ホルモンやさまざまな物質はこの細胞膜を通して細胞の内外を行き来しているので、油の質こそが重要です。
「脳の50%~60%は油(脂質)でできており、認知機能を保つためにも脂質は重要な栄養素といわれています。良質な油をとることで、自律神経を整えるための脳内ホルモンを作り出したり、そのホルモンをスムーズに伝達したりする手助けをしてくれます」(姫野先生)
自律神経を整えるために“隠れたカギ”となる良質な油。現在、数多くの食用油がありますが、そのなかでも意識してとるべき油は、次の2種です。
脳を動かすエネルギーを生み出すMCTオイル

自律神経を整えるためにとりたい油のひとつ目はMCTオイル。脳を動かすエネルギーになります。
「自律神経を整える脳内ホルモンは就寝中にも作られるので、睡眠中も脳にエネルギーを供給することが必要です。そして睡眠の質を高めるために夜間の血糖値の安定をさせること。この2つを叶えるのに適しているのがMCTオイルです」
MCTオイルの主成分は中鎖脂肪酸(Medium Chain Triglyceride )。母乳や牛乳などの乳製品、さらにはココナッツなどのヤシ科植物の種実にも含まれるものです。
「一般的な食用油(長鎖脂肪酸油:Long Chain Triglyceride:LCT)と比べてMCTオイルは、すばやく消化・吸収され、ケトン体を生成しやすいという特徴があります。ケトン体は糖分(ブドウ糖)と同様に脳のエネルギー源になり、エネルギーが十分であると、血糖値が安定します」
効率のよいエネルギー補給や体脂肪対策の観点では日中に摂取したほうがよいですが、6月病対策としては夜にとるのがオススメとのこと。
「寝る前に豆乳にMCTオイルを少量入れて飲んでみてください。豆乳は脳内ホルモン合成に必要なたんぱく質やミネラルを多く含み、自律神経を整える脳内ホルモンが作られます。そこにMCTオイルを加えることによって夜間低血糖も防げるので朝の寝起きがよくなります」
脳内ホルモンの働きをスムーズにするオメガ3系オイル

もうひとつは脳内ホルモンの働きをスムーズにするオメガ3系オイルです。
「毎日摂取することが推奨されている必須脂肪酸のオメガ3は、脳機能の発達や維持にとても重要な役割を果たしています。オメガ3は脳の細胞膜をやわらかくし、自律神経を整える脳内ホルモンのはたらきをスムーズにしてくれます」
オメガ3は一般的に青魚に多く含まれていますが、毎日の食事で手軽にとり入れるなら、オメガ3系の油である、アマニ油やえごま油がオススメ。
「オメガ3脂肪酸は、ミネラル・ビタミン・たんぱく質と一緒に摂取するのがよいですね。脳内ホルモンのバトンタッチがスムーズになります」

監修:姫野友美(ひめのともみクリニック院長)
考案:大柳珠美(ひめのともみクリニック 管理栄養士)
そこで、姫野先生のオススメ簡単レシピは『ばくだん納豆』。
【材料】(1食分)
納豆…1パック(50g)
まぐろ(刺身用)…50g
オクラ(ゆでたもの)…2本
キムチ…50g
卵黄…1個分
アマニ油 または えごま油…小さじ1
しょうゆ…適量
納豆、まぐろの角切り、ゆでたオクラの輪切り、ザク切りした発酵キムチを小鉢に盛りつけ、中央に卵黄をトッピング。最後にアマニ油またはえごま油、しょうゆを回しかけます。お好みでちぎった焼きのりをプラスしても◎。これからの暑い季節にもぴったりな一品です。
自律神経を整えるためには、こうした脳への「栄養」も大切。加えて、十分な睡眠をとって脳と体を休め、適度な運動を心がけるとより効果的です。不調を感じやすい季節には2つの脂質をじょうずにとり入れ、心と体にエネルギーをチャージしましょう。
文/庄司真紀