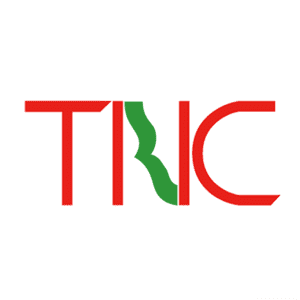強風によりJR博多駅前のケヤキが倒れた。高さ13メートルの巨木で、幸いけが人は出なかったが、大きな事故につながる恐れもある倒木だった。そういった事故を未然に防ぐため、木の健康を管理する、木のお医者さん「樹木医」の取り組みを取材した。
街路樹一本一本を“健康診断”
博多駅前の倒木について、「もし事前に検査をしていたら『危ないから植え替えが必要』と私は診断していたでしょう」と話すのは、樹木医として約30年の経験を持つ森陽一さんだ。
森さんは、今回の倒木の原因を根腐れの可能性が高いと指摘する。
樹木の健康状態を診断する樹木医。街や公園など身近にある樹木を守ることが主な仕事だ。この日、森さんが樹木の“健康診断”を行っていたのは福岡・春日市の街路樹。1本ずつ街路樹を診て回る。
「この木は根が巻いていますね。これは“巻き根”といって自分の幹を締め付けていくので、余りいい状態ではない」と1本の樹木を診断。また別の1本に対しては、ステンレス棒を根に刺して根の状態を確認し、「木の根っこ付近が腐れることが多い。倒れるのは根株腐朽(ねかぶふきゅう)といって、根から倒れることが多い」と診断した。
根が腐っている場合は、棒が地面の奥まで刺さるため、発見次第、伐採していく。2時間ほどかけて街路樹の検査は完了。樹木は成長するので、繰り返し点検することが重要だと話す森さん。この街路樹には、経過観察が必要なものの危険な状態の樹はなかったという。
特別な機械で木の密度をチェック
続いての森さんの仕事は、街路樹ではなく寺院。福岡市の金龍寺東堂だ。三好龍光老師は「クスノキはこの門の奥にありました」と当時を振り返る。
境内にある大きなクスノキ。以前は、本堂の前に植えられていたが、14年前に本堂を建て替える際、工事の妨げになってしまっていた。
300年の命を、改築するために伐採するのは、余りにもむごたらしいと心を痛めた三好龍光老師は、大事なクスノキを山門の前に移植することを決断。その移植作業に携わったのが森さんだった。
この日は、移植したクスノキの定期検査。森さんが「これで音波を発生して、木の中の状態を測る機械」と取り出したのは、樹木の密度を調べる道具だった。九州には1台しかないという特別な機械だ。
空洞の割合が大きいと倒木の可能性が高まるという。また、この機械を使うと木の密度が色で分かる。「白」が最も密度が低く「青」「赤」「緑」の順で密度が高くなっていく。
検査したクスノキは、密度が低いとされる「青」が大部分を占めていた。森さんは「ちょっと空洞がありました。だけど大丈夫です!周りはしっかりしているから、それほど大きな心配はない」と、異常なしと判断。クスノキは移植してからも元気に育っていた。
「治療すれば木も応えてくれます」
一方で、同じ場所に樹木を残したいという人もいる。福岡市内の住宅の敷地内にあるクロガネモチの木にも、ある問題があった。幹からのぞく黒い部分。その黒い部分を指差しながら「結構、腐ったりしていたんですよ」と森さんが打ち明けた。
このクロガネモチは、内側から虫に浸食され腐りかけていたため10年ほど前から定期的に診断を受けていたのだ。
さらに家の外側に回った森さん。以前はさらに背が高かったというクロガネモチの木。しかし、周辺に住んでいる人から「怖い」という声が寄せられ、少し小さくコンパクトになったという。
高さ15メートル以上のクロガネモチの木は、幹も太く大きくなり過ぎたため、塀の一部を取り壊して保存されていたのだ。
「もう私が生まれるかなり前から、この家に伝わるというか、守ってくれている木なので、ご神木的な存在ですね、我が家のお守り」と残したい理由を話す依頼主の女性。
クロガネモチの木はこの家で代々、受け継がれ、樹齢300年を超えているという。「小さいときに木の根っこに座ったりして、この木があることが普通のことだった」と物心ついた時からこの木と一緒に育ってきたと女性は懐かしそうだ。
“切り倒すことはできない”という思いをつなぐために、森さんは、黒くなっている部分の防腐処理に虫の防除、さらに根元部分は、樹脂を固めたのもので補強し倒木を防ぐといった治療を施した。
「何とか1年でも1秒でも長く、ここに鎮座してもらいたいですね」と、依頼主の女性は樹齢300年を超えるクロガネモチの木をいとおしそうに見上げていた。
樹木医の森陽一さんは最後に「ちゃんと治療してあげれば木も応えてくれて元気になります。もう200年、300年もたつ“お年寄り”ですから、大切にしたい」と話した。
(テレビ西日本)