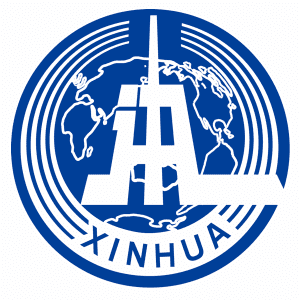ベルギー・ブリュッセルのNATO本部で行われたスウェーデン国旗の掲揚式。(3月11日撮影、ブルジュレット=新華社記者/趙丁喆)
【新華社パリ6月26日】北大西洋条約機構(NATO)のストルテンベルグ事務総長はこのほど、訪問先の米国で、NATOの欧州加盟国とカナダの今年の国防費が前年比で18%増え、過去数十年で最大の伸びになると述べた。加盟32カ国のうち23カ国の国防費が今年、国内総生産(GDP)比2%以上に達する。
NATOが国防費を大幅に増やす主な要因となったのは、同盟国に絶えず「安全保障上の不安」を売り込み、機に乗じて利益を得る米国の「恐怖マーケティング」である。ストルテンベルグ氏はこれを少しも隠さず、同盟国の新たな国防支出は「多くが米国に使われている。NATOは武器販売市場を作り出した」と語った。

14日、ベルギー・ブリュッセルのNATO本部で行われた国防相会合。(ブルジュレット=新華社記者/趙丁喆)
米国は「仮想敵」を作り、「火に油を注ぐ」ことで地域紛争をあおり、NATO加盟国に国防費を拡大するよう仕向け、米軍需企業はおかげで莫大な利益を上げている。NATOはウクライナ危機が激化して間もない2022年6月、米国主導の下で新たな「戦略概念」を採択し、ロシアを「最大かつ直接の脅威」と位置付けた。米国が力を尽くして醸成した「ロシア脅威」論は、欧州の同盟国に安全保障上の不安をもたらし、各国が次々と戦争に備え軍備を拡張し始めている。ここ2年のNATOの軍事調達は3分の2が米国企業からで、総額は1400億ドル(1ドル=約160円)に上る。ストルテンベルグ氏は訪米中、「NATOは米国の安全保障だけでなく、産業や雇用にも寄与している」と述べた。
米国は経済的利益を手に入れる一方、「恐怖マーケティング」によって同盟国の自らに対する「安全保障上の依存」を生み出し、安全保障戦略で同盟国を操り、西側世界での覇権的地位を守っている。長年中立を保ってきたフィンランドとスウェーデンも米国の「恐怖マーケティング」攻勢にあらがえず、NATOに加盟した。フランスのパリで開かれた世界最大級の防衛展示会「ユーロサトリ2024」では、開催国のフランスを除き、米国が最大の出展国となった。フランス紙フィガロは、米国の強い存在感によって今回のユーロサトリが「欧州の対外依存の象徴」になったと論評した。
米国式「恐怖マーケティング」には「友を害し自らを肥やす」ための綿密な計算が隠され、同盟国の直接的な利益とは相反する。米国の同盟国は、米軍需企業の在庫処分を身銭を切って支援してきた。当初は「金で安全を買う」つもりだったのが、結局は金と安全の両方を失う結果に終わるだろう。NATOの東方拡大は典型的な例だと言える。NATOは米国主導の下、ロシアを「仮想敵」として東方への拡大を続け、ウクライナ危機の激化を招き、欧州大陸で戦火を再燃させた。米国は機に乗じて火に油を注ぎ、NATO同盟国に武器を売りつけ、欧州を火薬庫に変え、危険の淵に立たせている。フランスのシンクタンク「戦略研究財団(FRS)」のブリュノ・テルトレ副所長は、フランス国民議会の国防委員会で国際情勢を説明した際、米国が戦闘機F35の購入と引き換えに欧州の安全を永続的に保障してくれるという欧州の一部の国の考えは「間違っている」と指摘した。
これら同盟国では、大量の資源を国防分野に回したことで重要な社会や経済のニーズがないがしろにされ、国民の不満が募り、国内の不安定要因を増大させている。欧州の経済政策を研究するシンクタンクはリポートで、国防支出の増加が経済を圧迫し、社会福祉制度の破壊と重要分野への公共投資の削減につながることで、国民の不満と社会不安を引き起こす恐れがあるとし、欧州諸国の安全と安定にマイナスの影響を及ぼすとの見方を示している。
米国が「小サークル」づくりと「武器販売」という二重の目的を果たすため、この「マーケティングモデル」を世界のより多くの地域で再現しようとしている点は警戒に値する。米国式「恐怖マーケティング」によって露呈したかたくなな冷戦思考は、国家間の紛争激化や世界の安全保障状況の悪化を招き、各国を軍拡競争に陥れ、世界の平和と安定を脅かすだけである。スロベニアの政治経済学専門家ボゴミル・フェルフェイラ氏は、国防費が多いほど安全だと考えるのは誤解だと指摘。「共に享受してこそ真の安全保障だと言える。安全は一方の軍備では実現しない。なぜなら他国も同様の行動を取るからだ」と語った。米国式「恐怖マーケティング」は世界をさらに危険な状況に追い込むだけである。