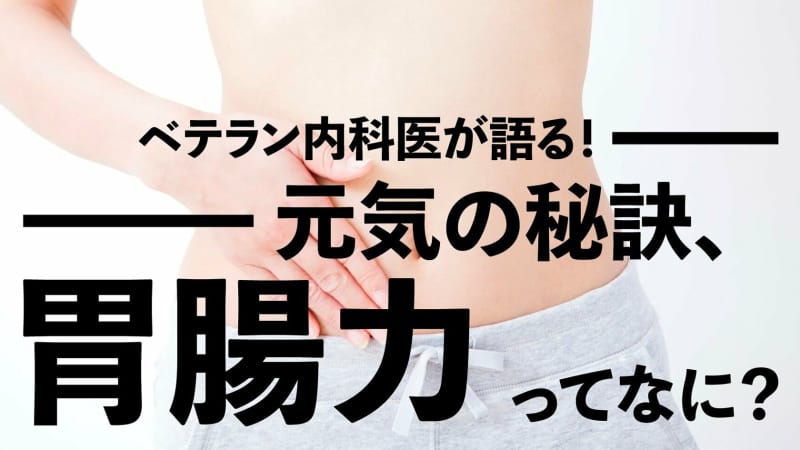
CHAPTER1 胃腸を制すものが健康を制す
胃腸力をつけよう
元気はつらつの源は“胃腸力”
私は年間4500検査もの胃カメラと大腸内視鏡検査を行い、その数だけの胃腸を日々診断しています。診察に来られた方を加えると、その3倍以上、1年に1万3500人以上の方の胃腸を診ています。
そこからわかるのは、「見た目や健康状態と胃腸の調子は一致していることが多い」ということです。
胃腸が元気な人は、実年齢よりも若々しく、アクティブで声にも張りがあります。一方、不調を抱えている人は、どことなく不安げで前かがみの姿勢になりがちです。胃腸が元気な人は年齢を問わず、食欲があることが共通点。食欲があり、食べたものを自分に必要な栄養に変えられるのが「胃腸力」がある人です。
診察のときに、必ず年齢を確認してますが、動作や声の張り、記憶力など90歳以上にもかかわらず、70歳くらいに見える方がいらっしゃいます。ご自身の健康の秘訣を伺うと、「なんでもよく食べますよ。特にお肉が好きなんです。量は食べませんがね」とおっしゃいます。その言葉に納得です。
ただし、食欲といっても偏食は例外です。例えばストレスが強くかかると、甘いものや脂っぽいものばかりを食べたくなる人もいるでしょう。こういう人は、確かに食欲はあるけれど、胃腸の調子はあまり良くないケースも多いのです。
「胃腸力」がある人とは、空腹感と食欲があって、食べて活動的になり、そしてまた空腹になり食欲がわく人といえます。食欲は健康のバロメーターです。そのため診療に来られる方には必ず食欲があるかないかを伺っています。
「胃の痛みはあるけれど、食欲はある」という方も結構いらっしゃいます。そのような方は検査をして問題ないこともよくあります。そういう方には、「検査の結果問題ないので大丈夫ですよ。心配ありませんよ」とお伝えすると、「心配ない、治るんだ」という安心感からかストレスも軽減され、思いのほか早く回復する傾向があります。
「心配ない、大丈夫」という言葉を聞きたい方は大勢いらっしゃるように感じます。
自分の「胃腸力」を知る
健康の要かなめである「胃腸力」を知ることが大切です。胃腸力の低さを自覚していれば日々の食事を見直す、人間ドックや検査などを受ける、病気が見つかれば早めに治療を受けるなど必要な対策がとれるからです。
胃腸力が高ければ、安心してアクティブに過ごせます。そこで次の胃腸症状とその症状の原因となり得る生活習慣のなかから、該当する数によって胃腸力をチェックしてみましょう。
症状チェック
□胃がもたれる
□胃が痛む
□胸やけがする
□おなかが痛い
□よく下痢をする
□便秘になりやすい
□便秘と下痢を繰り返す
□食欲がない
□空腹感はあるのにたくさん食べられない
□おなかがゴロゴロする
□げっぷが出る
0~2個…… 胃腸力あり。
3~5個…… 胃腸力に少々問題あり。胃腸力が低下し始めている。
6~10個…… 胃腸力はかなり低い。生活を見直しましょう。症状が続くときは診察を受けましょう。
症状チェックが多く当てはまった人は、後述する「胃腸の不調の症状」で自分に当てはまる症状を探してみてください。症状が強ければ病気につながることもあります。また、検査を受けるきっかけにもなります。
生活習慣チェック
□寝る2時間前に食事をすることが多い
□朝食を抜くことが多い
□お手洗いを我慢することが多い
□少食
□食事の時間がバラバラ
□長時間お手洗いに行けないことがある
□辛いものが好き
□暴飲暴食をしてしまうことがある
□アルコール類、カフェイン類を毎日摂っている
□ストレスを強く感じる
0~2個…… 胃腸力の管理は大丈夫。これからも良好な胃腸力を維持しましょう。
3~5個…… 胃腸管理にやや不安あり。規則正しい食生活をまず心がけましょう。
6~10個…… 胃腸管理に問題あり。今のままではいずれ胃腸の病気から全身の不調につながります。できることから生活を見直しましょう。
生活習慣チェックに当てはまる項目が多かった人は、のちに記述する「胃腸が悲鳴を上げる5大原因は「ピロリ菌」「暴飲暴食」「自律神経のバランスの乱れ」「加齢」「ストレス」」をご覧ください。胃腸力が弱まっている原因がわかり、生活習慣や、症状を改善するヒントになります。
※本記事は、2022年10月刊行の書籍『名医が教える胃腸の守り方』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。
