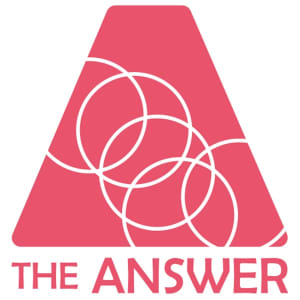本人執筆の連載「田中希実の考えごと」、第6回「オリンピアンとして考えたこと(後編)」
陸上女子中長距離の田中希実(New Balance)は複数種目で日本記録を持つトップランナーである一方、スポーツ界屈指の読書家としても知られる。達観した思考も魅力的な24歳の彼女は今、何を想い、勝負の世界を生きているのか。「THE ANSWER」では、陸上の話はもちろん、日常の出来事や感性を自らの筆で綴る特別コラム「田中希実の考えごと」を配信する。
長年の日記によって培われた文章力を駆使する不定期連載。第6回は「オリンピアンとして考えたこと(後編)」をしたためた。5月に5000mの参加標準記録を突破し、パリ五輪の出場権を獲得。2021年東京五輪に続きオリンピアンになる。この3年で苦しみ、「因縁」が生まれた場所が米オレゴン州ユージーン。1975年に24歳でこの世を去った偉人ランナー「プリ」に思いを馳せ、「生きることとはなんなのか」に思考を巡らせた。26日の前編に続き、本人がその脳内を書き連ねた。
◇ ◇ ◇
私は今年5月に、プリフォンテーン・クラシックにおいてパリ五輪5000mの参加標準記録を切った訳だが、本来は1500mにエントリーしていたのを、ドーハダイヤモンドリーグの5000mで記録を切ることに失敗したため、急きょ種目変更してもらったものだった。
だからこそもう後がないと、今回も2022年の時と同じくらい、かなり神経過敏になっており、すったもんだした訳だが割愛する。そもそもドーハにもここでは語り尽くせない因縁がある訳だが、もちろん割愛する。
前編で、プリフォンテーン(愛称プリ。以降プリ)がナイキ初の契約選手であると説明したが、当時はアマチュアリズムが正義であり、選手はスポーツによって生計を立てたり、報酬を得ることさえも禁じられ、選手が大会に出ることで生じる利益は全てアマチュアスポーツ協会の手に握られていた。しかし、選手がスポーツを続けるにはその社会基盤に乗っかるしかなかった。
それが、プリの登場によって変革されていき、今ではスポーツにおけるプロ活動が当たり前の世の中になった。
プリの走りが人を惹きつけたのは、走ることそのものが彼の自己表現であり、自分の責任のもとに全てを出し切ろうとしており、誰がどう見ても、彼の走りは「余暇」などではなかったからだ。生きることそのものに真正面から向き合うことの素晴らしさを彼は教えてくれていたのだ。
しかし、プロフェッショナルがアマチュアリズムより優れた精神かと言えば、もちろん、そうではない。自分のしたいことに打ち込むという点では、アスリートにとって二つの精神は根底では同じもので、垣根はないはずである。
そして社会的には、プロやアマチュアの仕組みをいかに利益に繋げられるかだけの違いで、根底では同じであるように感じる。なぜなら、アスリートというだけで、社会では一定の価値が自動的に見出されるからだ。
アスリートはきっと、血も滲むような努力をしているに違いない。しかし、だからこそアスリートの血も涙も美しい。アスリートは真面目で品行方正、爽やか、決してたゆまず、みんなに感謝し、笑顔を絶やさない。人間の鑑。憧れ。ヒーロー。そして実際に人間離れした結果を残そうものなら、神のように祀り上げ、崇めたてられる。
そして、どんな果敢な挑戦や、それに伴う成功であれ失敗であれ、世間の求めるヒーローのストーリーとして、食いつぶされてしまう。ヒーローが泣いている時、世間は笑い、ヒーローが久しぶりに笑えた時、世間は嘆く。それくらい互いのストーリーは、乖離している。
そして、アスリートはその基盤の上でスポーツをするしかない。世間から求められている人物であるしかないのだ。なぜなら、大好きなスポーツがしたいから。全くの自分の責任のもとにスポーツが成り立つはずのないことは自明だからである。
ベーブ・ルースは少年院の子だったのに、偉大な野球選手になっただけで更生したと思われる。スポーツは素晴らしい、人をより良く変えると思われる。彼は、本当は芯の部分で変わった訳でなく、野球のためなら、社会の中心で生きていくためなら、我慢しようと自分を押し込めていただけかもしれないのに。
日陰者はスポーツをしてはいけないのだろうか。スポーツをしさえすれば、表舞台の仲間だとみなされるのだろうか。(こんなことを書いている時点で根暗でひねくれもののアスリートがここにいる)

二十歳で自殺した女子大生の日記を読んで思う「彼女は生きることに真正面から…」
最近、1960年代の学生運動の最中、二十歳で自殺した女子大生の、死の数日前までの日記をまとめた本を読んだ。社会への怒り。自己を出すと反乱分子とみなされる悲しみ。意固地になって探すほどに見つからない確固たる自己。満たされない仲間意識や愛。これらは全て、単なる学生運動による悩みではなく、誰もに覚えがある悩みではないだろうか。
多分彼女に死ぬつもりなんてなかった。生きていることと死んでいることの境目が無くなってしまったに過ぎないのだと思う。
自分を探し、自分を保つことが、とにかく何か目的をもち、行動することだとしたら、目的さえ分からなくなった時、どうしても目的がもてないくらいこてんぱんにやられた時、行動さえできなくなり、息が詰まり出す。生きてることと死んでること、自分と他者との境目がなくなり、どうしようもなく心細くなってしまうのだろう。
心細さを取り除く為に誰かに助けを求めることさえも己の弱さと糾弾し、たとえ弱くとも、なりふり構わず守るようなものや、守られている安心感がなかったのだろう。彼女は自己防衛に走り過ぎた。感情を理性で押さえつけ、本当は自分なんてものはどこにもないのかもしれないという恐怖の感情から逃れようとした。それだけ生きたかった。何とかして、自分が、自分から守りたいと思える、守るべき自己を見つけたかった。そのためにあえて独りになったのだ。彼女は生きることに真正面から向き合いすぎた。
私がなりふり構わず弱さをさらけ出せるのは、守るべき自己=陸上があるからにすぎないと思う。また、スポーツと同じく、人が生きようとする中で自分の責任のもとに全てを完結することには無理があると思う。だから生と死の境界線も、自己と他者の境界線も、こんなにも危うい。
死んだらおしまいと人は言うだろう。彼女自身も日記の中で散々、死ぬのは負けだとか、死んだら何も考えられなくなると自分に言い聞かせていたけれど、こういう生き方(死に方)があったっていいだろう!と、本当は叫んでいるんだと思う。そもそも彼女は生きている間ずっと演じていた訳だし、死ななければ本当の彼女と言えるノートが世に出ることはなかった。
それなら死んで初めて、彼女は生きられたとさえ言えるのではないだろうか。彼女は生きる意味を、どうしても生きているうちに見つけられなかった。
人間が生きる意味を問うことは、アスリートの存在意義を問うことと同じではないだろうか。
オリンピアンは公人と規定され、スポーツには商業的な価値が見出されている。メディアは観客動員を促し、観客は人間離れしたヒーローを見物にくる。その日のヒーローの心中はどうでも良く、ただ来てくれればいい、見れさえすればいいのだ。実のところアスリートも他の多くの人となんら変わらない存在でいるべきではないだろうか。
答えのない苦しみに苛まれている人がこの世にいっぱいいるのに対し、苦しみに対して勝敗というはっきりした答えをもって確認でき、必ずその過程を見届けてくれる誰かがいることを思うと、アスリートは恵まれ過ぎてはいないだろうか。あるいは反対に、アスリートは社会から付随される価値によって、あまりにも搾取されてはいないだろうか。
私にもし走ることがなかったら、世間のオリンピック騒ぎを疎ましく思う人物だったろう。体育なんて何一つ出来ない子供時代。スポーツなんてむしろ恨みに思うような人物だったろう。
スポーツに注目なんて集まるべきではない。みんな平等に、世の中の一部、社会の歯車であるべきでは?
そして改めて、考えてみる。まさにその社会を構成している、人間とは? その人間たちが、生きる意味とは? 意味のある生とは? 意味のある死とは? 答えのない問いに迷い、熱に浮かされたように喘いでいる人でこの世は溢れている。
誰かのために生き、誰かのために死ぬ。そうしたいと思う人がいる。自分のために生き、自分のために死ぬ。そうしたいと思う人がいる。なんとなく生き、なんとなく死んでいく人がいる。誰かを傷つけながら生き、誰かを傷つけ続けた上で死ぬ。そういう人々もいる。

アスリートもただの人間、ただ少し他と違っているのは…
アスリートは、決して特別な存在ではない。勇気や希望を与えるだけがアスリートでないのはもちろんだ。実に色んなアスリートがいる。実に色んな人がいるのと同じように。アスリートもただの人間なのだから。
ただ、少し他の人間と違っているのは、アスリートは、人間の最も人間らしい部分に触れてしまっていることだ。アスリートは勝利を常に求めずにいられない。何者にも折り合いがつけられない。死んでもいいから勝ちたいと思うことだってある。そしてそれは、アスリートにとっては、生きたいという願望そのものなのだ。言葉の上では矛盾しているのだが。
その裏腹に、キャリアの中では、なんとなく勝つ時があるしなんとなく負ける時もある。忌むべき勝ちも喜ばしい負けもある。もし、試合の勝敗をアスリートにとっては生き死にに例えられるとしたら、アスリートは多くの人生を、何度も何度も、そのキャリアの中で繰り返していると言える。
いつも、心の中で血を流している。苦しみに満ちた人生を何度も生き、そして何度も死んでいる。その全てが答えであると、アスリート自身は知らず知らずのうちに、常に発見している。ただ、それだけのことであって、意味はない。
我々は、どう生きるか。どう死ぬか。同じ人間という仲間として、考え続けようではないか。
絶対に、人それぞれに、アスリートにとっての競争のような存在があるはずだ。夢中になれるもの。その人自身が、夢中になるに値すると決めたもの。信念。それに伴う苦しみの過程と、その結果。過程にも結果にも特段意味はないはずなのに、驚くべきことに、それらは苦しい時間をやり過ごし、振り返ると必ず存在する。そして、いつか必ず終わりが来る。
スポーツはその縮図ではないだろうか。それを社会に分かりやすく示しているだけではないだろうか。だから、みんなスポーツに魅入ってしまう時だってあるのではないだろうか。スポーツに興味がなく、むしろ恨みに思うような人でも、ふと見かけたときに涙を流すことだって、あるかもしれない。特に理由なく、名前のない感情から溢れる涙を。
アスリート自身が、意味の分からない涙を毎日流しているくらいなのだから。
アスリートは精神的に優れている訳でも、崇高な存在でもなんでもない。
非常に俗っぽい、脆く陳腐な、ただの人間だ。ただその運命に抗い、何者かになろうともがいている。
私がこんな文を書いているのは、運命のただ中にあって、他になす術がないからだ。
先日、パリ五輪の権利をとって初めて、私はパリに向けて走り出せた気がする。しかしそうでなかったとしても、東京の時からずっと、私はオリンピアンだったらしい。でも、オリンピアンとはなんなのか。私は四六時中、オリンピックのために生きているわけではない。私は今日走ることだけを考えていて、明日も走れるかどうかだけを考えていて、4年に一回巡り合えるかどうかという奇跡に、生きている実感を委ねたくなどない。私は、オリンピアンでなくランナーであるはずなのに。
There is so much more to come.
この文を読んで来る震えは、武者震いだろうか。いや、迫り来る運命に対する恐怖に慄いているのだ。
しかし私はこの運命に、最後まで折り合いをつけるつもりは、ない!
○…5000mでパリ五輪代表に内定している田中は、27日開幕の日本選手権(新潟・デンカビッグスワンスタジアム)で同種目と800m、1500mの3種目にエントリーした。1500mは参加標準記録4分02秒50を突破し、優勝すれば代表に即時内定。優勝なら1500mは5連覇、5000mは3連覇で3年連続2冠となる。
田中希実 / Nozomi Tanaka