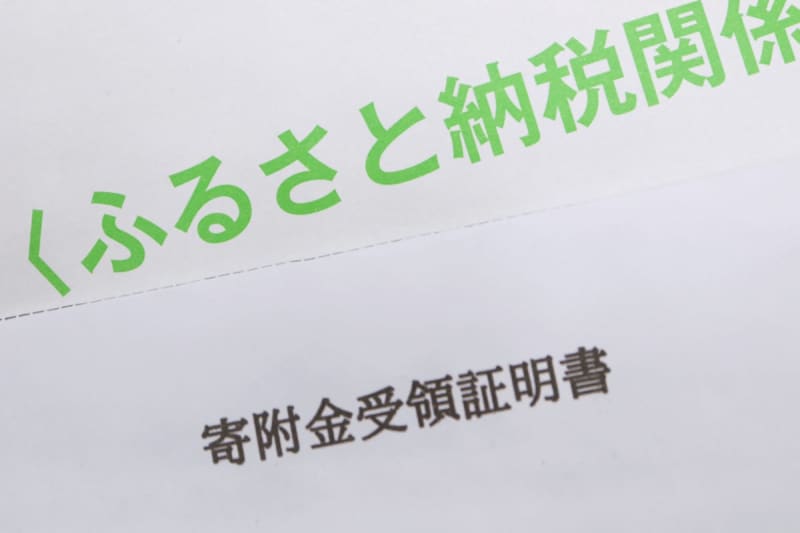
ふるさと納税とは
ふるさと納税は「納税」という言葉が入っていますが、寄附の一種です。これは、希望する自治体に対して寄附を行い、2000円を超える部分に対して、一定限度額まで所得税や住民税から控除することができる制度です。
例えば、ある自治体に3万円のふるさと納税をし、自己負担額2000円を除いた2万8000円が控除された場合で、所得税と住民税の控除割合を考えてみましょう。このときは、2万8000円の部分に所得税率(特別復興税を含む)を乗じた額を所得税から控除でき、住民税は基本分と特例分で控除されます。
住民税の基本分は2万8000円×10%となり、一方の特例分は、ふるさと納税額(この場合は3万円)が住民税所得割額に占める割合で、算出方法が異なります。特例分が住民税所得割額の2割を超えないときは、以下の式で表されます。
特例分=2万8000円×(90%-特別復興税含む所得税率)
一方、2割を超える場合は、住民税所得割額×20%=特例分となります。
仮に所得税等の税率が10.21%、特例分が住民税所得割額の2割以下だった場合は、所得税から2859円が、住民税から2万2400円が控除されます。
なお、ふるさと納税額はいくらでも控除されるわけではなく、所得や家族構成によって上限が決められています。また、ワンストップ特例を使った場合には、住民税からの控除となります。
ふるさと納税は、相続税の節税となるのか
ふるさと納税のような寄附に対しては、所得税から控除することができる「寄附金控除」という制度があります。この制度においては寄附をすることで、寄附額から2000円を差し引いた額に対して、所得税は40%、住民税は20%まで所得から控除することができるので、納付する税額が少なくなるといえます。
この控除は相続税に対しても利用することができるので、「相続税の節税を行える」といえるのではないでしょうか。
また、ふるさと納税には「自治体への寄附に対して返礼品がある」というメリットがありますが、返礼品などが50万円以上のものであれば、「一時所得」の対象として課税対象となることに注意は必要です。
ふるさと納税を使って相続税対策を行うときの注意点
仮に預貯金が数千万円あり「納税の義務がある」と考えられる場合に、上限なくふるさと納税を行うことができるかというと、それはできません。
前述したように、ふるさと納税など寄附金控除には上限があります。上限を超えた額に対しては、寄附控除の対象にはなりません。ふるさと納税を行うと、相続財産の減額にはなりますが、相続人に分与される財産が減少することになってしまいます。
また相続人が複数いる場合には、相続人全員の承諾を得たうえでふるさと納税を相続財産から行い、さらに寄附の証明書を添付した相続税の申告を申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに行う必要があります。
なお、ふるさと納税に使える相続財産は、相続人が遺産分割で受け取った財産を寄附する場合に限られます。被相続人の遺言書に「寄附をする」という内容があった場合は、その寄附に関しては対象となりません。
まとめ
相続した場合に、相続税を納付する必要がある場合、相続した財産をふるさと納税して寄附金控除を利用することはできます。
ただし、ふるさと納税では家族構成によって控除の上限が異なります。この上限以上に寄附を行うこともできますが、寄附金控除の上限を超えた部分に対しては、控除対象外となります。
また、ふるさと納税の返礼品が50万円を超えた場合には、一時所得の対象になることにも注意が必要です。
執筆者:吉野裕一
夢実現プランナー
