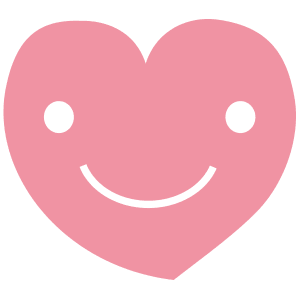国立感染症研究所の2024年第23週(6/3-9)速報データによると、咽頭結膜熱の全国の定点あたりの報告数は0.92。前週の0.89から約12%の微増となり、岩手県では、先週から警報レベルとなる3.0を超える値が続いています。都道府県別にみると、岩手県(3.18)・北海道(2.64)・富山県(2)・山形県(1.79)の順に高くなっています。別名「プール熱」とも呼ばれており、春から夏にかけて流行する感染症です。主にアデノウイルス3型(他に1、2、4、5、6、7型等でもみられる)に感染することによってみられる咽頭炎、結膜炎を主とする急性ウイルス性感染症です。なお、「プール熱」という名前の方が一般的に知られるようになり、プールに入ったら感染してしまうなどというイメージを持っている方もいらっしゃいますが、残留塩素濃度の基準を満たしているプールの水を介して感染することはほとんどありません。今回ご紹介するのは、2023年末の流行時に『感染症・予防接種ナビ』に寄せられた、家庭内で感染したとみられる35歳の方の咽頭結膜熱の経験談です。
【2024年】6月に注意してほしい感染症!溶連菌感染症高水準維持 手足口病・咽頭結膜熱と言った夏の感染症に注意 医師「マイコプラズマ肺炎徐々に増加」
35歳島根県
12月5日 娘が発熱し、受診。おそらくアデノだろうと言われる。熱は1日で収まる。
12月11日 目の充血と喉の腫れ。「また風邪引いたかな?」くらいにしか考えてなくて、疲れ目かな?程度。
12月12日 前日と同様。職場の人から目の充血すごいよと言われる。昼過ぎ頃から身体がだるくなり早退。夕方37.5℃の発熱。
12月13日 受診、アデノ陽性。38度台の熱と悪寒が続き身体がだるく、何もやる気にならない。解熱剤で何とか抑え込んでいる感じ。
12月14日 前日と同じ。充血も良くならず、ずっと寝ているわけにもいかないので出来る家事育児だけをしていた。
12月15日 一向に良くならない。それどころか咳も出始め鼻詰まりも辛い。
12月16日 もうこのまま倒れるのでは無いかと覚悟を決める。
12月17日 解熱剤も底をついてきた。現在12月18日の朝ですが、解熱剤を処方してもらうために、また病院行こうと思います。こんなに長引くとは思わなかった。
感染症に詳しい医師は…
感染症に詳しい大阪府済生会中津病院院長補佐感染管理室室長の安井良則医師は「咽頭結膜熱の原因となるアデノウイルスの潜伏期間は、5-7日ほどと言われています。期間的に、お子さんから感染した可能性があります。直接、診断した訳ではないので、分からないこともありますが、咽頭結膜熱の発熱期間は、およそ4日ほどです。今回の方は、少し、長引いたようですが、ゆっくり休んで頂くしかありません。また、目の充血がひどい時は、眼科を受診することをすすめますが、体調的にしんどかったのでしょう。お大事にしてください。」としています。
また、現在の流行状況について安井医師は「2023年秋冬から2024年初頭の流行が大きすぎたためか、現在の流行が小さく感じる方も多いと思います。しかし、現在の夏にかけての流行は、例年と比較して小さくありません。第24週(6-10-16)のデータは、過去同週の平均データよりも高い値を示しています。じゅうぶん注意が必要でしょう」と話しています。
咽頭結膜熱とは…
咽頭結膜熱とは、アデノウイルスが原因の感染症です。症状としては、38~39℃の発熱、ノドの痛み、結膜炎があります。5〜7日の潜伏期間の後に発症。まず発熱があり、頭痛、食欲不振、全体倦怠感とともに、咽頭炎による咽頭痛、結膜炎に伴う結膜充血、眼痛などがあり、3〜5日程度持続します。特に治療法はなく、対症療法が中心となります。子どもに多い感染症で、罹患年齢は5歳以下が約6割を占めているというデータもあります。生後14日以内の新生児に感染した場合は、全身性感染を起こしやすく、重症化する場合があることが報告されています。
アデノウイルスの感染経路は?予防法は?
咽頭結膜熱などを起こすアデノウイルスは、飛沫感染、接触感染などでうつります。
・飛沫感染 感染している人や咳やくしゃみ、会話をした際に、病原体が含まれた小さな水滴(飛沫)が口から飛び、これを近くにいる人が吸い込むことで感染します。飛沫が飛び散る範囲は1〜2メートルです。子どもたちが遊ぶ時などは距離が近く、また感染したことがなく免疫がない子どもが多いため、集団感染が起こりやすくなります。保育所や幼稚園などでは、咳やくしゃみなどの症状がある場合、登園を控え、まわりにうつさないようにすることが重要です。
・接触感染 感染源に直接触れること(握手、だっこ、キスなど)や、汚染されたもの(ドアノブ、手すり、遊具など)に触れることでアデノウイルスが手に付着し、その手で口や鼻、眼などを触ることでも感染します。感染者が使用したタオルなどを共用することで感染することもあります。小さいお子さんではおもちゃをなめたりすることもあり感染を防ぐことは難しいですが、接触感染に最も重要な対策は手洗いなどにより手指を清潔に保つことです。小さな子どもは大人が手伝ってあげて、正しい手洗いの仕方でウイルスを除去することが重要です。
症状がなくなっても約1か月にわたってウイルスを排出
咽頭結膜熱は症状がなくなっても、約1か月にわたって尿や便の中にウイルスを排出するといわれています。トイレやおむつ交換等で衛生に気をつけないと、感染を広げる原因となります。また、感染しても発病しない場合もあるので、保育園、幼稚園、小学校などでは流行時期には集団感染に気をつける必要があります。
登園の目安は?
厚生労働省が発行する「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改定版)」によると、罹患した子どもの登園の目安は「発熱、充血などの主な症状が消失したあと2日を経過していること」となっています。アデノウイルスに感染したことがない小さなお子さんは、感染を防ぐことは難しいですが、身の回りを清潔に保ち、体調が悪いときは無理をせずに休むなど、感染症にかからない、そしてまわりにもうつさないよう、日々過ごしましょう。
引用
国立感染症研究所:「IDWR速報データ2024年第24週」「咽頭結膜熱とは」「アデノウイルスの種類と病気」「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改定版)」
厚生労働省:咽頭結膜熱について
取材
大阪府済生会中津病院院長補佐感染管理室室長 安井良則氏