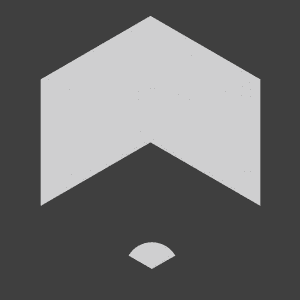2023年度駒場祭2日目の11月25日、今年4月に最年少で市長職に当選した現職の兵庫県芦屋市長・高島崚輔(りょうすけ)氏を招いたイベントが行われた。企画元は東大内のゼミ「瀧本ゼミ政策分析パート」だ。本記事では高島氏に対し、同ゼミにより行われた政策提言の様子をレポートする。後編では政策提言の後に行われたフリートークセッション及びイベントを終えての対談の様子をお届けする。(取材・海老澤茉由莉、高橋潤 撮影・新内智之)
【前編はこちら】
短時間で9人の質問によどみなく回答する市長
政策提言後のフリートークセッションでは9人の参加者から質問が寄せられた。以下にそれぞれの質問と高島市長の返答を紹介する。
──芦屋市のような財政的に余裕がある自治体が、なぜふるさと納税を受け取るのか
現状ふるさと納税は、元々の趣旨である、都市部と地方の格差を是正したり、市民に自治体が取り組んでいる事業に関心を持たせたりすることはできてないという状況にあります。
でもこのゲームに乗っている以上、否応なくやらざるを得ないという前提の中で、せめてそれをよく使うためにはどうしたら良いかということを考える必要があると思います。例えば「学校の設備を良くするために使います。ふるさと納税ください。」だと、芦屋のために他の自治体の税収を、ある種もらうことになるじゃないですか。
なので、ある意味、他の地域の税収をお借りして、うちで良い政策、良いモデルを作って、それを他の自治体に広げるという目的でふるさと納税を使うのが、今の与えられたゲームの中では一番倫理的というか、良いんじゃないかなと思います。
──日本の若者の政治参画意識の低さを残念に感じているが、若者への市民改革や意識改革などのアプローチには希望が持てない。どうしたら政治に興味を持ってもらえるのか
これはしょうがないと思うんですよね。そもそも投票率が低いという話もありますが、じゃあ忙しい若者が、大事な日曜日に、わざわざ1回も行ったことない集会所とか自治会館に行って聞いたこともない人の名前を書く行為、合理的に考えてやらないと思うんですよね。だから投票に行こうとか、社会参画しようっていう訴えかけはあまり意味がないと思っていて。それよりも大事なことは、どう成功体験を作るかだと思うんです。自分が声をあげたことによって社会が変わったなっていう成功体験とか、自分が何か行動をしたことによってこう変わったんだっていう体験です。別に小さくて良いので、それを作ることが1番大事かなと思っています。
そのために何やろうかってことで私たちは中学校の校則を見直すということをやっているんですね。きっかけは市内の中学校を回って、中学生の代表の子たちと色々おしゃべりした際に改正案を20個ぐらい持ってきた子がいたんですね。でも私が受け取って教育委員会にこれ変えてよっていうのも全く意味がないので突き返して、こちら側からアドバイスはするから自分達で頑張って校則改正をしてみようと提案しました。
その際に色々作戦会議を練ってどうしたら良いかなとみんなで校長先生や教育委員会を含めずに相談をして。ちょうど先月どうなったかと話を聞いたところ、3つ校則が変わったと。自分達が動いて、先生と交渉して、3つの校則改正を勝ち取った、こういうことが成功体験なんじゃないかなと思うんですよね。
こうした自分達が行動することで社会って変えられるのだという成功体験の積み重ねによって「投票したらちょっと変わるかもな」とか「自分の暮らしも変わっていくかもな」とか、そういう意識を持っていただけることが大事だと思います。ですので、この問題への特効薬は無いかなと思います。まあ、若い人がより(選挙に)出てくれば関心を持つ人も増えるかもしれませんが。
──高島市長は、高3で文転し、東大文一を経て、ハーバード大で文系分野を学び、後にエネルギー工学を扱った。そして卒業後に市長になるという選択をした理由とは
その時に自分が本当に興味あることをやろうって、ただそれだけです。ゆくゆくは市長になろうと思っていたわけでは全くないですね。ただ自分自身が、それこそ大学在学中に3年間休学をして、世界中の都市を回って調べたりとか、まちづくりについて学んできたりした中で、政治が果たす役割はすごく大きいなと思ったというのがまず一つです。あとは、いわゆる基礎自治体の、市であるとか区であるとか。そういうところが果たす役割ってすごく大きいなと思ったのが理由ですね。
社会を変えることができる仕事は色々ありますが、中でもやっぱりこの市の行政を動かす、その予算であったり人事であったりっていうものを動かすことができる仕事というのはインパクトがあるなと思いましたし、そういう部分を担えるのであれば挑戦したいなと思って選びました。一言で言うと、一番面白い仕事だと思ったからです。
──行政の縦割り・トップダウン的な性質は下の意見がなかなか上層部に伝わりにくいのではないか。市役所内で市の職員から新しい政策の提案があった場合、取り入れるのか
実際、うちの行政でもそこの部分は完全に解消できていないと思います。ただ、できるだけ(市の職員が)新しい取り組みをしようと思った時に、それが十分(上層部に)伝わるような仕組みは作りたいなと思っています。まず上司の人たちのマインドセットが変わることが大事だと思っています。新しい提案が出てきた際に、上司はその案の実行が無理な場合はなぜ無理なのかをちゃんと説明してほしい。それを職員に言ったことによって結構変わってきたなという部分はありますね。
自分も学んで、職員の方も提案に対する理由をしっかりと示すということをしていくと、ロジカルなコミュニケーションもできるし、下から上がってきた新しい面白そうなアイデアに対して、何も考えずに全否定するってことは無くなっていくのではないかなと思いながら仕事をしています。
──日本の若いリーダーに必要な素質や、新しいリーダーが学んでいくべきこと、身につけていくべきこととは何かお聞きしたい
私が一番大事にしたいと思っているのは対話の姿勢です。ある程度相互理解がないと物事って進まないと思うんですよね。リーダーのところに回ってくるのって、意見が分かれている案件だけで、皆んなが賛成している案件だったら勝手にやっといてよって話ですよね。その中で意思決定することは、もちろん大事ですが、意思決定よりもその後が大事だと思っていて。その後にどうそれを伝えるかが大事だと思うんですね。
コロナでハーバードが休校になった時に大学の寮の先生がずっと食堂にいて学生の話をひたすら聞き続けていました。そういう状況で対話をし続けたはすごく印象的でした。みんなどうしようもないっていう状況の中で、そういう風にリーダーが対話をする姿勢を見せ続けるってのはすごく大事だと思います。
──教育と医療の連携があまり進んでない問題についてどう考えるか。芦屋市の教育改革の中に医療と教育の連携を促進する対策を盛り込む予定はあるか。子供の発達の観点から聞きたい
芦屋はインクルーシルブ教育を伝統的に大事にしているので、ここの部分は重視しています。ただ、その中でインクルーシブ教育と言っても、なかなかインクルーシブになっていないという現状もあります。つまり、統合教育のまま留まっているということです。一緒に同じ空間にはいるけれども、一人一人に対しては適切なケアが施されていないっていう部分をどう変えていくのかというのはすごく大事だと思っています。
発達障害のグレーゾーンの子供もそうですし、コロナもあって心の中にいろいろな問題を抱えている子供も、やはり存在しています。それが不登校や、いじめという形で表出していることも、そうでないことも含めてあると思っています。ですので、例えば臨床心理士の方を学校の中に入れていくとか、そういう部分での心のケアは今進めていきたいとまさに考えているところです。
──年上の職員と協力関係を築くために実践していることは何か
「なぜ」というところをきちんと明らかにするところかなと思っています。なぜこう思っているのか、きちんと理由を説明して、だから一緒にやりませんかっていうところです。トップダウンでどうこうみたいな話ではなかなか難しいので、やっぱり共感してもらえるかどうかってすごく大事だと思います。指示だけじゃなくなぜこれなのかっていう、その裏側にある部分を伝えるっていうのがすごく大事かなと思っています。

──市長の考える芦屋市の改善していきたい点や最終的にどういった街にしたいのか
不満がないんですよ。本当にそうです。芦屋は相当恵まれた地にいると思います。
そこで私が今、一番大事にしたいのは教育なんです。芦屋で教育が変わる、良い教育のモデルを作れるとこれは日本中につながると思うんです。日本が一番大事にしなければいけないのは人だと思っていて、その点で教育がすごく大事だと。私立も良い学校が出来てはいますが、やはり公立が変わらないと世の中変わらないと思っています。公立の小中学校をどういう風に変えていくか、一人一人に合ったちょうどの学びっていうものをどう実現していくかというのが最も大事だと思っています。それに注力して取り組みたいと思います。
──大学で学んだ政治学と、実際に市政を行う上での姿勢や政治を進める方法に共通する点と異なる点は何か
現役の知事が来るようなゼミをハーバードで受けていて、そこで学んだことは結構似ている部分があると思います。対話を重視したスタイルで、実際の市政を行っている人が多かったので、そういう影響は受けているかなと思っています。
トークセッションを終えて(対談)
──イベントを終えてどのような感想を抱きましたか。また、学生主催のイベントの意義とは何でしょうか
若い世代の生の声を姿勢に反映するのは大事だと思っています。市民の若い世代はもちろんですが、日本各地で市政の課題の解決策などのアイデアを持った若い世代は多くいると思うので、イベントの形で学生から直接政策を提言してもらったことは非常に意義があると思います。(高島市長)
──政策提言を実際にしてみて伊丹さんはどうでしたか
社会実装を目指して実際に現役の市長に政策を提言するという経験を大学生のうちからできたことは非常に貴重でした。同時に、それを公開形式で実施したことが観客の方にとって社会に対してさまざまな考えや興味を巡らせるきっかけになったらいいなと思います。(伊丹さん)
──かなり鋭い質問も飛んでいましたが、どういったものが興味深かったでしょうか
事前に自身の取材記事やSNSを見ていただいた上で質問してくださったのがすごく嬉しかったですね。ふるさと納税の話とか。でも、やはり私が発信の時に大事にしたいと思っているのは「今日これやりました。」ではなくて「なぜ今日これをやりました。」とか「なぜこう決めました。」と「なぜ」をしっかり伝えることです。基本的に「何をしたか。」しか報道されないことが多くて「なぜ。」の部分の説明をあまりしないからですね。
その部分をしっかりと自分の言葉で説明することが大事だと思っていたので、それを踏まえて質問してくださったのは非常に嬉しかったです。(高島市長)
──最後のフリートークによる来場者との対話を通した心境の変化はありましたか
今日も市長になりたいといってくれた高校生がいましたが、そういった若いうちから市政に参加したい学生が出てきているのはすごく嬉しいと思いました。自身が市政をきちんと司るのは当然やるべきことではありますが、同時に政治を志していたり、市長を目指す自身の一個下の世代にも恥ずかしくないような働きをしていきたいと改めて思いました。(高島市長)
──成功体験を積み上げる経験を提供することを大事にしているとのことです。ただ成功体験を積むことができたが、声を上げた若者が後々レッテルを貼られてしまい、将来の就職に影響するといった指摘もあって声をあげにくい環境下にあるとも思いますがどのように考えますか
若者の声をきちんと受け止める技量は行政側にも必要ですし、今の状況を変えていこうと思った若者の意見を受け止めて、一方的に現状を変えるのではなくて一緒に変えていくことができるような姿勢でありたいです。
我々、行政側も受け取りやすい市民の声の形式というのがあります。例えば、最近対話集会とかの際には要望ではなくて、提案をできるだけしてくださいとお願いしています。「市民側はこうするので、行政しかできないこの部分はこうしてもらえませんか」みたいな形式で、要望ではなくて、提案をしてもらえると我々も乗りやすいです。市民からの提案を実現できないにしても、できない理由がはっきりするというのはすごく大事なことだと思っています。建設的なディスカッションをする大前提として組み立てられた提案をいただけるとありがたいですね。(高島市長)
──このイベントを実施して良かった点はありますか
公開の政策提言という形で、学生による政策提言という取り組みを発信できたことがやはり一番よかったと思っています。そしてこのイベントを通して参加者が、若者が中心となって社会を動かそうと考える契機になってほしいなと思います。(伊丹さん)
最後に、政策提言と同時に、公開イベントだったことによって問題意識の共有ができたことが非常によかったと思っています。今回、施策の実現ができなかったことはすなわち失敗ではなくて、まさに本日の養育費に関する提言は世論形成に非常に資することだと思うんですよね。参加者が問題意識を持つ契機につながったという意味でもすごく良かったんじゃないかなと思います。(高島市長)

The post 【後編】高島市長の鋭い指摘が飛んだ公開政策提言 【瀧本ゼミ政策分析パート駒場祭イベントレポート】 first appeared on 東大新聞オンライン.