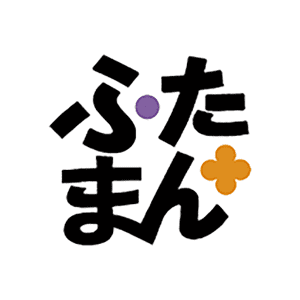2023年11月17日に公開された劇場作品『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』、略して「ゲ謎」。本作では鬼太郎の父「目玉おやじ」が人間だったころの話が明かされ、SNSを中心に大きな反響を呼び、興行収入は27億円と異例のヒットとなった。
それでは、目玉おやじ以外の妖怪たちはどうやって誕生したのだろうか? その多くは、民間伝承などで語り継がれる実際の妖怪である。そこで鬼太郎ファミリーのなかでも伝承が残っているものに的を絞り、その正体について調べてみた。
■意外と可愛かった「砂かけばばあ」
「砂かけばばあ」は、奈良、滋賀、兵庫など近畿地方を中心に伝わる妖怪だ。アニメでは目つぶしに砂を投げつけたり口から砂を吐いたり、何かとアグレッシブな印象が強い砂かけばばあだが、伝承では人に砂をかけて脅かすだけ……意外と控えめな妖怪だ。
その正体は狸やイタチが化けたものとする説や、実際に人に砂をかける老婆がいたとする説など、伝承地によってさまざまのようだ。狸が本当に化けるかどうかは置いておいて、たとえば犬がフンをしたあとに後ろ足で砂を蹴散らす様子などを思えば、砂をかける行為と動物とを結びつけるのは何となく合点がいく。
また、スズメやヒバリといった小鳥を怪異の正体とする説は現実的にもあり得そうだ。彼らは体についた寄生虫を落とすため砂浴びをする習性を持つ。砂浴び後に空を飛ぶと体についた砂が落ち、下を歩く人はまるで何もないところから砂をかけられたように感じることだろう。
あの強面のおばばの正体が動物や小鳥だと思うと、どこか可愛らしく微笑ましい。
■意外と危険な妖怪だった「子泣きじじい」
砂かけばばあ婆とは対照的に、ぱっと見は好々爺といった印象の「子泣きじじい」は、実は意外と危険な妖怪のようだ。夜道で赤ん坊の泣き真似をし、親切な通行人が抱きあげると石のように重くなる……というのはアニメからも想像がつくが、さらにその後、抱えた人を圧死させるというのだ。
この妖怪は徳島に伝わるものとされていたが、のちの調査により、実際には子泣き爺の伝承はなかったことが判明したという。一方で、このように赤ん坊の泣き声で人をだまして悪さをする妖怪の伝承は日本各地にある。加えて、徳島に赤ん坊の声を真似ながら徘徊していた老人がいたという話から、これらの情報が錯そうして「子泣きじじい」という伝承を生み出したのではないか……という推察がされている。
それにしても“赤ん坊(のような老人)の重みで押しつぶされる”というのは、現代の感覚からすると育児の過酷さや介護問題のメタファーのようにも感じられてしまう。これが子泣きじじいのもう一つの正体だとしたら? たしかに石のように重い話だ……。
■「ぬりかべ」は暗闇が作り出した?
福岡や大分など九州地方では、夜道を歩いていると突然前に進めなくなるという伝承がある。横にそれてもやはり進めず、まるで目の前に見えない壁が広がっているようだという。この現象こそ、「ぬりかべ」という妖怪の仕業とされている。
その正体は砂かけばばあと同じく狸やイタチとする説が多いようだが、現象そのものについての説明はあまり見かけない。
とはいえ“夜道で突然前に進めなくなる”というのは、比較的分かりやすいことではないかと思う。今と違って電気などなく、本物の暗闇がすぐそこにあった時代。提灯一つで闇夜を行くさなか、ふと不安や恐怖に囚われて進めなくなることがあっても不思議はないだろう。闇が消えつつある現代では、ぬりかべは真っ先に消えてしまう妖怪かもしれない。
■子どものしつけにも大活躍の「一反もめん」
「鬼太郎ど~ん」とのんびりした九州弁が可愛らしい「一反もめん」は、その方言どおり鹿児島県に伝わる妖怪だ。
夕暮れ時になると、どこからか一反(10メートル×30センチくらい)ほどの木綿のようなものが飛んできて顔に巻き付いて窒息させたり、人をさらったりするのだという。昔は夕暮れ時になると親が子に“早く家に帰らないと鬼にさらわれるよ”などと言ったものだが、伝承地では鬼ではなく一反もめんがさらいに来るそうだ。
この地方では土葬の際に墓に木綿の旗を立てる風習があり、これが風に飛ばされてひらひら飛んでいるのが一反もめんの正体ではないかという説がある。墓に立てていた旗が夕暮れどきに飛んでいるさまは、たしかに不気味に思えるのも分からなくはない。恐ろしい話を付属させて子どもを脅すには十分な材料だ。
こうして見ると妖怪の正体とは、日常の些細な不思議と、それに対する人々の不安や恐怖といった心の動きなのだろう。現代人はそういった感情を必死に排除しようとするが、昔の人々は妖怪の仕業と捉えて共存しようとした。その心の余裕を見習いたいものだ。