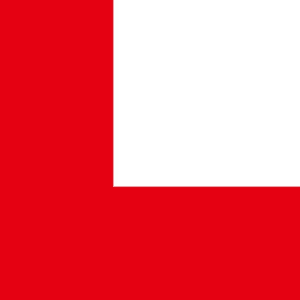映画評論家・ミルクマン斉藤さん(本名:斉藤和寛)が亡くなって半年あまり。関西を拠点にしながらも数々のメディアに寄稿し、その類い稀なる洞察力と情報量をもって鋭く作品に切り込む論評は多くの映画人、読者から支持を集めた。その生前のご功績を偲び、ミルクマンさんとともにLmaga.jpの映画ブレーンとしても活躍いただいた芸能ライター・田辺ユウキさんに追悼文を寄せていただいた。

生前のミルクマン斉藤さん(左)と田辺ユウキさん(写真は2014年のイベント時のもの)
「田辺くんは今、自分のインタビューや書くことについて自信を持ってるんちゃうか。読んでたらそれが分かるもん」
3、4年くらい前、ミルクマン斉藤さんにそのように言われた。私は「まあ、そうですね」くらいの軽い返事をしたが、内心、ミルクマンさんに認められた気がして嬉しく思った。
ミルクマンさんは私より年齢が16歳上。私は当然ながら、映画、音楽、書籍などあらゆるカルチャーの知識量は圧倒的に劣る(いや、ミルクマンさんの場合は年齢差云々の話ではないが)。加えてそれらの知識を土台とした、『ミルクマンワード』といえる言葉のチョイス、文章のテンション感とリズム感があった。それは「センス」で片付けられるものではなく、間違いなく幼少期から見続けてきた諸芸術作品の影響を感じさせていた。
とりわけ印象的だったのが、人名の表記と発音へのこだわりである。映画『タクシードライバー』(1976年)のマーティン・スコセッシ監督は、日本では一般的に「マーティン・スコセッシ」と表記されるが、ミルクマンさんは頑なに「マーティン・スコセージ」と呼んで譲らなかった。無論、ツイッターも「トゥウィッター」だった。そのように文字面へのこだわりが半端なかったからか、深川栄洋(よしひろ)監督のことは結構長い間「えいよう」と『そのまま読み』をしていた。
私が、そんなミルクマンさんのことを初めて意識(認識)したのが2001年10月である。私は当時、半年後に卒業を控えた大学生。記者、ライターを目指していたので学生時代からいろんな書籍を読んでいた。そして、その時期に手にしていたのが『笑うシネマ』という雑誌。笑える映画がいろいろ掲載されていたその書籍にミルクマンさんは寄稿していて、「限りなきモラルの欠如は人生の謳歌へと転化する」とのテーマのもと、ジュリアン・ディヴィヴィエ監督の『アンリエットの巴里祭』(1952年)、ジャン・ルノワール監督の『草の上の昼食』(1959年)、ジャン=ポール・ラプノー監督の『うず湖』(1975年)、エドアール・モリナロ監督の『エレベーターを降りて左』(1988年)、中平康監督の『あした晴れるか』(1960年)をピックアップ。
そこでの「巨匠ジャン・ルノワールともなると、性的モラルはあたかも宇宙最大の害毒のように描かれて凄まじいばかり。『素晴らしき放浪者』なんてのはほとんど危険思想の域だが、『草の上の昼食』の能天気さもまた人倫を遥かに図抜けている」という一文に衝撃を受けた。文章の弾け方、言葉の組み合わせ方、ワードチョイスなどは、今まで読んだどの映画紹介文にもないもので、それでいてちゃんと作品の特徴が捉えられていた。この一文をミルクマンさんは38歳という若さで書いた。その事実は現在まで私の心のなかにずっしりとあり、「あの一文をミルクマンさんは38歳で書いたんだ」「自分はもう38歳を過ぎているのにあれを超える一文を生み出せていない」などと考えながら今日までライターをやってきている。

Lmaga.jpの映画ブレーンたち(左からミルクマン斉藤さん、田辺ユウキさん、春岡勇二さん)
さらにミルクマンさんの『見る目』への信頼を深めたのが、筧昌也監督の『美女缶』(2003年)や冨永昌敬監督の『亀虫』(2003年)などへの高評価と批評である(ちなみにその頃、私は雑誌・WEBの編集社に勤務していた)。おそらく雑誌『Lmagazine』での映画評だったと思うが、これらの極めてアバンギャルドな作品を的確に評していたのは、当時の大阪のメディア関係者ではミルクマンさんくらいだった。
その後、私は『Lmagazine』への寄稿を通してミルクマンさんと接点を持つようになる。大阪を拠点にして映画などのカルチャーネタを扱っているメディア関係者は、東京に比べるとどうしても作品や人物に対するセンサーの働きや感度が鈍い。ある程度、全国的に売れたり名前が知られたりしているものでなければ気にも留めないし、おもしろいかどうかなども正当に判断できない。
その点で私自身は、新しいものに関しては有名・無名関係なくかなり早めに、そして細かく見聞きするタイプではあった。ミルクマンさんももちろんそうで、なおかつ「これはなぜおもしろいのか」「どういうところがおもしろいのか」をお互いにしっかり分析し合える関係性ではあった。新しいもの、という点では私の方が先取るのがやや早い傾向にあったので、ミルクマンさんもいろいろこちらに頼ったり、尋ねたりしてくれた。今や大人気の映画監督となった、入江悠、今泉力哉、小林啓一などを初期からチェックして、ちゃんと「おもしろい」と言えていたのは、関西のメディア関係者ではミルクマンさんと私くらいだった(あくまでメディア関係者に限った話である)。
と、こういう風に書いていくと「田辺ユウキというライターはミルクマン斉藤さんに憧れていたんだな」と思われるかもしれないが、そんな気持ちは一つもない。もちろん、リスペクトはしている。しかし憧れはまったくなく、知識は絶対敵わないにしても、新しいカルチャーに対しての眼力みたいなものについては「ちゃんと張り合いながら活動しよう」と思ってここまでやってきた。
これもミルクマンさんが話していたことだが、「田辺くんのインタビュー記事とかを読んで、『これは負けた』『これは勝った』とか思ったりしてる」と言ってもらったことがある。実は私もそういう風にミルクマンさんの記事を読んだりしているところがあった。だから、これも内心「分かります」と返事をしていた。
偉そうな口ぶりになるが、ここ2、3年、体調をよく崩すようになってからのミルクマンさんが書く原稿は精彩を欠くものも少なくなかった。おそらくそれはご自身も気づいていたはず。だからこそ最後にもうひとつ、私が「これは一生かけても追いつくことができないな」と感じられる一文が読みたかった。ミルクマンさんから認めてもらえて嬉しかった・・・が、「いや、まあでもミルクマンさんにはやっぱり手が届きませんよ」とご本人に伝えたかったのが素直な気持ちである。
文/田辺ユウキ