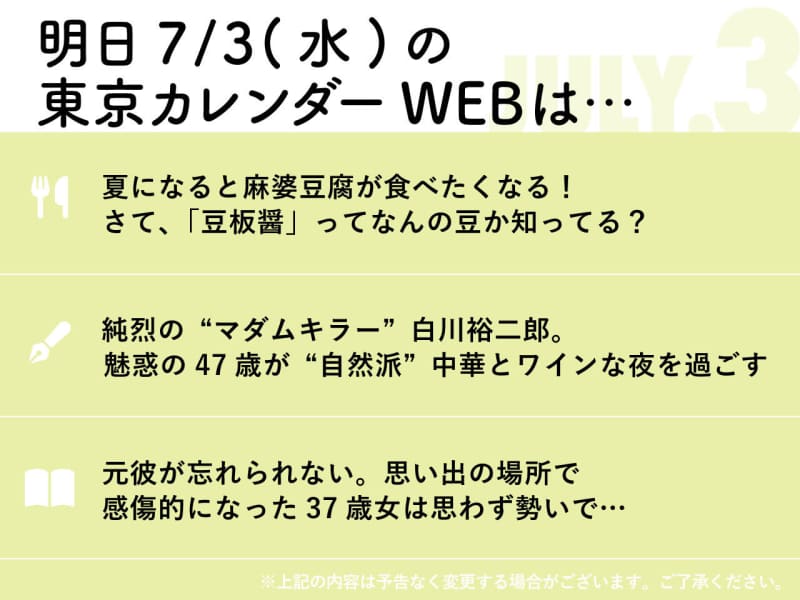◆前回のあらすじ
食品メーカーの営業である唯子は、同じ会社のデザイン室に勤める瑛太と恋人同士。しかし瑛太は最近、仕事でなかなか結果が出せていない様子。
そんななか、瑛太が応募した社内コンペの結果が出たが…。
▶前回:出会って1ヶ月で交際に発展。社内で憧れていた彼を落とした25歳女のテクニック

クリエイターの男/唯子(25歳)の場合【後編】
正午きっかりに届いた社内メール。
『【重要】新製品のロゴコンペの審査結果のお知らせ』と書いてあるそのメールを開くと同時にデスクの内線電話が鳴り、唯子は思わずうわずった声を上げた。
「私の案が採用…!?」
かかってきた内線電話は、審査を担当する商品企画室からだ。唯子の応募した案が満場一致で採用された、とのことだった。
受話器を持った手が、震える。
― まさか、軽い気持ちで出したのに。
応募したことは瑛太にも言っていなかった。募集要項には『デザイン部に限らずすべての部署の社員も応募可能』と記載があったのを見て、ほんの出来心で応募したのだ。
片手間で、しかも1点のみ作成しただけ。販促ツールのデザインを考えるついでに思い浮かんだ案を軽い気持ちで出したまでで…。
「メール見たよ、福浦くん。すごいじゃないか」
受話器を置くと、すぐに営業部長がやってきて、その快挙をたたえてくれた。
「ありがとうございます。実は私、美術を専攻していた時期があって、独学でもデザインを少々勉強していたんです」
「おおー、元アーティストだったのか。福浦くんの作る販促ツールはセンスもいい上に、考え方も独創的だと前から思ってたんだ」
調子いい部長の軽口だとわかっていても、褒め言葉は嬉しい。唯子は自分の中にあるクリエイターの残り火に気づいた。
「これからお祝いに『美濃金』に鰻でも行くか?あそこの鰻は絶品だ。もちろんご馳走させてもらうよ」
「…申し訳ありません。またの機会にぜひよろしくお願いします」
唯子は、せっかくの部長の誘いを断ってしまった。
「おおそうか…残念だ」
隣でおこぼれにあずかろうとしていた同僚たちはため息をつく。後ろ髪をひかれたが、仕方ない。唯子には、このことを真っ先に伝えなければならない人がいるのだ。
唯子はデザイン室のある上層階フロアへまっすぐ向かった。
フロアに降り立つと、ちょうど瑛太も昼食休憩に出るタイミングだった。デザイン室から彼らしき人物が出てくる影を見つける。
社内一斉のメールで、瑛太も結果を知っていることだろう。わざわざ会いに来たのは、彼の反応がやはり気になったからだ。
「あ、瑛…」
しかし、瑛太の姿がはっきり目に入ったところで、唯子は慌てて身を隠した。隠さざるを得なかった。
瑛太は、明らかに落ち込んでいる様子だったから。
視線は虚ろで、傍から見ても分かりやすく肩を落としている。
「…」
唯子の足はすくみ、結局、声をかけることはできなかった。
― 私、してはいけないことをしてしまったんだ。
「直接報告して、瑛太に褒めてもらおう」…どこかでそう期待していた自身の傲慢さにも落ち込む。
以前、悩みを吐きだした瑛太の苦悶の表情が脳裏に浮かぶ。彼の気持ちを考えながら、唯子は静かにフロアを立ち去ったのだった。

22時過ぎ。ひとり暮らしの1LDKに帰った唯子は、帰るなりリビングの中心に置いてあるヨギボーの特大クッションに身を預けた。
― なんか、疲れた…。
今日は目まぐるしく色々な事が起こった一日だった。ただ、それが心地のいい疲労であることは否めない。
明かりをつけるのも忘れた薄暗い部屋。にもかかわらず気持ちは晴れやかだ。天井を見上げ、口元にほのかな笑みを浮かべながら唯子は一日を回想する。
昼に選考結果が知らされてから、午後は商品企画室での会議や、面談、契約などに関する打ち合わせで、終始バタバタしていた。
「実に素晴らしい作品で、すんなり決まりました」
「今後、何十年も愛されるロゴになるでしょう」
「営業部の社員が考案したなんて前代未聞だよ」
天の上のような役職の上司も紹介され、その栄誉をたたえられたのも嬉しかった。

コンペに通った。みんなに賞賛された。
単純だけど、自分という存在が認められた喜びで、ムクムクと生気が満ちてきている。
ずっと抱えていた空虚。その理由が、コンペで採用されたことでわかった。
― 私やっぱり、クリエイターに未練があったんだ…!
今日の出来事で、抱えていた心の隙間が埋まったような気がしたのだ。
「デザイン室へ異動したいっていう希望はあるの?」
面談では、唯子が美術やデザインの素養があると知った者からそんな言葉をかけられたことを思い出し、くすぐったいような喜びが湧き起こる。
まんざらではない話であったが…瑛太の反応だけが気がかりだ。
唯子はむっくり起き上がり、LINEを開く。なんだか怖くて、お昼以来、ずっとスマホを見るのを避けていた。
案の定、異動した先輩や同期入社の友人からのいくつものお祝いの中に、瑛太からのメッセージが1件届いていた。恐る恐る開いてみる。
『結果見たよ。すごいね』
いつもの彼らしくない、淡白な文面。ただ、平静を装った悔しさがじんわりと伝わってきた。
『ありがとう』
唯子は、ただそれだけ返信して、再びスマホを伏せた。
― まあ、大丈夫だよね。
昼に目撃した瑛太の失意に打ちひしがれた表情を思い出すも、無理やりかき消し、自分に言い聞かす。普段通り接して、少しすれば、普段の素直な明るさに戻ってくれるはずだと。気を使うのも彼のプライドを刺激するだろうから、と。
◆
「おはよー!瑛太」
その決意通り、唯子は翌日、さっそく出勤時間を彼と合わせ、会社のロビーで顔を見るなり自ら声をかけた。
「あ…唯子、おはよう。元気だね、朝から」
「昨日ぐっすり眠ったからね」
「そっかぁ…」
瑛太の顔を見る限り、まだ落ち込んでいたようだった。ただ、気にしないそぶりで話しかけていると、次第に明るさを取り戻してくれた。
「ねぇ瑛太、今日の夜空いている?行きたいお店があるんだ」
「別にいいけど…」
瑛太の優しい笑顔に唯子はホッと胸をなでおろす。
― よかった。やっぱり気にするほどのことじゃないみたい。
しかし…。
ロゴコンペの結果発表から数週間たった。
「福浦さん、ちょっと時間あるかな。例のコンペの件で」
祝日を挟んだ連休明けの朝。出社するなり唯子は、コンペの主催である商品企画部の上席から直接呼出しを受けた。
「あ…はい」
わけがわからぬまま、唯子は社内でも一番大きな会議室に案内される。
― 一体、何があったんだろう。
しん、と静まり返った会議室。そこには総務のコンプライアンス担当係も数名同席していた。
無機質なオフィス空間ながらも、重い雰囲気に押しつぶされそうになる。何もしていないのに責められているような圧力を感じ、おろおろと目を泳がせる唯子の戸惑いをよそに、担当者は淡々とした口調で話を切り出した。
「…私の作品が盗作って?」
「はい。匿名で告発がありました。身に覚えはありますか」
告発の内容とは、唯子の応募作がある画像サイトに掲載された絵柄の一部と酷似している、というものだった。
「ありません」
食い気味に断言する。断じて「していない」と言いきれる濡れ衣だったから。盗作など寝耳に水だ。
「ですよねぇ。わかりました。ま、単なるやっかみでしょうね」
「え…?」
以外にあっさりと、唯子の言い分は受け入れられた。
「酷似と言っても、モチーフである野菜の形が似ている程度のものでしたし、私たちも訴え自体に首をかしげています。念のため本人の主張を聞いてみなければと、こうやってお呼びさせて頂いたわけです」
「ありえません。一体だれが…」
唯子が怒りをあらわにすると、コンプライアンス担当が周囲の面々と目配せをし、SNSや掲示板の投稿データの数々が印刷されたコピーを提示した。
「ご存じですよね。この投稿者と同じ方です」
それは、SNSに疎い唯子が初めて目にする罵詈雑言であった。
「なんです?これ?」
唯子の言葉に、周囲は途端に動揺する。知っているものだと誤認していたようだ。
無理矢理尋ねて教えてもらう。どうやらコンペの結果発表後、SNSや掲示板に、会社や唯子に対する誹謗中傷が見られるようになったらしい。複数社員から通報があったという。

『…社の営業部にとんでもなく緩いオンナがいるらしい』
『営業部の福浦唯子ね。ジジイころがしで有名だよね。部長の愛人の噂』
『あのコンペは上層部に取り入った出来レースだったわけ』
『クソダサいし、センスもないのになぜ選ばれたのか納得』
唯子は怒りで震えたが、同時に、暗雲が胸の中に立ち込めるのを感じた。
― 嫌な予感…。
「内容からデザイン室の社員であることは確定的だったため、社内ネットワークを監視したところ、あっさり犯人は分かりました。
社内からの書き込みであること。たった1名が複数のアカウントを使い分けで行っていたこと。そういった悪質性を鑑みて、該当人物に対してはしかるべき処分をする予定です」
ドクン、と心臓が跳ねる。
嫌な予感がどうやら当たってしまっていたことに、胸がつまる。
処分される予定の人物に、唯子は心当たりがあった。
…少し前から瑛太は、体調不良で会社を休んでいるのだ。
「信じられない…」
「悔しかったんでしょうね。十数点応募したにもかかわらず、デザイン室とは無関係の社員に決まってしまったから」
担当者は犯人の名前こそ告げなかったが、唯子にとってはほとんど答え合わせのようなものだ。
目の前が、真っ暗になる。
恋人への失望で、唯子はどん底へと突き落とされたのだった。

3ヶ月後、唯子はデザイン室へ異動となったが、そこに瑛太はいなかった。
あれからすぐ、彼から「長崎の実家に帰ることになった」と一方的に別れを告げられ、連絡もブロックされてしまったのである。
「自分より仕事がデキる女は、彼女にしたくない」というのが、瑛太の本音なのだろう。
失望。諦め。怒り。しばらく連絡しても反応もなく、最後のメールが来ても、唯子は縋ることもしなかった。
この結果は、お互いの自業自得だと理解していたから。
もう、どうあがいても前のような関係には戻ることはできないのだと、納得の上の結末だった。
「ええと、デスクはここかな…」
異動後、初出社の日。
唯子が使うことになったのは、瑛太が使っていたワークブースだった。あまりの皮肉さに、乾いた微笑みを浮かべることしかできない。
彼が退社となって以来そのままだったようで、デスクはほこりにまみれている。
机の上のコミカルな落書きはそのまま。文具も引き出しに入ったままだ。かすかに感じるキリリとした胸の痛みを誤魔化しながら掃除をしていると、Macの裏に置き去りにされた一枚のポストカードを見つけた。
唯子がかつて心を奪われたロビーのポスターを印刷したものだ。
― これはもしかして…。
コンプライアンスとネットワークセキュリティーの対策を喚起する、そのデザイン。皮肉めいた瞳で眺めていると、その裏に瑛太の字で何か書かれているのを見つけた。
<<俺のファン第1号の唯子へ>>
クセのある弾んだ文字を、唯子はただ茫然と見つめることしかできなかった。
瑛太から初めて声をかけられたときの、彼の笑顔を思い出す。同時に、コンペに落選した時の虚ろな表情も重なる。
― クリエイターの繊細さは、理解できていたはずなのに…。
価値観と性格が通じ合った、似た者同士のふたり。だからこそ、互いに自分自身が大好きな者同士でもあった。すれ違うのも当然だ。
唯子は自身の至らなかった部分を反省しつつ、ポストカードを胸に抱く。
彼とは、恋人同士としてはうまくいかなかった。
だけどいつか、同じ方向を夢見る同志として、瑛太と再会できる日が来ることを、唯子は胸の奥で祈るのだった。
▶前回:出会って1ヶ月で交際に発展。社内で憧れていた彼を落とした25歳女のテクニック
▶1話目はこちら:富山から上京して中目黒に住む女。年上のカメラマン彼氏に夢中になるが…
▶Next:7月9日 火曜更新予定
スパイスの魔力に取りつかれた、個性派男子がオススメする絶品カレーって?