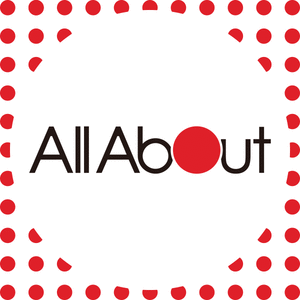乳幼児の医療費を助成してくれる制度
乳幼児の医療費を軽減してくれるのが、自治体がそれぞれ独自にサポートする乳幼児の医療費助成制度。こうした行政によるサービスが充実しているかどうかによっても、「住みやすさ」も違ってきます。
乳幼児の医療費助成って?
乳幼児期は頻繁に病気をしたり、思わぬケガをしたりと、病院への通院の機会も少なくはありません。
本来であれば、公的医療保険の自己負担割合は、未就学児は2割、小学生からは大人同様、3割の自己負担があります。しかし、乳幼児が病院で診察や治療を受けた時に、この医療費の自己負担分の一部または全額を自治体がサポートしてくれることになっており、この制度を乳幼児の医療費助成制度と言います。
助成の内容や助成を受ける方法は自治体で異なります。全体的な傾向として、中学を卒業するまでの子を対象とする(長いものだと高校まで対象となる自治体も)など対象年齢の幅が広がり、中には「こども医療費助成」などと呼んでいる自治体も。
制度は70年代にスタートし、その後、子育て支援策の一貫として拡大してきました。特に過去10年ほどの間に対象年齢が上がり、内容も充実する等大きく拡大してきた感があります。
まずは、自分の住んでいる自治体の制度はどうなっているか、確認してみましょう。こうした行政によるサービスが充実しているかどうかは、ファミリー世帯にとって「住みやすさ」にもつながります。
なお、乳幼児の医療費助成とは別に、出生時体重が2000g以下だった未熟児や、心臓などに異常があり、手術や入院の必要がある場合、あるいは特定の慢性病の場合に、医療費を助成してくれる国の制度もあります(所得に応じた自己負担あり)。
助成内容は自治体で異なる
前述の通り、助成の内容・方法等は自治体で異なります。首長の方針や自治体の財政状態などによって差が出ていると見られます。何歳まで助成を受けられるかといった助成期間は、「3歳まで」、「小学校入学前まで」、「中学を卒業するまで」、「高校を卒業するまで」などかなりの幅があります。
また、自己負担額全額を負担してくれる「全部助成」なのか、自己負担分の一部は自分で負担する「一部助成」なのかも異なります。他にも、入院と通院で助成内容が異なるかどうかや、助成を受けられる親の所得制限が設けられているかどうか(所得制限は設けられている方が少ない)も異なる点です。
こうした内容は、随時変更になる可能性もあるので、自治体の情報には常にアンテナを張っておきましょう。
制度利用の対象者は?
対象となる子どもの年齢は、自治体で異なります。幼児の医療費助成制度を利用する大前提として、赤ちゃん自身も健康保険に加入していなければいけないという点に気を付けましょう。
対象とならない乳幼児は次の通りです。
□国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない乳幼児
□生活保護を受けている乳幼児
□施設等に措置により入所している乳幼児
乳幼児を養育している保護者に所得制限が設けられている場合もあります。所得要件等も自治体で確認しましょう。
助成される範囲は?
医療保険の自己負担分の全部、または一部が助成されますが、内容は自治体で異なります。通常、薬の容器代や入院時の食事療養費、差額ベッド代などを除きます。
<対象となるもの>
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等(自治体で異なります)
<対象とならないもの>
□医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等) 。
□交通事故等の第三者行為
□健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
など(自治体で異なる場合があります)
助成方法
助成を受ける方法は、病院の窓口で専用の乳幼児医療証を提示することで助成を受ける場合が多いようですが、中には、いったん窓口で通常通り支払って、あとから自治体に請求をする方法もあります。
ただし、住んでいる自治体以外の病院で診療を受けた場合は、いったん立替えてあとから請求をする場合もありますが、中には助成されない自治体もあります。実家へ帰省しているときに急に病院へ行く可能性もあるので、あらかじめ確認しておくといいでしょう。
手続きは 速やかに!
「マル乳医療証」が交付される自治体では、役所に申請して発行してもらいます(自治体によっては健康保険証に子どもの名前が記載されるだけの場合もあります)。
申請に必要なのが、赤ちゃんが医療保険に加入していること。そのため、赤ちゃんが誕生したら、会社員なら総務または健康保険組合に、自営業なら役所で国民健康保険への加入手続きを済ませます。
所得制限などで引っかからない人は、保険証に名前が載ったら、さっそく助成制度の手続きを行います。手続きに必要なものは、あらかじめ役所で確認しておきましょう。
自治体によって医療費助成の内容が異なるので、自分の住んでいる市区町村ではどうか、あらかじめ確認しておくことが大事です。医療費助成の対象になる場合、申請に必要な書類は妊娠中に確認しておき、産後すみやかに済ませるようにしましょう。
なお、制度の内容や条件が変更になったり、あるいは所得制限の関係で途中から利用できるようになることもありますので、利用するための条件やその変化に注意しましょう。年に1回はチェックすることをお勧めします。