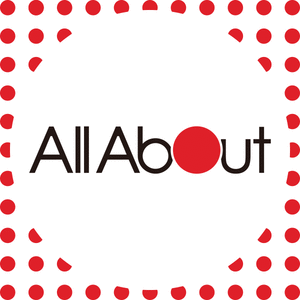中途退職をして現在失業中という方は確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付される可能性があります。また確定申告を行うことで、翌年の住民税の額が下がる可能性もあります。自分の場合はどうなのか、チェック方法などをご紹介します。
中途退職後、今は無収入でも住民税を払うケースはある
住民税の基本的な仕組みは、前年の所得の状況に応じて今年課税される、ということです。つまり、中途退職した方で、現在は収入源がない場合でも、基準となるのは「前年の所得の状況」ですから、住民税が課される可能性が高いということです。
例えば
・現在は失業中、あるいは求職中
・昨年結婚して、現在は専業主婦
・社会人から学生になった
という場合には、現在は収入がないかもしれませんが、基準となる「前年の所得の状況」に応じて、住民税が課されることになります。

中途退職した方は源泉徴収票をチェック!
中途退職をした方は、前の勤務先からもらった源泉徴収票が手元にあるはずです。そこには、年末調整を受けた源泉徴収票とは異なる特徴があります。
中途退職した方の源泉徴収票には、以下のような情報しか記載されていません。
・年収……年初から退職日までの給与の合計
・社会保険料……年初から退職日までに給与天引きされた社会保険料の合計
・源泉所得税……年初から退職日までに給与天引きされた所得税の合計
勤務を継続している場合も、中途退職した場合も、働いていた翌年の1月31日までに、源泉徴収票と同じ内容を記載した「給与支払報告書」というものが、勤務先から各市町村へ送られます。その内容に基づいて住民税が課税されるのです(冒頭の「前年の所得の状況に応じて課税される」というのはこういうことです)。
ここで注意したいのが、中途退職した場合の源泉徴収票は「月々の給与明細を集計しただけのもの」であるということです。これを元に計算された住民税は果たして適正といえるのでしょうか。
それを判断するには、源泉徴収票の記載事項でいくつかポイントを確認する必要があります。
チェックポイント1:記載箇所が3カ所しかない
上記ですでに書いたように中途退職者の方の源泉徴収票には3カ所しか金額が記載されていません。
その3点とは
・年収……年初から退職日までの給与の合計
・社会保険料……年初から退職日までに給与天引きされた社会保険料の合計
・源泉所得税……年初から退職日までに給与天引きされた所得税の合計
なのですが、要はその3点以外に考慮される所得控除等があれば、
・それが考慮されていない所得税が差し引かれたままになっている
・それが考慮されていない住民税が翌年課税される可能性がある
ということです。
以下、具体的にどのようなチェックポイントがあるのかみていきます。
チェックポイント2:社会保険料控除
図は、中途退職したある方の源泉徴収票です。これを例に、チェックすべきポイントをご説明しましょう。

この源泉徴収票では5月31日に退職したことになっていますが、その後、本人が国民健康保険や国民年金を支払っていないのでしょうか。
あるいは任意継続といって、いままで会社と折半だった社会保険料を全額本人負担で継続して支払うことができるのですが、そのような制度は利用していないのでしょうか。
会社では5月31日に退職した日以後のことは把握していないので、会社が発行した源泉徴収票に記載されることはありえません。
もし、そのような事実があるのであれば、この源泉徴収票の社会保険料控除額は正しいとはいえず、通常はもっと多額になる、つまり、控除が多くなるケースは多いのです。
チェックポイント3:生命保険料控除や地震保険料控除
また、もしこの方が生命保険料控除の対象となる生命保険や地震保険料控除の対象となる地震保険に加入していたのであれば、当然、その該当箇所に数値が記入されていることになります。しかし、図の例では空欄です。
それは、中途退職したことにより年末調整の対象者から外れているため、生命保険料控除や地震保険料控除が考慮されていないのです。
年末調整の対象者であれば、雑損控除・医療費控除・寄附金控除以外の所得控除はすべて年末調整で考慮されます。
逆にいえば、年末調整の対象者から外れると、退職後の社会保険料や生命保険料控除・地震保険料控除などまったく考慮されない源泉徴収票が発行され、それに基づいて住民税が課税されています。場合によっては住民税を払い過ぎということにもなります。
チェックポイント4:源泉所得税は月収ベースで差し引かれている
毎月毎月の給料から差し引かれる源泉所得税額は、社会保険料控除後の給与の額と扶養親族等の数で定められています。つまり、月収ベースで決められているということです。
一方、所得税の基本は年間の所得の状況に応じて税額を決定する、というのが基本なので、年収ベースで決定するということです。
たとえば、33万3000円の額面の給与をもらっていた人が、3カ月で退職したとします。この場合、年収ベースでは99万9000円ですので所得税はかかりません。
ですが、実務においては、その人が独身者と仮定したら、源泉徴収税額表にあるとおり、
・1万1120円×3カ月=3万3360円
の源泉所得税が差し引かれたままとなっています。

このような方は、確定申告するだけで、3万3360円の差し引かれたままの源泉所得税額が還付されます。
中途退職後、確定申告をすれば払い過ぎた所得税が戻ってくる
このような方が所得税の還付を受け、住民税の負担を軽減させるには、源泉徴収票に記載されていない所得控除があることに気づき、あるいは所得税が月収ベースで差し引かれていることに気づき、確定申告(還付申告)をする必要があります。
確定申告を行えば正しい所得税が計算され、年初から退職日までの給与から天引きされた源泉所得税が多ければ還付を受けることができます。
また、そのデータが税務署を通じて、各市区町村に流れる仕組みにもなっているので、各市区町村も適用可能な所得控除が考慮されていない給与支払報告書ではなく、適用可能な所得控除が考慮された確定申告書による適正な住民税課税が可能となるのです。
所得控除が適用漏れになっているということは、必要経費が少なくカウントされているのと同じですから、余分な所得税も支払っているのみならず、過大な住民税を支払うことにもつながります。