街づくり・持続可能性委員会/小宮山委員長「鉄の〝飽和〟は持続社会の希望」
2020年の東京五輪・パラリンピック大会での持続可能性に配慮した運営に向けたさまざまな取り組みについて話し合う、公開ブリーフィングが14日、都内で開催され、同大会の組織委員会で街づくり・持続可能性委員会委員長を務める小宮山宏氏(三菱総合研究所理事長)が「東京大会は日本が21世紀の持続社会をどう考えるのかを全体像として示す機会にすべきだ」と語った。〝持続社会〟とは同氏が主唱する〝プラチナ社会〟と同義であるとした上で、「先進国における持続社会の特長は〝飽和〟だ。鉄に関して言えば、高度成長の時期にビルや自動車などの形で一気に蓄積され、今や世界的に飽和が近づいている」と指摘。中国は5年後の20年に1人当たりの鉄鋼蓄積量が日本と同水準の飽和状態となり「世界も50年の前には飽和状態になる可能性が高い」とした。
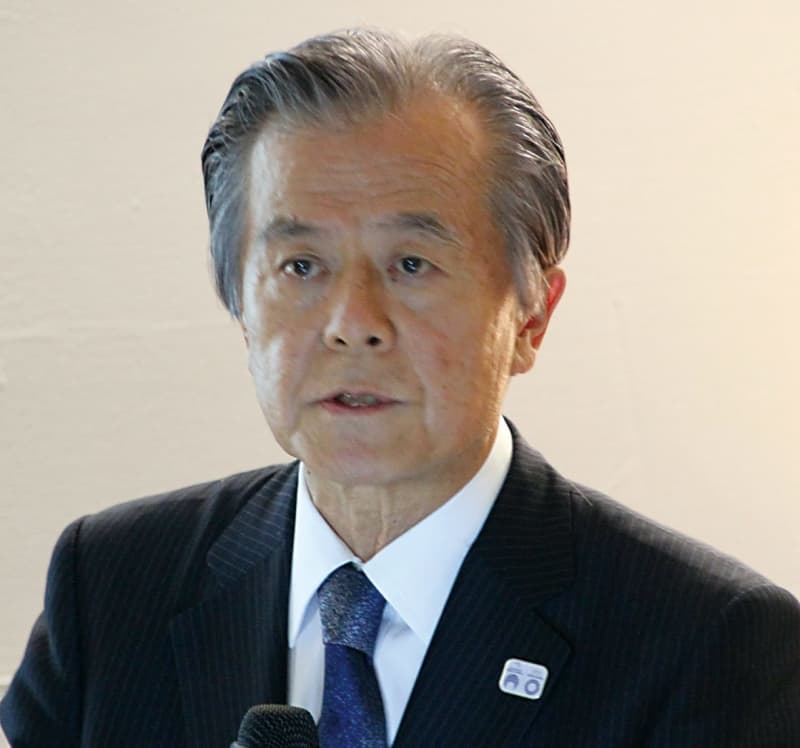
鉄が〝飽和〟状態にあることについては「量的な経済成長から質的な成長に移行するのが必然であり、同時に〝飽和〟とは持続社会の希望だ」と強調。飽和の意義について「必要十分な鉄などの資源が都市鉱山の中にあるということであり、言い換えれば21世紀中には新たな自然鉱山が基本的になくなる。人類は採掘という行為から解放され、(資源を)まわす時代を迎える」と指摘した。
このため、東京五輪大会では「都市鉱山からメダルを作り、競技場を鉄スクラップのリサイクル鋼材から作ることが21世紀の持続的社会を示す象徴になる。また、プロジェクトの総体として持続社会をレガシーとして遺すことが今大会の約束でもある」と語った。
「都市鉱山からメダル」プロジェクト/小池都知事「世界への大きなメッセージ」
同公開ブリーフィングを総括した小池百合子東京都知事は、今年4月に開始した「都市鉱山から作る!みんなのメダルプロジェクト」について「世界に対する非常に大きなメッセージになる」と述べ、日本の先進的なリサイクルの取り組みを世界にPRする機会としての意義を強調した。

東京都でも訪庁する世界各国の要人に対して、同国の大使館員が持っている使用済み携帯電話など小型家電を「メダル協力ボックス」に投入してもらうよう要請。自国の五輪選手が東京大会でメダルを獲得することによって、金や銀、銅などの資源が自国に戻る仕組みとなる。このため、東京五輪大会への応援に一段と熱が入るとの考えで「非常にメッセージ力のあるプロジェクトだ」と語った。
同プロジェクトは東京2020組織委員会が主催するもので、東京大会で贈られる約5千個のメダルを全国から集めた小型家電から抽出したリサイクル金属でつくる国民参加型の取り組み。9月1日時点で小型家電リサイクルを実施している自治体の約9割にあたる1136自治体が参加している。
2月から先行して回収を始めた東京都では8月末時点で約5万7千個の使用済み小型家電を回収。ただ、小池都知事は「まだまだ目標には届いていない」と語り、事業系の使用済み携帯電話を回収しやすくするため、マニフェストの扱いを若干変更するなどの対応を要請しているとした。

