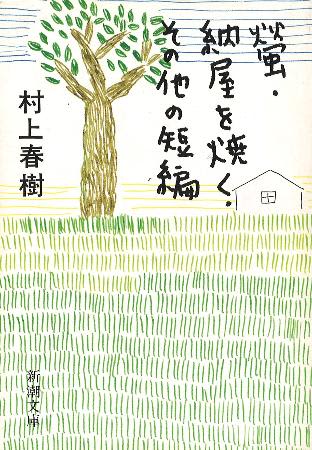
『騎士団長殺し』(2017年)では「免色渉」という人物が魅力的な存在で、作品をよく読んでいくと、「私」は「免色渉」が述べたことから、影響を受けて、「免色渉」の言葉が自分の心の姿に反映していったりします。そのことを、このコラム「村上春樹を読む」でも紹介してきました。
この「免色渉」は村上春樹が最も愛する作品、スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』で言えば、ジェイ・ギャツビーに相当する人物です。そのことは村上春樹自身が認めています。『みみずくは黄昏に飛びたつ 川上未映子訊く/村上春樹語る』(2017年)の中で「免色さんの造形も、ジェイ・ギャツビーのキャラクターがある程度入っています」と述べていましたし、その免色渉と小田原郊外で、谷を隔てて暮らす「私」は『グレート・ギャツビー』の語り手のニック・キャラウェイに相当しているようです。それはこのコラムでも紹介しましたので、興味がありましたらそちらを読んでください。
今回は『騎士団長殺し』の「免色渉」と「私」は、どこがどのように違うのかということを考えてみたいのです。結論をまず先に書いてしまえば、「私」は<恐怖と闘って、それを乗り越えていく人>だという点が「免色渉」との大きな違いです。後で詳しく紹介しますが、『騎士団長殺し』の中にそう記したところがあるのです。そこに至るまで、登場人物たちが、どのように「恐怖」と闘っているかということを記してみたいと思います。
☆
村上春樹作品の中で「恐怖」との闘いは心の内なる闘いです。例えば『騎士団長殺し』の「第2部 遷ろうメタファー編」で、「私」が自分の心の世界である地底を進んでいく場面があります。「私」が、まず地底にある「巨大な森」を進んで行きます。その「巨大な森」も、自分の心の中の森です。その森の中で「私」は「何かに向かって近づきつつある」のですが、いったい「それが善きものなのか、あるいは悪しきものなのか、知りようも」ありません。でも「善きものであるにせよ悪しきものであるせよ、その光が何であるかを自分の目で実際に見届けるしかない」と思って一歩一歩進んでいくと、やがて「森が急に終わった」のです。「森を抜け出せた」のです。
つまり、私たちが「巨大な森」を抜け出すには「自分の目で実際に見届ける」ということが大切なのです。たとえ善きものであるにせよ悪しきものであるせよ、それが「何であるかを自分の目で」しっかり見ることが大切なのです。そういう村上春樹の考えが記された場所です。「何であるかを自分の目で」しっかり見るという行為を通して、我々はその深い巨大な森から抜け出ることができるということを村上春樹は書いているのでしょう。
☆
でも「私」の地底の世界はそれで終わっていないのです。「森」を抜け出ると、次には「洞窟」が待っています。
行く手に「洞窟の入り口」が待ち構えていて「洞窟の中に足を踏み入れる以外に、私にとれる行動」はありません。そこに入る前に何度か深呼吸をして、できるだけ意識を立て直して、「私」はその洞窟の中に足を踏み入れていくのです。
そうすると洞窟の中で黄色い光がこぼれてくる方向があって、「私」がその方向に進んでいくと、それは岸壁に打ち付けられた太い釘に吊られた古風なカンテラの光でした。その中には太い蝋燭が燃えています。そして、そのカンテラの下には、身長60センチほどのドンナ・アンナが立っていたのです。
小説のタイトルとなった「騎士団長殺し」とは、モーツァルトのオペラ『ドン・ジョバンニ』の冒頭にある場面のことですが、その放蕩者ドン・ジョバンニは美しい娘、ドンナ・アンナを誘惑し、それを見とがめた父親の騎士団長と果たし合いになり、刺し殺してしまいます。つまりドンナ・アンナは、ドン・ジョバンニに殺害された騎士団長の娘です。
『騎士団長殺し』には、この洞窟の中での、ドンナ・アンナと「私」の「恐怖」をめぐる会話が記されています。
ドンナ・アンナが言うには、洞窟の左の隅の方に横穴の入り口があるそうです。それは狭い穴ですが「あなたはそこに入っていかなくてはなりません」とドンナ・アンナは「私」に告げます。さらに「あなたが昔から、暗くて狭いところに強い恐怖心を抱いていることは存知あげています。そういうところに入ると正常に呼吸ができなくなってしまう。そうですね?」と言います。つまり「私」は強い「閉所恐怖症」なのです。
「でもそれにもかかわらず、あなたはあえてその中に入っていかなくてはなりません。そうしなければ、あなたはあなたの求めているものを手に入れることができません」とドンナ・アンナは語るのです。
「私」はドンナ・アンナに問います。
「この横穴はどこに通じているのですか?」。それに対してドンナ・アンナは「それは私にもわかりません。行き先はあなたご自身が、あなたの意思が決定していくことです」と答えます。つまり、この洞窟の中を行く「私」も、自分の心の中を進んでいるのです。そのように考えれば、「行き先はあなたご自身が、あなたの意思が決定していくこと」というドンナ・アンナの言葉も受け取れると思います。
「でもぼくの意思には恐怖もまた含まれています」「ぼくにはそれが心配なのです。ぼくのその恐怖心がものごとをねじ曲げ、間違った方向に進めてしまうかもしれないことが」と「私」は語ります。でもドンナ・アンナは「繰り返すようですが、道を決めるのはあなたご自身です。そして何より、あなたはもう行くべき道を選んでしまっています。あなたは大きな犠牲を払ってこの世界にやって来て、舟に乗ってあの川を渡りました。後戻りはできません」と告げるのです。
こうやって、閉所恐怖症の「私」が狭い狭い穴を通り抜けていく場面が始まっています。
☆
その途中で、『騎士団長殺し』の中で「白いスバル・フォレスターの男」と呼ばれる男が「おまえがどこで何をしていたかおれにはちゃんとわかっているぞ」と声をかけます。その声に虚を突かれた「私」はひるみます。
「私」は妻と別れた後、車で東北を移動中、若い女に誘われて、ラブホテルに行き、その女に懇願されて、バスローブの紐で、女の首を絞めたのです。演技的な、プレイ的な行為でしたが、その行為の中に、実は人をも殺しかねない自分が存在していたのです。「おまえがどこで何をしていたかおれにはちゃんとわかっているぞ」という「白いスバル・フォレスターの男」の声は「私」のその行為のことを言っているのです。
でもその時、亡くなった妹のコミ(小径)の声が聞こえてきて、「懐かしく思うものを何か心に浮かべて」と話してきます。「さあ、何かを思い出して」「手で触れられるものを。すぐに絵に描けるようなものを」と言うのです。
そんな中を、「私」は進んでいくのです。「穴」は狭く、狭くなって、背後に何かが近づいてくる気配があります。
「私はそのざわざわという足音を聞き、不揃いな息づかいを感じ」ます。それは「私」のすぐ背後までやってきて、動きを止めて、沈黙します。息をひそめ、様子をうかがっているようでした。「それからぬめりのある冷ややかな何かが、私のむき出しの足首に触れた。それはどうやら長い触手であるようだった。形容のしようがない恐怖が私の背筋を這い上がった」と村上春樹は書いています。
でも「私」は、その身体が通れないほどの「狭い穴」の中を、あらゆる理性を捨て、渾身の力を込めて、身体をより狭い空間に向けて突き出していくのです。「たとえ身体中の関節をそっくり外さなくてはならなかったとしても。そこにどれほどの痛みがあろう。だってこの場所にあるすべては関連性の産物なのだ。絶対的なものは何ひとつない」と思って進んでいくのです。
「痛みだって何かのメタファーだ。この触手だって何かのメタファーだ。すべてが相対的なものなのだ。光は影であり、影は光なのだ。そのことを信じるしかない。そうじゃないか?」
「穴抜け」の最後に、そんな言葉が記されています。その言葉の後、改行されて「出し抜けに狭い穴が終わった」とあるのです。『騎士団長殺し』は、このようにして「恐怖を乗り越えていく」小説なのです。
☆
その「私」が「狭い穴」の中を進んでいた時、13歳の少女である「秋川まりえ」は「免色渉」の家の中に隠れています。自分の存在が「免色渉」に知られることなく、彼の家の中に隠れ潜んでいたのです。息を潜めてクローゼットの中に隠れていた時、その「秋川まりえ」のクローゼットの闇に誰かが近づいてきました。「激しい恐怖」が「秋川まりえ」を襲ってきます。
でも「どんなに恐ろしくても、恐怖に自分を支配させてはならない。無感覚になってはならない。考えを失ってはならない。だから彼女は目を見開き耳を澄ませ、その足先を睨みながら、ピンクのワンピースの柔らかい生地をすがるように強く握りしめていた」と村上春樹は書いています。
このまりえの護符のようにクローゼットの中にあるイフクは「免色渉」の愛人だった、まりえの母(スズメバチに刺されて急死しています)のものだと思われます。そして、その「イフクが私を護ってくれるのだ、と彼女は強く信じた」と記されています。そうやって「ただ沈黙を守り、不安と恐怖に耐えた」のです。
主人公の「私」は、恐怖に陥らず「自分の目で実際に見届けるしかない」と思う人間であり、「秋川まりえ」もまた恐怖に自分を支配させずに「目を見開き耳を澄ませ」る人間です。
そして「私」は「痛みだって何かのメタファーだ。この触手だって何かのメタファーだ。すべてが相対的なものなのだ。光は影であり、影は光なのだ。そのことを信じるしかない」というように「信じる」人です。「秋川まりえ」も「そのイフクが私を護ってくれるのだ、と彼女は強く信じた」というように「信じる」人間です。
そうやって「信じる」ことで、勇気をもって〈恐怖を越えていく〉人として、「私」と「秋川まりえ」は『騎士団長殺し』の中にあります。
☆
そして今回のコラム「村上春樹を読む」で最初に記したこと。『グレート・ギャツビー』で言えば、ジェイ・ギャツビーに相当する「免色渉」と、『グレート・ギャツビー』の語り手、ニック・キャラウェイに相当する「私」は、お互いに交流し合う人たちですが、でも2人は何が違うのか、どういう点で「免色渉」と「私」は違うのか、という点です。
そのことが『騎士団長殺し』の最後の最後に書かれています。長いのですが、それが今回紹介したいことの中心的な部分にかかわっていますので、引用してみましょう。
「でも私が免色のようになることはない。彼は、秋川まりえが自分の子供であるかもしれない、あるいはそうではないかもしれない、という可能性のバランスの上に自分の人生を成り立たせている。その二つの可能性を天秤にかけ、その終ることのない微妙な振幅の中に自己の存在意味を見いだそうとしている。しかし私にはそんな面倒な(少なくとも自然とは言い難い)企みに挑戦する必要はない。なぜなら私には信じる力が具わっているからだ。どのような狭くて暗い場所に入れられても、どのように荒ぶる曠野に身を置かれても、どこかに私を導いてくれるものがいると、私には率直に信じることができるからだ。それがあの小田原近郊、山頂の一軒家に住んでいる間に、いくつかの普通ではない体験を通して私が学び取ったものごとだった」
これが大長編『騎士団長殺し』の結論にあたる言葉です。この中で最も大切なものは「信じる」という言葉です。「私には信じる力が具わっている」という言葉の「信じる力」の部分には傍点を打って、村上春樹は表記しているのです。さらに「どこかに私を導いてくれるものがいると、私には率直に信じることができるからだ」という言葉もあって、この場面で「信じる」ことは2度も書かれています。
そして、この大長編『騎士団長殺し』の最後の言葉も「『騎士団長はほんとうにいたんだよ』と私はそばでぐっすり眠っているむろに向かって話しかけた。『きみはそれを信じた方がいい』」というものです。「むろ」は「私」の妻が産んだ子ですが、「信じる」ということが、どれだけこの『騎士団長殺し』という作品にとって、大切な言葉であるのか、よくわかると思います。
狭く、暗い「穴」を抜けながら、「私」は「すべてが相対的なものなのだ。光は影であり、影は光なのだ。そのことを信じるしかない」と思えた時、「出し抜けに狭い穴が終わった」のです。「秋川まりえ」も暗いクローゼットの中で「そのイフクが私を護ってくれるのだ、と彼女は強く信じた」という力で、恐怖を乗り越え、最終的に「免色渉」の家から脱出しています。
☆
「恐怖を越えていく」というテーマは、村上春樹の作品に一貫してあるものです。この連載コラム「村上春樹を読む」の中でも何回か、このテーマに関係した作品を紹介してきました。
例えば、連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』(2000年)のいくつかの短編には「恐怖を越える」ということがテーマになった作品があります。
同短編集の中の「かえるくん、東京を救う」という作品には「最高の善なる悟性とは、恐怖を持たぬことです」というニーチェの言葉が紹介されていますし、「真の恐怖とは人間が自らの想像力に対して抱く恐怖のことです」というジョセフ・コンラッドの言葉も記されています。
「片桐」という男は両親が既に亡くなり、弟と妹の面倒をみて大学を出してやり、結婚もさせていますが、自分には妻子もありません。自分が殺されても「誰も困らない」し、片桐自身「とくに困りもしない」と思っている人間です。そのため、片桐はその世界では、肝の据わった男としていささか名前を知られています。つまり片桐は「想像力に対して抱く恐怖」を持たない人間なのです。
ある日、帰宅すると、アパートの部屋に巨大な蛙(かえる)が待っていました。そのかえるは、東京直下型地震の原因である地下の暗闇の「みみずくんと闘うのは怖い」ので「あなたの勇気と正義が必要」と片桐に頼みます。そうやって、かえるくんと片桐が力を合わせて、地震を未然に防ぐという話です。「恐怖」を越えて、地震を防ぐのです。
表題作の「神の子どもたちはみな踊る」の主人公・善也にとっては、野球の試合で、たいていの外野フライを落球してしまうことが「恐怖」でした。その善也が小説の最後、ピッチャーズ・マウンドの上にのぼり、「踊るのも悪くないな」と思い、1人で踊り始めます。草のそよぎと雲の流れにあわせて踊るのです。
その踊りには「パターンがあり、ヴァリエーションがあり、即興性があった。リズムの裏側にリズムがあり、リズムの間に見えないリズムがあった」と記されていますし、その複雑な絡み合いは「様々な動物がだまし絵のように森の中にひそんでいた。中には見たこともないような恐ろしげな獣も混じっていた」と書かれています。
そして「でも恐怖はなかった。だってそれは僕自身の中にある森なのだ。僕自身をかたちづくっている森なのだ。僕自身が抱えている獣なのだ」と思うのです。これも「恐怖」を越えていく物語です。自分の心の中の「恐怖」を乗り越えていく話です。
☆
長編で言えば、『1Q84』(2009年―2010年)のハイライトの場面。それは女主人公で殺し屋である「青豆」が、カルト宗教団体の「リーダー」と呼ばれる男と対決して、ついに殺害する場面ですが、その前に「青豆」とリーダーとの長い対話があります。その時、リーダーは青豆に「怯えることはない」と語ります。
リーダーは「君は怯えている。かつてヴァチカンの人々が地動説を受け入れることを怯えたのと同じように。彼らにしたところで、天動説の無謬性を信じていたわけではない。地動説を受け入れることによってもたらされるであろう新しい状況に怯えただけだ。それにあわせて自らの意識を再編成しなくてはならないことに怯えただけだ」と言うのです。
我々が、もし今の世界を再編成することができるとしたら、それにともなって自分たちの意識も再編成しなくはならないのですが、でもそれは怖いことであり、「恐怖」なのです。自分の意識を再編成することは「恐怖」であり、そのことに、つい人は怯えてしまうのですが、そういうことに「怯えることはない」とリーダーは言っているのです。
ここにも「恐怖を越えていく」というテーマがよく表れていると思います。
『1Q84』という物語は小学校の同級生で、10歳の時に誰もいない放課後の教室で、1度だけ手を繋いだことのある「青豆」と「天吾」が、20年をかけて再会して結ばれる話です。物語の最後に「青豆」は、こんなことを思っています。
「私たちは論理が力を持たない危険な場所に足を踏み入れ、厳しい試練をくぐり抜けて互いを見つけ出し、そこを抜け出したのだ。辿り着いたところが旧来の世界であれ、更なる新しい世界であれ、何を怯えることがあるだろう。新たな試練がそこにあるのなら、もう一度乗り越えればいい。それだけのことだ。少なくとも私たちは孤独ではない」
ここに「恐怖を越えていく」という村上春樹の作品のテーマが、確認されるかのように記されています。
☆
でも「恐怖」というものは、具体的にどうあらわれ、どうしたら「恐怖を越えていける」でしょうか。
「私」が「狭い穴」の中を行く時、そのざわざわという足音と不揃いな息づかいで背後までやってくるものがあります。ぬめりのある冷ややかな何か、長い触手のようなものが、「私」の足首に触れます。「形容のしようがない恐怖」です。
でも、その「恐怖」というものは「関連性の産物」なのです。「絶対的なものは何ひとつない」のです。「関連性の産物」ということは、意識の世界のものです。「人間が自らの想像力に対して抱く恐怖」なのです。
「私」は「痛みだって何かのメタファーだ。この触手だって何かのメタファーだ。すべてが相対的なものなのだ。光は影であり、影は光なのだ。そのことを信じるしかない」と思い、そして、それを信じると「狭い穴」は終わっているのです。
今までも「恐怖を越えていく」ということを村上春樹は書いてきました。でも『騎士団長殺し』では、その恐怖を越えていく力として「信じることの力」というものが、強く、はっきりと具体的に書かれているのです。
混乱する21世紀を生きる人々に向けて、自分もその時代を生きる1人として、「信じる力」を通して、この世界を再構成したいという思いが託された物語なのだと思います。
☆
最後に「私」が「狭い穴」を脱出できる考え、つまり「痛みだって何かのメタファーだ。この触手だって何かのメタファーだ。すべてが相対的なものなのだ。光は影であり、影は光なのだ。そのことを信じるしかない。そうじゃないか?」という言葉の「痛みだって何かのメタファーだ」の部分について、書いておきたいと思います。
「身体的な痛みが、何かのメタファーだ」とは、どんなことを意味しているのかについて考えてみたいのです。
これは、おそらく、「めくらやなぎと眠る女」(「文學界」1983年12月号)の中に記された「それに恐いんだよ、本当はね。痛いのが嫌(いや)なんだ。本当の痛みより、痛みを想像することの方がつらいんだよ。そういうのってわかる?」という言葉に対応したものではないでしょうか。わたし(小山)は、そのように考えてます。
「めくらやなぎと眠る女」は、久しぶりに帰郷した「僕」が、右の耳が悪い10歳以上年下のいとこの病院通いに付き添っていき、そのバスの往路でのことや、いとこの診療を待つ間に、昔、友だちと一緒に病院に入院していた、その友だちのガールフレンドを見舞いに行った日のことを思い出す話です。
バスの中で、いとこが「耳のお医者にかかったことある?」と訊ねます。そこで僕は「これまでのやつはずいぶん痛かったの?」と聞くのです。「そんなでもない」「でもね、そりゃ痛いときもあるよ。いろんなものつっこんでみたりさ、洗滌したりさ。たまにだけどね」という、いとこの言葉があって、その後に「それに恐いんだよ、本当はね。痛いのが嫌(いや)なんだ。本当の痛みより、痛みを想像することの方がつらいんだよ」という言葉が記されているのです。
この「めくらやなぎと眠る女」は長い版と、それを4割ほど削減した短い版がある作品として知られています。紹介したのは長い版で『螢・納屋を焼く・その他の短編』(1984年)に収録されています。短い版は「めくらやなぎと、眠る女」(「文学界」1995年11月号)というタイトルで『レキシントンの幽霊』(1996年)に収録されています。
短い版では、いとこと僕の耳の痛みに関する会話は「いちばん辛いのは、怖いことなんだよ。実際の痛みより、やってくるかもしれない痛みを想像する方がずっと嫌だし、怖いんだ。そういうのってわかる?」と書かれています。
長い版では「それに恐いんだよ」と記されていた言葉が、短い版では「怖いことなんだよ」と漢字も変わり、さらにもう一度「怖いんだ」と記されています。長い版の「恐」と短い版の「怖」を合わせると「恐怖」となるような直しとも言えますね。
☆
この短い版の「めくらやなぎと、眠る女」は1995年の阪神大震災後、神戸で開かれた村上春樹の朗読会のために、生まれた作品として知られています。朗読用に短くしたようですが、両方のバージョンの作品をそれぞれの短編集の中に収めているのです。
村上春樹は日本ではめったに朗読会などをしない作家として知られていますが、自分が育った地が阪神大震災に襲われ、その地の人々を励まし、再生のための力になりたいという思いが強くあったのでしょう。この作品は村上春樹が育った土地が舞台となっています。
細かく記すと繁雑になるので略したいと思いますが、紹介した言葉の前後を読むと、長い版「めくらやなぎと眠る女」よりも、短い版「めくらやなぎと、眠る女」のほうが「自らの想像力に対して抱く恐怖」という面が明確に書かれていることが分かります。
そして、長い版の発表は1983年、なんと34年前のことです。そこから、ずっと村上春樹は「恐怖を越えていく」ことを自分のテーマとして考え続けてきたのでしょう。
「痛みだって何かのメタファーだ。この触手だって何かのメタファーだ。すべてが相対的なものなのだ。光は影であり、影は光なのだ。そのことを信じるしかない。そうじゃないか?」
『騎士団長殺し』で「狭い穴」を抜け出す時に「痛みだって何かのメタファーだ」という言葉を記した際、おそらく村上春樹の心の中には、1985年の阪神大震災後の神戸で、自分が育った土地の再生を願って開いた朗読会への思いがあったのではないかと思います。そして、今、混乱する世界の再生を願う気持ちが、きっとあっただろうと思います。(共同通信編集委員 小山鉄郎)
******************************************************************************
「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓
