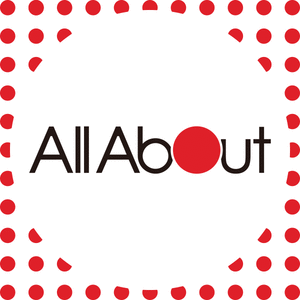若い方には馴染みがないかもしれませんが、以前はよく縁日などで「カラーひよこ」を見かけました。単に「ひよこ」をカラースプレーなどで色付けしたもので、動物愛護の観点などから最近では見かけることはありません。
一方、医療の世界では「染料」が薬として使用されていた時代があり、副作用で「カラーひよこ」のように体の色が"青"や"赤"に変化していたという時代もあったというから驚きです。
「合成染料」が治療に有効?
19世紀半ばには、照明用のエネルギーとして「石炭ガス」が多く使われていました。その石炭ガスを生成する際にできる副産物がコールタールで、当初は厄介者扱いされていました。ですが、精製すると、染料、医薬品、プラスチックなどの原料になることが分かり、これをもとにドイツでは合成染料が主要産業となったのです。
ドイツの細菌学者・生化学者であったパウル・エールリッヒは、細菌を染めるのに染料を使っていました。あるとき染料が神経線維まで染めているのに気が付き、合成染料が神経伝達に何らかの作用があるのではないかと考えたのです。
染料だけに、投与すると体の色が……
1891年、マラリア原虫がメチレンブルーでよく染まるという観察から、軽いマラリアにかかっていたドイツ人水兵にこの染料を投与したところ、効果があったのです。
この色素は熱帯でかかる重症型のマラリアには効果がないということが後に判明したものの、合成した化合物がある特定の病気にうまく作用するということが初めて証明されたのでした。
ただし、メチレンブルーは青い色素の染料なので、体を“真っ青”に染めてしまうことがあるという問題点もありました。
化学物質から梅毒の薬
エールリッヒは、「ある色素は選択的に細菌や原生動物を染めるものだから、病原体に選択的に吸着し、宿主に害を及ぼさずに病原体だけを殺す物質ができる」という考えをもとに研究を続けます。
当時猛威を放っていた梅毒に対して、とある論文をもとに「梅毒にはヒ素化合物が有効」という仮説をたてます。そして、日本の細菌学者・秦佐八郎と共に数多くの合成されたヒ素化合物で動物実験を行った結果、606番目の化合物で見事成功するのです。これが梅毒治療薬「サンバルサン」の誕生です。この薬は1940年代にペニシリンが登場するまで、梅毒に対しての唯一の薬として活躍しました。
エールリッヒのこの発見は後のサルファ剤・ペニシリンの発見をうながしたという点で非常に功績が大きいとされています。この研究により、1908年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。
赤い色素の染料が医薬品へ
エールリッヒの発見の後、化合物から有効な薬が作られることが期待され、染料を含む数多くの化合物が主要な感染症に対して実験されたのですが、すべて失敗に終わります。化学物質から次の有効な医薬品が作られるまで、それから20年以上も待たなければなりませんでした。
1932年、ドイツの病理学者・細菌学者であるゲルハルト・ドーマクは、革を染めるときに用いる赤い色素プロントジルが連鎖球菌に有効だということを発見します。
自分の娘に「染料」を用いて病気が完治
運命のねじれか、自分の6歳の娘がその数か月後に連鎖球菌感染を起こしてしまいます。ほかの治療が効果のないなか、実験用薬物の赤色プロントジルを投与し、無事に完治することに成功します。ただし、肌が“ゆであがったロブスター色に染まる”という副作用は永久に消えることがありませんでした。
ゲルハルト・ドーマクも、この成果により1947年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。
体が染まらない薬の開発
その後の研究により、抗菌作用が「染料」でなく「スルファニルアミド」という物質にあるということが判明。この成分を利用した「サルファ剤」が作られるようになりました。新薬の開発により、患者が真っ赤なロブスター色に染まるという副作用もなくなり、抗菌活性も高いサルファ剤が開発され多くの命を救うこととなりました。
その後、カビから「ペニシリン」が開発、感染症に対してさらなる医学の発展を遂げていくこととなります。何気なく使っている薬にも、先人のさまざまな苦労が隠されているのですね。