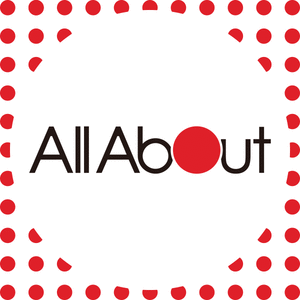待機児童数は、増えている?
待機児童を減らそう、なくそう、と各自治体の取り組みが続いていますが、相変わらず待機児童が増えているのが現状です。厚生労働省によると、平成29年4月の待機児童数は、26,081人で、平成28年(23,553人)より2,528人増えています。
一方、保育所等を利用している児童は、約255万人で、平成28年より約8万8千人増加しているとのこと。保育所等を増やしてはいるけれども、利用を希望する人も増えているので、結果的に待機児童が増えてしまっている状況です。認可外保育園などを利用して、なんとか預け先を見つけられれば良いのですが、なかには退職を考える方もいらっしゃるかもしれません。
育児休業給付金が最長2歳まで受け取れることに!
2017年10月から育児・介護休業法が改正され、所定の理由がある場合は、子どもが2歳になるまで、育児休業給付金を受け取ることができるようになりました。育児休業給付金は、原則は、「1歳に達する日の前(誕生日の前日)までの子どもを養育するために育児休業を取得した場合」に支給されるものです。
改正前は、預けられる保育園が見つからない場合などの理由がある場合、半年間(子どもが1歳6か月に達する日前まで)延長して、育児休業給付金を受け取ることができました。けれども、子どもが生まれた月によっては、保育園に空きが出にくく、なかなか保育園が見つからないというケースもあります。
今回の改正では、そのような場合、さらに6か月(子どもが2歳に達する日前まで)延長することができ、育児休業給付金も2歳まで受け取れるようになりました。これなら、「保育園の募集が多い時期まで育児休業を取り、保育園が決まってから職場復帰する」という可能性が拡がります。
子の看護休暇は、半日単位で取得可能に
すでに平成29年1月から改正されていますが、「子の看護休暇」を半日(所定労働時間の2分の1)単位で取ることができるようになりました。看護休暇は、小学校就学前の子どもを養育する労働者が、1年に5日(子どもが2人以上の場合は10日)まで、病気やけがをした子どもの看護や、子どもに予防接種や健康診断を受けさせるために使うことができます(日々雇用される方は除く)。
予防接種や健康診断の付き添いの場合は、半日で足りることも多いので、残った半日を別の機会に使うことができるのは助かると思います。
有期契約労働者も育児休業や看護休暇を取れる
育児休業などは、正社員の方だけが取れると思われがちですが、パートや派遣社員、契約社員など、いわゆる有期契約で働いている方でも、一定の範囲の方は、育児休業を取ることができます。一定の範囲とは、以下の2つを満たす方です。
(1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
(2)子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合は、更新後の契約)期間が満了することが明らかでないこと
1歳以降の育児休業については、1歳に達する時点で保育園に入れないなど、特別な事情がある場合は、上記(1)(2)の要件を満たせば1歳6か月に達する日まで育児休業を延長することができます。また、10月の改正により、2歳に達する日までさらに延長することも可能です。その場合、上記(2)は、「子が2歳に達する日までに労働契約期間が満了することが明らかでないこと」となります。
このほか、週の勤務日数や勤続期間など、一定の条件を満たしていれば、子の看護休暇や短時間勤務制度も利用することができます。企業によって、国の基準以上の制度がある場合もあります。パートなどで働いていらっしゃる方は、まずはご自分が利用できる育児支援制度について、勤務先などに聞いてみることをお勧めします。
育児休業、いつまで取得する?
育児休業が条件によっては最長2年まで取得できるようになりましたが、考えなくてはならないのが、キャリアと家計の面です。以前、ガイド平野のところに家計相談にいらした方が、「SE(システムエンジニア)の仕事は、技術の進歩が目まぐるしいので、職場から離れたらスキルが追い付かなくなるんです。体調次第だけど、出産後は、できる限り早く復帰したい。」と話されていました。
一方、家計面で見ると、育児休業中の収入は、当初6か月は、休業開始時の賃金月額の67%で、6か月経過後は、50%になります。育児休業後、フルタイムで復帰する場合は比較的早い期間で、出産前の収入に戻りますが、短時間勤務をする場合、おおよそ70%くらいの収入になることが多いです。夫婦でライフプランを作って、将来やりたいことや希望する教育費、住居費が賄えるかどうか、シミュレーションをしてみることをお勧めします。
子育てしながら共働きしやすい環境をつくる!
「子どもとの時間は大切にしたい。けれども自分たちのスキルや将来の希望を叶えるために、共働きは続けたい」というご夫婦は多いです。子育て・暮らし・仕事・家計(ワークライフ&マネーバランス)を大切にするために、「保育園に入れやすい自治体にマイホームを買った」「通勤時間が短い駅や駅から近い住宅に住み替えた」という方も多くいらっしゃいます。今住んでいるところが子育てをしながら働きやすい環境かどうか、改めてチェックしてみてもよいと思います。
また、家事の負担を軽くする家電や家事代行サービスなどにも予算を取り、家の中でも共働きしやすい環境づくりをしている方も増えてきました。国や企業の制度がさらに良くなることを願いつつ、ご夫婦でできることもぜひ取り入れて、子育てしながら共働きできる環境にしていただけたらと思います。