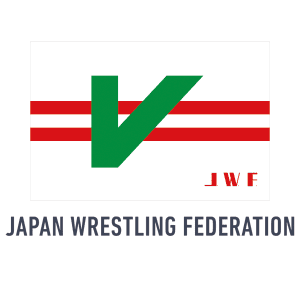(文・撮影=増渕由気子)

福岡大が2季ぶり27度目の優勝を飾った今年の西日本学生秋季リーグ戦。今大会、同連盟は新しい試みを二つ実行した。一つは、一部リーグを8チームの総当たり戦にし、これまでの「2グループの予選リーグ~順位決定戦」の形式から変更した。
西日本学生リーグ戦は、東は岐阜、西は九州と幅広い地域の大学が一堂に会して試合を行うため、関係者の気持ちとして、「せっかく集まるのだったら、もっと試合をして西日本のレベル向上につなげたい」という想いがあった。
これまでは4チームとしか試合ができなかったが、全チーム(7チーム)と対戦できることで組み合わせの運などがなくなり、結果が明瞭になるというメリットもある。これまでと同じ日程で運営をやりくりする方法を思案し、5月の春季リーグ戦では、試合方式は変えずにマット3面での運営を行い、審判の人繰りなどをテスト。満を持して、今大会の一部総当たり戦に臨んだ。

大会運営に携わった西日本学生連盟の福川敦理事長は、「試合数が大幅に増えましたが、運営に関してトラブルやアクシデントは特になく、予定どおりに行うことができました」と大会を成功に収めたことを評価した。各大学からも、試合が約2倍になったことで、選手の活躍の場が増えたことを好意的に捉える指導者が多かった。
日本文理大の湯元健一監督は「(試合数が増えたことで)選手の疲労に配慮しなければならないが、試合が増えた分、多くの選手を起用することができたので、この方式はよかった」と振り返った。
この試合形式を継続するかどうかは未定。福川理事長は「来季の継続の可否は来春の理事会で決める」と話した。
もう一つ、今大会は試合をインターネットで生配信を行ったこと。動画配信はネット回線や機材などの費用がネックになってくるが、テストケースとして、費用をかけずに手元にある機材やネットワークで行った。
同連盟の漆原功二広報担当は「今回、ゲリラ的にやれる範囲で中継を行ったが、回線もパンクせずに配信することができた。画質は及第点だが、もっと向上する必要があるが、学生主体でできることを研究して、今後も続けていきたい」と話した。