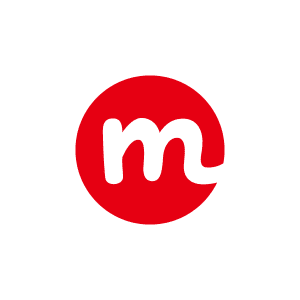アラビアと聞くと、童謡「月の沙漠」の世界が頭に浮かぶ。ヒトコブラクダに乗ってはるかな道をゆく旅人たち。古代からアラビア半島には交易路が張り巡らされ、人やモノ、文明が行き交った。東京国立博物館表慶館(東京都台東区)で開催中の「アラビアの道」は、サウジアラビアで発掘された考古遺物など約420件を通してその歴史と文化をひもとく展覧会。日本で同国の文化財を本格的に紹介するのは初めてという。(黒沢綾子)
改めてアラビア半島の位置を確認すると、西は紅海をはさんでエジプト、東はイラクなどに接している。つまり古代文明が花咲いたメソポタミアとエジプトに挟まれた地域。さらに俯瞰(ふかん)すると、地中海世界とアフリカ、インドなど南アジアを結ぶ要地だとわかる。
同展入り口で来場者を迎えるのは、今からざっと5000年前、移牧民や遊牧民が砂漠に残した人形(ひとがた)石柱だ。墓や祭祀(さいし)の場にあったものだろう、素朴な造形だが精神性を感じさせる。