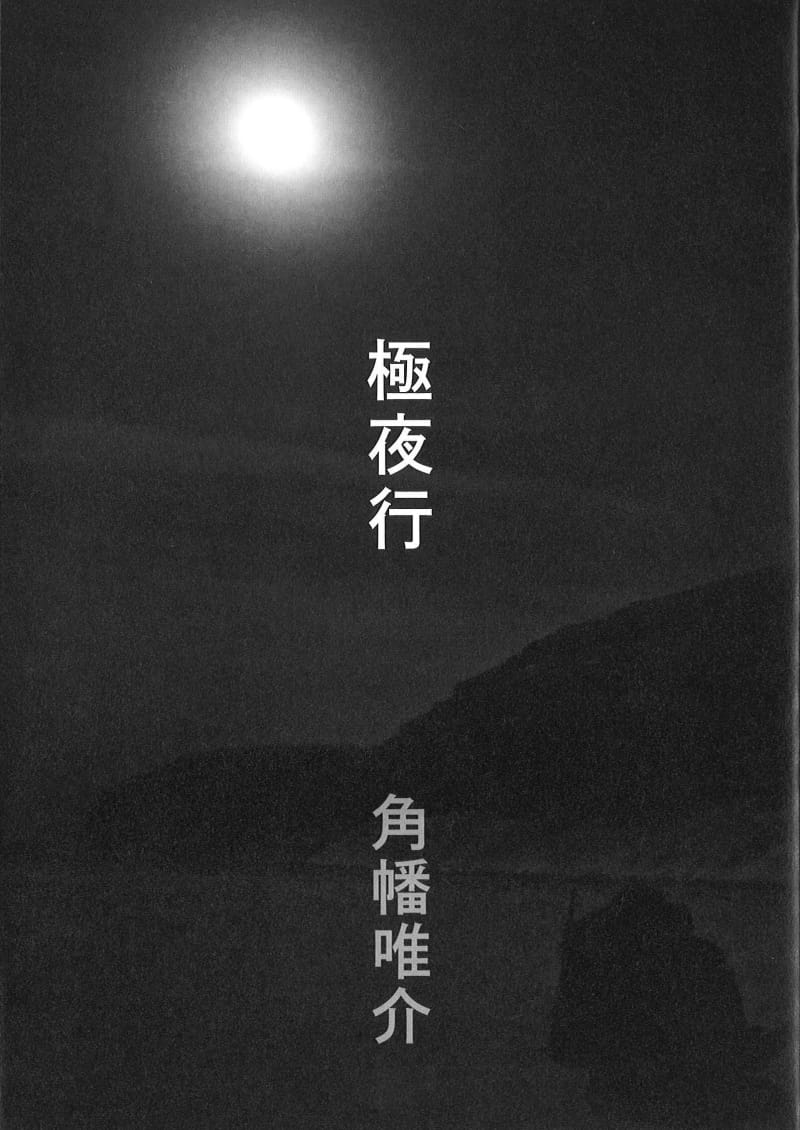
白夜は北極点に近いエリアで起きる、一日中太陽が沈まず“昼間”が続く現象として有名だが、その反対の極夜についてはあまり語られることはない。一日中太陽が昇らず、四ヶ月間もずっと(場所によってはさらに長く)“夜”のままであるという極夜を旅するというのが、探検家である著者が選んだ探検なのである。
その目的とは真の闇を経験すること、そして長い夜の果てに地上に顔を出す「本物の太陽」を見ること。人工的な照明やエネルギーに依存している現代社会を生きる我々は、「本物の太陽」を喪って久しいと著者は語る。
「日々の生活が自然と直に結びついていた時代」には、太陽が「人間の実存に関わる本質的な力をもって降り注いでいた」はずで、その頃のような「本物の太陽」を是非見てみたいと言うのだ。それを目の前にした時、何を感じるのかが知りたいのだと。
探検の相棒は一匹の犬のみ。二台の橇に食料や燃料を積み込んで、著者と犬はグリーンランドにあるイヌイットが住む最北端の村を、さらに北に向かって出発。氷床(氷河の塊)の上を進みながら、人はおろか植物も存在し得ない極寒かつ真っ暗闇の中を進んでいく。しかもGPSは使わず、地図とコンパスと星で位置を確認しながら。
雪の中にテントごと埋められそうになったり、ブリザードに吹き飛ばされそうになったり、マイナス四十度、五十度で凍えそうになったりと、危険や困難は次から次へとやってくる。狼や北極熊の気配に怯えながら歩き、食料が尽きて餓死する恐怖にも襲われる。そもそも危険や困難だらけの場所に足を踏み入れているのであって、何かを一つ間違えばすなわち死という世界なのだ。それらを著者がどうやって切り抜けていったのかは本書の大きな読みどころである。
そしてさらに特筆すべきは、終始ユーモアを忘れない軽妙な語り口だ。命の危機的場面を描写しているにもかかわらず、著者の筆致はそれをドラマティックに修飾する方へは向かわず、危機の中に潜んでいる滑稽な部分をありのままに描く。もちろん読者へのサービスという意味合いもあるのだろうが、命が危ぶまれるような場所でも、人というものはどこか滑稽で愚かなものであるという一つの本質が垣間見えるようで興味深い。
そして極夜が明け、「本物の太陽」を前にした時、著者は何を思うのか?
冒頭に描かれた著者の妻の出産シーンと見事に繋がり、まさに地球規模の大きくて美しい円を見せられたようで感嘆した。
(文藝春秋 1750円+税)=日野淳

