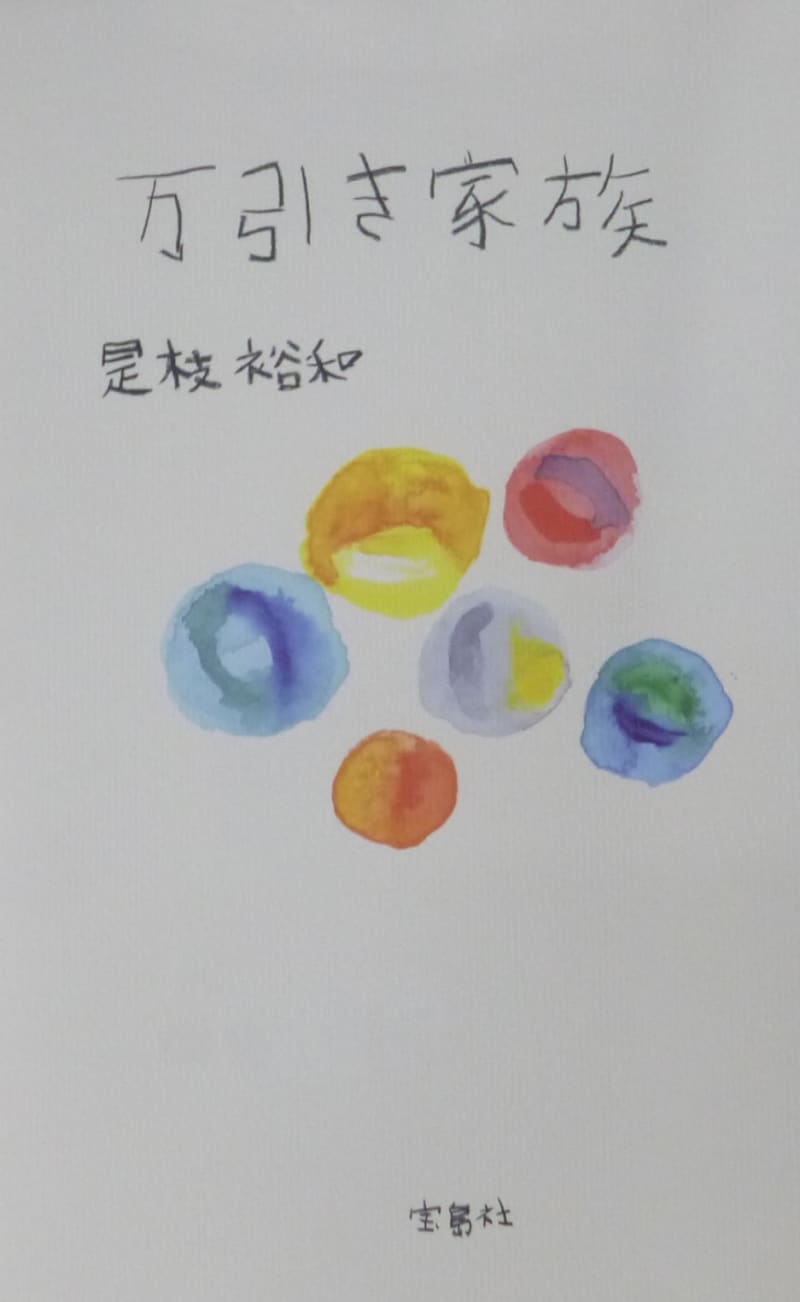
第71回カンヌ国際映画祭で最高賞の「パルムドール」を日本映画としては21年ぶりに受賞した是枝裕和監督の「万引き家族」。樹木希林さん演じるおばあちゃんの家に住む父役のリリー・フランキーさん(治)、母役の安藤サクラさん(信代)ら5人(後に6人)の疑似家族が、おばあちゃんの年金を頼りに、子どもにも万引をさせながら、都会の片隅でひっそりと暮らす姿を描いた作品で、6月に日本で公開されて以来、興行収入は是枝監督作品の過去最高を更新するなど、注目を集め続けている。
映画人気もさることながら、合わせて人気なのは、公開に先駆け発売されたノベライズ本だ。7月中旬までに14万部が発行されたという。監督自らが書き下ろし、映画には描かれていない部分もあり、映画と本を合わせて楽しむ人も多いそうだ。ならば!とさっそく映画を見に行き、本を読んでその違いを感じてみることにした。
先に映画を見た。印象に残ったのは、俳優たちの演技だ。特に、審査委員長の俳優ケイト・ブランシェットさんが絶賛したという安藤さんの「泣き」の演技は、ただ悲しいだけじゃなく、泣きたくもないのに泣いてしまったり、悔しかったり、みじめだったり…いろんな感情が交じり合っているのだろう気持ちが伝わってきて、自分も顔がくしゃくしゃになってしまった。松岡茉優さん(亜紀)の陰のある表情のカットも思わずぞくっとした。ストーリーが進むに従って、徐々に明らかになっていく“一家”の秘密。それでもわからないことがあった。子ども2人が一緒に住むようになった理由はそうだけれど、じゃあ、大人4人はなぜ?
それを知りたい一心で一気に読み進めた本。明かしてしまうのは気が引けるので、どんなエピソードかは割愛する。本を読んでいて、映画に出てくるシーンが書かれた部分になると、常に映画シーンが思い浮かんだ。信代の泣く顔、一家を温かく見つめるおばあちゃんの表情―。そこに本にだけある背景や心理描写を自分で付け足した、私編集バージョンの映画「万引き家族」が頭の中で上映される。解釈の余白が大きかったオリジナルよりさらに、具体的な解釈が加わって、ダイレクトな感動が増す。信代と治はこんなにも母、父と呼ばれたかったのか、亜紀はこんなにも居場所を求めていたのか―。映画のシーン一つ一つで見た、登場人物たちの表情の裏にある機微に触れた気がした。
この一家は、世間からは認められない家族だ。もちろん、子ども2人が加わった理由は現実社会でも許されるものではないだろう。だけど、それを「悪いことだ」と言い切ることは少なくとも感情の面ではとてもできなかった。「誰かが捨てたのを拾ったんです」。信代のせりふが重く心に響いた。
1人が1人を呼び寄せて、「みんな」になった。本で明かされる登場人物たちの背景。映画でも本でも、結局一家はばらばらになってしまう。「家族=結婚して、子どもが生まれて、年老いた親を呼び寄せて同居するようになって…」みたいな、そんな形が世の中のほとんどを占めている「家族」なのかもしれない。この作品で描かれる家族は、大多数に受け入れられる形ではなくても、何となく寄り添うようになって、同じご飯を食べて生活し、いたわり、支え合っていく。伝わってくる絆は、家族の成り立ちそのものなのではないだろうか。
人には人、あの家にはあの家のやり方や生き方がある。だけど、何でも良いよと言われると、かえって窮屈になる気もする。多分、これが王道、という絶対的な尺度がぶれるからだ。法律で確約された関係、血縁に裏打ちされている関係であれば、それはその点で揺るぎがない。だからこそ、選択肢が増えれば増えるほど、それらに依拠しようとする気持ち、形にこだわる風潮が増すのかもしれない。治がお父さんと呼ばれたがったのも、亜紀が、結局は大好きなおばあちゃんを疑ってしまったのも、もしかしたら、形になっていないことへの不安が、根底ではぬぐい切れていなかったからかもしれない。
美術館などで、音声ガイドを借りて展示作品を見て回ることがある。解説してもらうと、より深く知ることができたり、新たな視点で作品を鑑賞できたりするからだ。「万引き家族」も、それと同じような感覚で映画(展示作品)と本(音声ガイド)で楽しんだ。もちろん片方だけでも楽しめる。だけど、自分の見方とは違う本のガイドがあり、見たまま楽しめる魅力もあるけれど、よりかみ砕いて作品に触れることができた。本を併せ読むのは初めてだったけれど、これから映画を見るときは「これはありだな」と開眼した。(萩原里香・共同通信文化部記者)

