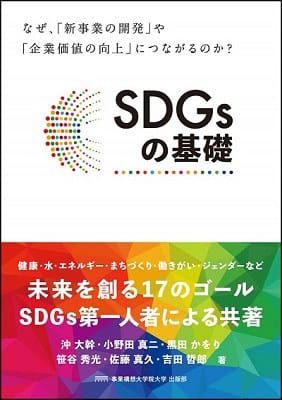
事業構想大学院大学出版部はこのほど、書籍『SDGsの基礎』を発刊した。SDGsに深く関わる6人が執筆、理解の一助となる入門書。副題に「なぜ、『新事業の開発』や『企業価値の向上』につながるのか?」を掲げ、採択された背景、企業の実践とその課題などを盛り込む。国連の沖大幹(おき・たいかん)事務次長補は最終章で、SDGsを積極的に活用し、企業が「国際社会の『観客』から『選手』へ」変わることを提唱した。(瀬戸内千代)
著者は、国際連合大学上級副学長でもある沖氏のほか、地球環境戦略研究機関(IGES)持続可能性ガバナンスセンターの吉田哲郎リサーチ・マネージャーと小野田真二研究員、伊藤園の笹谷秀光顧問、東京都市大学環境学部の佐藤真久教授、CSOネットワークの黒田かをり事務局長兼理事など、SDGsの立案や普及に関わってきた面々である。
先行企業を紹介した章では、オランダの石炭公社から転じて全事業でSDGsに配慮するグローバルな化学会社となったDSM社や、SDGsの複数のゴールを同時に満たす「PaperLab(ペーパーラボ)」を開発したセイコーエプソンなどを例に挙げ、SDGsを本業化する必要性をまとめた。
笹谷氏は、SDGsは特に「共通言語として使用し、取引先やNGO/NPOなどと目的を共有する」点で企業経営に有効であり、社員のモチベーション向上や優秀な人材の確保にも役立つと述べた。
佐藤氏は、MDGsとSDGsが完成した時代背景の差異に着目し、「SDGsは15年後に現在とは全く別の変化した未来を求める目標であり、発想の転換が必要」と強調した。
沖氏は、企業に問題解決型から「目標追求型」への移行を求めつつ、見せかけの取り組み(SDGsウォッシュ)に陥る危険性も指摘した。
また、日本企業が国際的な基準づくりの場に積極的に参画し、次世代に希望を伝えることの大切さにも触れた。
巻末にはSDGsの17個の目標の細かなターゲットや指標を日英2か国語で掲載。タイトル通りSDGsを基礎から伝える1冊となっている。

