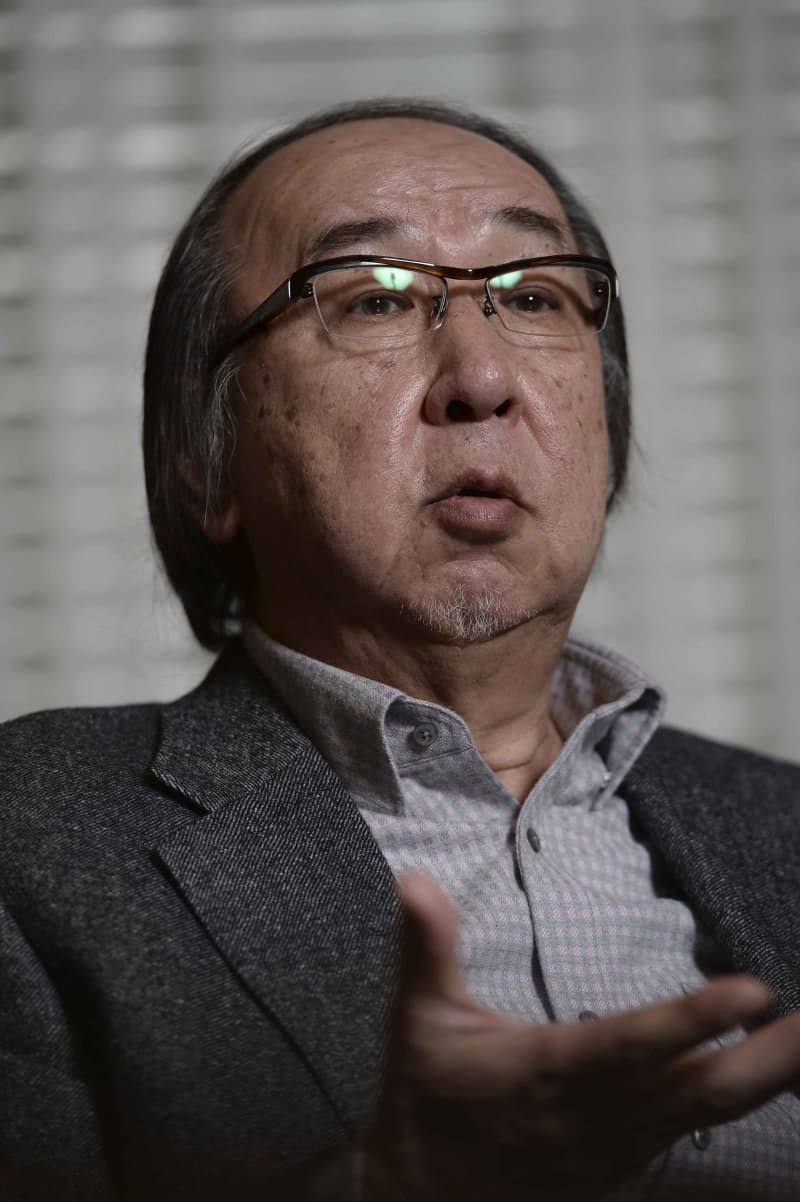
作家の横山秀夫さんが、長編小説『ノースライト』(新潮社)を出版した。英国推理作家協会賞の翻訳部門(インターナショナル・ダガー賞)の最終候補にもなった警察小説の傑作『64(ロクヨン)』の出版から6年4カ月。満を持して世に問う新作は、一級建築士を主人公に据えた建築を巡るミステリーだ。新たな地平を開いた横山さん。新作への思いと、作家として、人間としての歩みを聞いた。 (共同通信=田村文)
▽献辞に込められた思い
Q 『64』から6年ぶりのインタビューですね。
A あの時も「こんなに時間がかかってしまって、お恥ずかしい」と言いましたが、また同じことを言わなくちゃならない。いったい何を職業にしている人間なのか分からなくなってきちゃいました。「書き直し業、時々作家」とか…(笑)。
Q 「木村由花さんに捧げる」という献辞を見て胸を突かれました。雑誌「旅」の復刊時の編集長で、2015年に亡くなった木村さんのふんわりとした笑顔を思い出します。『ノースライト』は初め、「旅」に連載したんですね。
A 木村さんから連載の依頼をされ、ずっと伴走していただいたんです。『64』が終わって、次は『ノースライト』を本にしようという時にも、木村さんが来てくれて。
Q 「旅」の連載は2004年5月号からなので、単行本出版までに15年。連載時とは全然違うものになったのですか。
A 残っているのは1割もないと思う。全面改稿です。連載時は本当にきつかったんです。2003年1月に心筋梗塞で倒れて、心身ともにしんどくて…。出来上がってみたら満足できるものになっていなかった。それで先に『64』をやることにしたんだけれど、それも思いのほか長くかかってしまった。『64』が終わってすぐに『ノースライト』の書籍化に取りかかったのですが、それから6年。途方もない時間を費やした感じもするけれど、一瞬のような気もします。ひどいスランプで、座っているだけで何も書けないという時もありましたが、基本的には毎日書いていたんですよ。例えば、主人公の青瀬稔が別れて暮らす娘のことを思うシーンは30パターンぐらい書いた。何回書いても、もっと適切な書き方があるような気がして…。でも、いつもなら、本にする価値がないと思ったら「捨てる」という選択肢がありますが、今回は違った。木村さんが亡くなったことで、この本は絶対に出さなければならない特別なものになった。従来は書き終わるまでは見せない担当編集者にも、月に1度は会って、原稿を読んでもらいました。
Q 木村さんとの関係性は、この作品全体に影響を及ぼしている気がします。
A そうかもしれません。本来、小説とは生きることと死ぬことを書くものだから。身近な人の死が影響しないはずがないんです。
――主人公の青瀬稔は、施主から「あなた自身が住みたい家を建てて下さい」という依頼を受け、信濃追分に「木の家」を建てる。北からの光(ノースライト)を取り込んだ「Y邸」は、「平成すまい二〇〇選」に選ばれる。しかし施主への引き渡し後、そのY邸に電話しても誰も出ない。足を運ぶとそこは空き家で、建築家ブルーノ・タウトの椅子だけが残されていた。

▽「家」と「建築」と「旅」がピピッと
Q 『ノースライト』はたくさんのことに挑戦した作品だと思います。建築の世界が書きたかったのですか。
A 最初にあったのは、自分自身の閉塞感です。心筋梗塞で倒れた後も、仕事場から全く出られない状態が続いた。病気になる前より書くのが遅くなったので、家にも帰らず、ただひたすら書いていた。来月も再来月も、来年の仕事まで入っていて、ベランダから飛び降りちゃおうかと思ったこともあるぐらいです。そこに木村さんが来て、「旅」を復刊するから、松本清張さんの『点と線』を超えるようなものを書いてほしいと。ふふっと笑ってそう言った。受けられるような状態じゃなかった。でも「旅」だし、『点と線』という言葉も耳に入って、ふ~っと光を感じた。ああ、自分もここから飛び出して、旅に出てみたいな、と。
Q 主人公を建築士にしたのはなぜですか。
A 住むってどういうことなんだろう、なぜ自分はこの狭い仕事場にいるんだろうという問いがあったんですよね。そんな時、子どもの頃に「渡り」をしていた建築家がいるという話を耳にしました。
Q 青瀬の父はダム建築に関わる型枠職人で、青瀬も飯場から飯場へと転居を繰り返した。それを「渡り」と呼んだわけですね。
A 辞書にもある言葉ですが、まあ、ここでの使い方は小説的な造語です。その建築家に会って話を聞くうちに、頭の中で「家」と「建築」と「旅」がピピッとつながった。ただ、彼が「渡り」の経験をどう感受し、その後の人生にどんな影響を及ぼしたかは聞かなかった。人間形成の部分まで聞いたら、自由に想像できなくなってしまうから。
Q でも建築士のイロハは、聞かないと分からないでしょう。
A それはちゃんと聞きましたよ。他の建築士にも取材をしたり、雑談したりして学びました。雑談が大事なんです。いろんな建築士と雑談していると、みなさん自虐的な話もするんだけれども、どこかで「自分は他の人とは違う」という強い自負心を持っていることが分かる。
Q 青瀬は建築家ではなく建築士。そこにはこだわりがあったのですか。
A ありました。それは私が、派手な一線の刑事ではなく、警察の管理部門の人間を書き続けてきたことに通じるかもしれません。建築士のプライドはあるけれど、建築家と名乗ることにはためらいを覚える。そんなメンタリティーの人間を書きたかった。名のある建築家には思想や哲学がある。でも今回、その世界を書こうとしたわけではない。建築士を主人公に据え、そこにタウトという巨匠建築家を対置することで、青瀬の感情の増幅装置にした。それがこの小説の背骨になっています。もう一つ、建築士を主人公にしたかった理由は、家族が書きたかったからです。家について書くことは、家族を書くということ。書きながらずっとそう感じていました。一生活者として建築という仕事をする建築士のほうが、家族の機微を描きやすいだろうと思ったんです。=続
