
地球の持続可能性を考え、SDGsを実行する上で、社会を構成する組織と個人の関係がそもそもサステナブルな状態であることが求められるのではという考えを私は持っている。現在に至るまでSDGsとHRとの関係性はあまりに希薄だったのではないだろうか。
私はこれまで現場の最前線で人事業務を遂行してきた。
2009年から2014年までアジア地域を統括する会社でシンガポールに駐在しながらも、バングラデシュやベトナム等に足しげく出張を繰り返し、現場を見て、組織の観点から経営をサポートしてきた。当時、バングラデシュで史上最悪の労働災害と言われるラナプラザの崩壊事故が起こり、いかに持続可能なビジネスが求められているかということを痛感したことが、私の原体験となった。ビジネスを構成する組織と個人が、サステナブルな関係になっていることが求められる時代なのだ。
SDGsと人事の関係
2015年に帰国した私が見たのは「日本で働くこと」の現実だ。アジアの現場の最前線でいきいきと活躍されていたベテラン社員の方が、日本の本社組織のひとつの歯車となり、以前とは違った姿で働いていた。そして、若手社員が採用時に声を大にして掲げたやる気と、それが満ち溢れた輝く眼差しが、だんだんと薄れていってしまう光景。どの企業においても、ピラミッド組織を構成する上では、少なからずある現実ではないだろうか。
米ギャラップ社が世界各国の企業を対象に実施した従業員のエンゲージメント(仕事への熱意度)調査によると、日本は「熱意あふれる社員」の割合が6%しかなく、調査した139カ国中132位と最下位クラスだった。また、平成元年と平成30年の「世界時価総額ランキング」を比較すると、平成元年当時上位50社のうち32社を占めていた日本企業は、平成30年では1社のみとなっている。
人生100年・産業20年と謳われる昨今、長く豊かに働き続けられる個人を創出すること、そして多様化する個人を活かしながら成長する、これまでとは異なる組織体が求められている。持続可能な個人と企業を生み出すためには、個人と企業が双方に変化を促し、自らも変化していく必要があると強く思うわけである。
働き方改革がスタートして以降、社会の働き方に関する意識は高まった。いわゆるマインドセットは醸成されたと言ってもいい。しかし、それらを実行する人事部の組織体制は旧態依然のままだ。組織体制を変えない限り、本質的には何も変わっていかないのではないか。
人事の役割は、「組織」と「個人」 で最高のパフォーマンスを発揮することだ。
その役割を遂行する上で、現在の企業を取り巻く社会・経済環境にあわせ、いかに体制をシフトさせていくか。それをクリアにすることが今、求められている。だからOne HRで次世代の人事部モデルを策定するプロジェクトを立ち上げた。
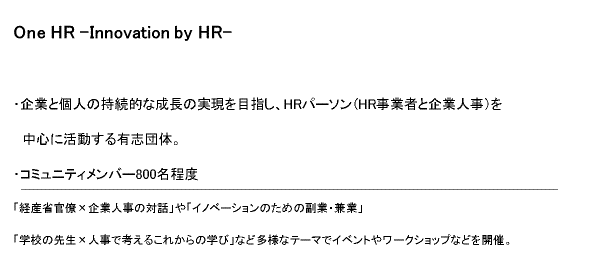
次世代人事部モデル策定プロジェクト
多様化する個のニーズをどこまで組織に取り込み、勝てる(世の中に必要とされるサービスを生み出すという意味で)組織を作れるか? 個人だけがいい、組織だけがいいということではなく、相乗効果を生み出す仕組みとしての“人事部”である必要がある。
人材の流動性は、今後間違いなく高まっていく。しかし決して1社での終身雇用を前提としないまでも、個人がその会社(またはプロジェクト)のメンバーシップとなった時に、いかに組織と個人のパフォーマンスを最大化できるか――。まさにその機能こそが、HRの定義であり、今改めて、人事部門に求められている能力だ。
組織・個人の関係がサステナブルな状態になり、その組織が生み出すアウトプットがSDGs達成につながる。その仕組みを構築することがOne HRの狙いであり、思いだ。
大企業からベンチャー企業の幅広い企業群の人事や、国連SDGs推進者、人材サービス会社、省庁、経営者、幅広い年齢層の社員、学生など。多様な人が集まり、議論を重ねてきた。
そしてまず、私たちは、組織・個人の関係がサステナブルな状態になるための開発目標としてHR版SDGsを策定した。
100年続く個人と組織を創るための6つの目標
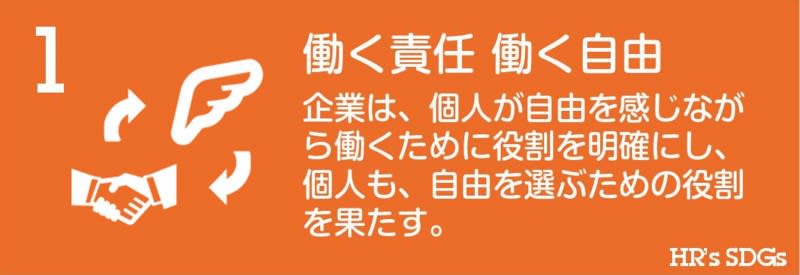
1.働く責任 働く自由
組織に与えられた役割の中で、その組織に最適化されたスキルしか育たず、組織内においても時代とともにスキルが陳腐化し、不必要な人材になってしまう。そんな人たちを減らすために、
私たちは「企業は、個人が自由を感じながら働くために役割を明確にし、個人も、自由を選ぶための役割を果たす」HRを創造します。
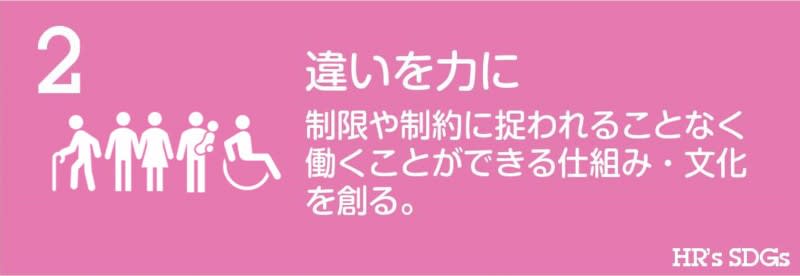
2.違いを力に
性別や国籍、信条、働く場所、身体、保育、介護などを理由に個人の活躍の幅が制限されることで、組織の人材獲得や成長の機会も制限される。個人の違いを、組織で生かすために、
私たちは「制限や制約に捉われることなく働くことができる仕組み・文化を創る」HRを創造します。
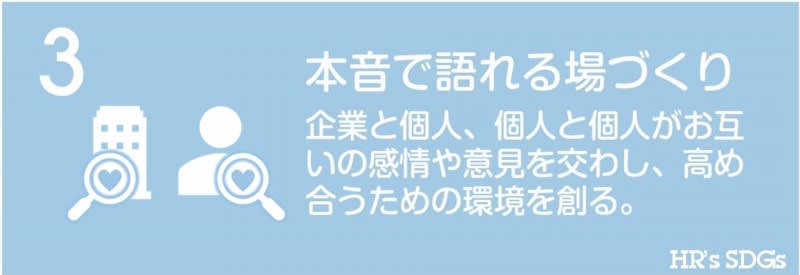
3.本音で語れる場づくり
当事者同士が本音で話し合い、議論し合う機会や環境がないことで、個人の意見が企業に反映されず、企業も個人の意見を吸い上げることができなくなっている。「心理的安全性」を確保し、意見や感情を個人と組織の成長に結びつけるために、
私たちは「企業と個人、個人と個人がお互いの感情や意見を交わし、高め合うための環境を創る」HRを創造します。
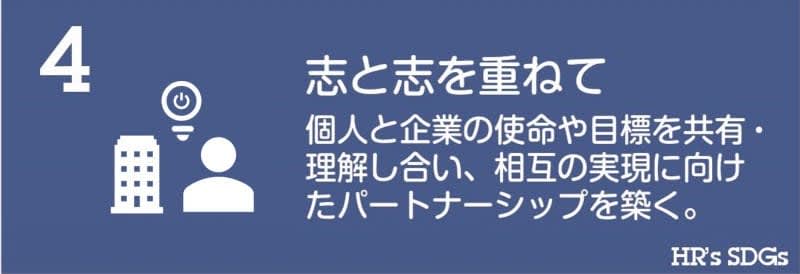
4.志と志を重ねて
仕事をするための目的は「給与」や「やりがい」、「仲間」「社会貢献」など人それぞれ。企業が自身のミッションを押し付けてしまうと、個人は疲弊し、企業の成長を損ねることも。「理念ハラスメント」をなくし、個人と組織がひとつになって前に進むために、
私たちは「個人と企業の使命や目標を共有・理解し合い、相互の実現に向けたパートナーシップを築く」HRを創造します。
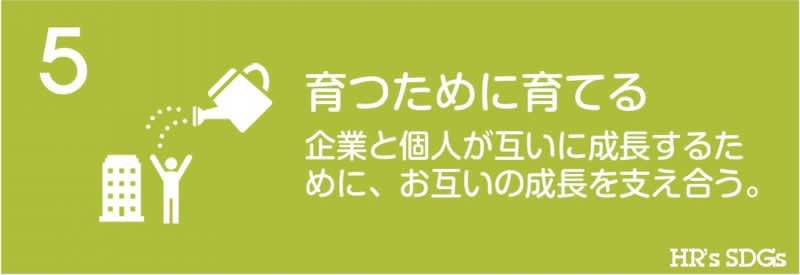
5.育つために育てる
企業組織が評価する個人のスキルやスタンスは、組織外では評価されないことが少なくない。企業が積極的に個人の育成に投資をし、社外と接する機会を後押しすることが必要とされる。時代に合致した企業を創るために、
私たちは「企業と個人が互いに成長するために、お互いの成長を支え合う」HRを創造します。
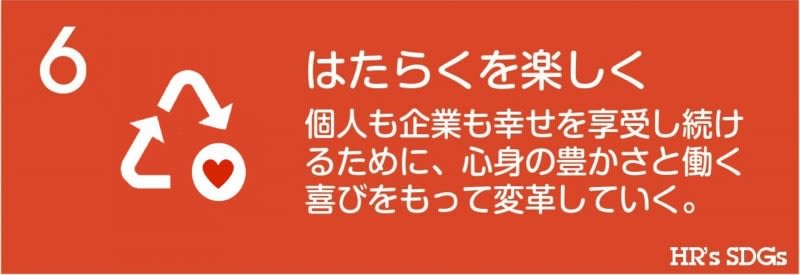
6.はたらくを楽しく
勤務問題を原因の1つとする自殺者数は2017年に1991人(警察庁自殺者統計データ)。日本の世界幸福度ランキングは58位(国連「世界幸福度報告書」2019年版)。個人と企業が持続可能な、豊かな未来のために、
私たちは「個人も企業も幸せを享受し続けるために、心身の豊かさと働く喜びをもって変革していく」HRを創造します。
そして、まさに求められているのは、これらの開発目標を実装できる人事部(仕組み)モデルの策定である。その話の前に次回は平成型の人事部を3つのレベルに分類し、これまでなぜ機能できたのか、なぜ今、改革が必要なのかを詳しく明かしたい。

