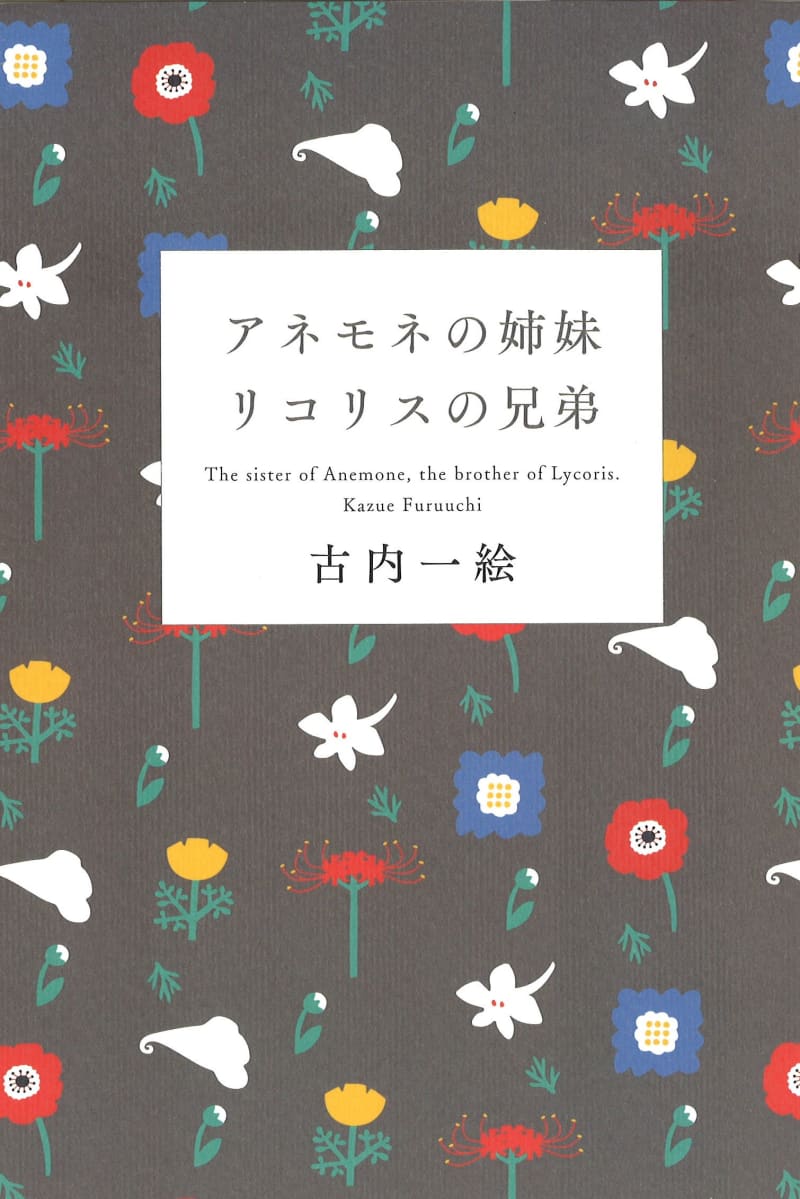
本書の帯には、こうある。
「兄弟姉妹に一度でも仄暗い感情を抱いたことのあるあなたへ」。
そんな人間が、いないはずがないことを、知り尽くした作り手によるコピーである。
6本の短編からなる本書は、コピーのとおり、きょうだいに対して複雑な感情——言ってしまえば憎しみ——を抱え、それを持て余している主人公たちの葛藤を描いている。描かれるきょうだいたちの大抵は、片方が器用に人生を渡り歩いている(ように見える)一方で、もう片方がそのことに屈折を感じながら生きている。周囲からは恵まれた優等生とされていた兄や姉は、そのプレッシャーから自由に羽ばたく弟や妹を羨んでいる。いつだって親の愛情から阻害されている(と思い込んでいる)弟や妹は、親の期待を一身に受けて優等生の役割を果たしている兄や姉を羨んでいる。
彼らは、きょうだい感情のみならず、自分の人生における幸せを受け取ることもきわめて下手である。そして全部きょうだいと親たちのせいだと思いこんでいる。
自分の人生の不遇の原因を、過去に置くことほど愚かなことはない。過去は変えられない。過去が不幸の原因なのなら、これからどんなに時間が経とうが、不幸は変わることがない。
人の人生を左右するのは、「今」でしかない。
6本の短編たちは、そのことを強く説いている。自分の判断ミスで双子のきょうだいに怪我を負わせてしまった中学生は、水泳部の顧問教師のある言葉によって顔を上げる。急逝した父から会社を引き継いだ姉は、奔放に生きる弟の婚約者の言葉によって、自分の人生を選びとる。
著者は、きょうだいたちのわかりやすい和解を描かない。誤解しててごめんねと抱き合って泣いたり、晴れ晴れと握手を交わしたりはまったくしない。描かれるのは、主人公の内心のみ。嫉妬の嵐がごうごうと荒れまくり、自分は間違っていないのだと人生の手綱を握りしめる。その執着の向こう側に、突然、大きな気づきが訪れる。
親の老いをはじめとする人生の岐路を、分かち合えるきょうだいの存在に憧れる私は40代半ばの独り身一人っ子である。しかしきょうだいを持つ人にこう言われたことがある。
「きょうだいがいてもいなくても、孤独なものは孤独だよ」。
幸福も不幸も、誰かのせいで訪れるものではない。すべては、自分。世界を見渡す自分の眼差しひとつなのだ。
(キノブックス 1800円+税)=小川志津子

