
記念すべき第1回在宅医療連合学会、学術集会。
光栄にも我が悠翔会の仲間と私は、いくつものプログラムに呼んでいただいたり、あるいは演題に採用いただきました。
こちらにまとめてご報告をさせてください。

7月14日(日曜日) 13:40~16:30
「在宅医療における医科歯科連携」座長:
竹山 廣光(三重北医療センター)
太田 博見(太田歯科医院)
基調講演:太田 博見(太田歯科医院)演者:
長野 宏昭(沖縄県立中部病院)
川村 洋(大崎歯科医師会)
近江 綾子(特別養護老人ホームつるみね)
若杉 葉子(医療法人社団悠翔会)
太田 俊輔(太田医院)
石井 良昌(社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス海老名総合病院/一般社団法人海老名市歯科医師会)
シンポジウム「在宅医療における医科歯科連携」に悠翔会の若杉先生が登壇しました。
手前味噌になりますが、悠翔会の訪問歯科診療チームは優秀だと思います。
摂食嚥下機能の維持・改善、それに伴う栄養状態の改善、肺炎の発症率の低下など、在宅患者における歯科介入の重要性を様々な角度から数字で示してくれました。
座長の太田先生からは悠翔会の組織の大きさ、患者の母集団の大きさに比して、歯科部門の伸びしろが大きいのではないかというご意見がありました。
「若杉先生が悠翔会のCEOで、歯科医を10人雇用できるとしたらどうする?」という太田先生のウィットに富んだ質問に対し、若杉先生は僕が頭の中で準備したものと同じことを答えてくれました。
訪問歯科診療に対する社会的ニーズの増大を改めて認識させられました。
法人として、歯科部門をしっかりバックアップし、訪問歯科診療に本腰を入れて取り組んでいきたいと思います。
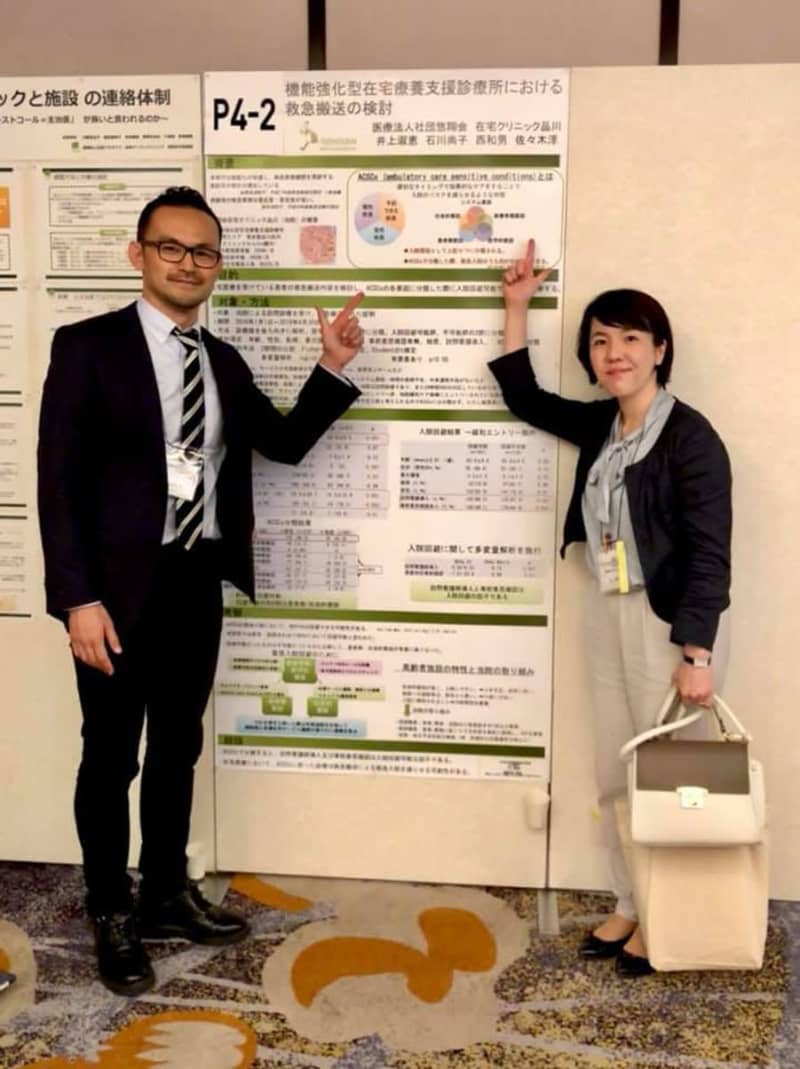
続いては、ACSCs(ambulatory care sensitive conditions)についての品川クリニックチーム、井上先生の発表。
救急専門医ならではの視点で、悠翔会の在宅医療の質と課題を数字で可視化してくれました。
入院の抑制(入院させないという意味ではなく、入院が必要な状況をできるだけ作らないという意味)は在宅医療の重要なミッションの一つです。
もちろん、命を守るために入院という選択肢があることは重要です。しかし、脆弱性の目立つ在宅高齢者は入院関連機能障害によって身体機能、認知機能が低下するケースが多く、社会保障財源の負担も大きいと言わざるをえません(後期高齢者の入院医療費は一日あたり平均で約3万円)。
急変や入院を防ぐことは、患者の生活の質の面だけでなく、救急医療システムの疲弊を回避し、社会コストを削減するという意味でも重要であると思います。
井上先生の検討からは、在宅患者の緊急入院の約4割に回避可能性があったことが分かりました。そして、回避可能性があったと判断された入院には、患者側要因、社会的要因が強く関与していることも明らかになりました。これらに対応することは、もちろん本来の病院のミッションではありません。
在宅医学管理をしっかり行うこと、何かあれば24時間往診できること、これらはもちろん重要だが、患者や家族の安心を守るためには、やはり地域全体のケア力がキーであることを再認識できました。在宅医療は単体では存在意義がないのです。
大都市部とひとくくりにされる首都圏も、地域ごとに特性があります。
悠翔会の12の診療拠点、それぞれで解析を進めれば、「社会的要因」の正体も明らかにできるかもしれません。
探究心の強い有能な若手が僕らの未来を牽引してくれています。
彼らとともに、在宅患者の「真のニーズ」を追求していきたいと思います。

「在宅高齢者と低栄養について考える」
7月15日(月曜日・祝日) 12:20~13:20
ランチョンセミナー 12
座長:平原 佐斗司(東京ふれあい医療生活協同組合梶原診療所)
演者:佐々木 淳
共催:イーエヌ大塚製薬株式会社/株式会社大塚製薬工場
2日目は、私にお呼びがかかりました。
まず平原先生座長の下、ランチョンセミナーで講演させていただきました。
370人収容の会場は立ち見の出る満席で、栄養ケアに対する関心の高まりを感じることができました。講演で使っているデータもそろそろアップデートしないといけませんね。臨床研究にもしっかり取り組んでいきたいと思います。
「これからどうする在宅医療」
7月15日(月曜日・祝日) 13:40~16:00
「これからどうする在宅医療」座長:
久島 和洋(ドクターゴン鎌倉診療所)
荘司 輝昭(立川在宅ケアクリニック)
基調講演:武田 俊彦(厚生労働省政策参与)演者:
木村 幸博(医療法人葵会もりおか往診ホームケアクリニック)
佐々木 淳(医療法人社団悠翔会)
安井 佑(医療法人社団焔やまと診療所)

最後のミッションはシンポジウムでした。
「在宅医療の課題と今後の展望」と題した武田俊彦先生の基調講演は、在宅医療のこれまでの流れを病院との関係性の中で論じつつ、「医療」としての在宅医療のあり方、診療の質やや持続可能性の確保まで、幅広い内容ながら、一本筋の通った素晴らしいものでした。
私は、開業にあたり感化された「患者のニーズが最優先」というメイヨークリニックのコアバリューを悠翔会の基本的な価値観として移植し、これまで進んできたこと、「患者のニーズ」を、患者家族の直接的なニーズ、費用負担者の期待、そして在宅医療専門クリニックが在宅医療を担うことが真の患者のニーズなのか、という3つの視点で整理をして(したつもりで)お話をさせていただきました。
急変を減らす、入院を減らす、そして自宅で看取る。
この3つをKPIに診療の質の改善に取り組んでいること。
急変を減らす、入院を減らすことは、患者の生活・人生の質の確保のみならず、社会保障財源や救急医療システムなどの医療資源の適正利用化にも貢献できること(貢献しなければ、単なる医療費の上乗せにしかならないこと)。
そして、患者の真のニーズは、その人のことをよく理解している「かかりつけ医」が、在宅医療を含めて最期まで診てくれること。その前提に基づき、地域のかかりつけ医の対応困難な時間帯のバックアップ、対応困難な患者の診療引継ぎを中心に地域連携を進めていること。
武田先生からは「社会的共通資本としての在宅医療」という言葉がありました。
私は、在宅医療を医師のビジネスモデルではなく、地域ニーズに応えるための公共事業として再定義する必要があると感じています。
やりたいことをやる、のではなく、やるべきことをやる。
私たちの自己実現のための医療ではなく、よりよい地域の未来を作るための医療に取り組む。
保険診療とは、そういうものなのだと思います。
施設在宅医療についての質問もありました。
在宅患者に占める施設入居者の割合が非常に大きいのに、在宅医療連合学会で取り扱われているのは個人宅の在宅医療ばかり。看取り率の高い福祉先進国において、病院死の割合が低いのは、在宅死率が高いのではなく、施設死率が高いから、という事実もあります。
施設在宅医療はやりたくない、という在宅医が多いのも事実ですが、施設在宅医療が機能しなければ、病院死率を下げることは難しくなります。
さまざまな論点が出て、よいシンポジウムであったと思います。個人的には在宅死を増やすという部分において、在宅医療専門クリニックがどうかかわるべきか、ということについて、もう少しディスカッションしたかったですが、各シンポジストの講演も非常に示唆に富むもので、たくさんの学びと気づきをいただきました。
僕自身は、話したいことが分散し、準備した資料もややオーバーフロー気味で、プレゼンテーションとしては反省点の多いものとなりました‥修練します。
座長の久島和洋先生、荘司輝昭先生、貴重な機会をありがとうございました。
武田 俊彦先生、木村 幸博先生、安井 祐先生、有意義な講演とディスカッションをありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
佐々木 淳
医療法人社団 悠翔会 理事長・診療部長 1998年筑波大学卒業後、三井記念病院に勤務。2003年東京大学大学院医学系研究科博士課程入学。東京大学医学部附属病院消化器内科、医療法人社団 哲仁会 井口病院 副院長、金町中央透析センター長等を経て、2006年MRCビルクリニックを設立。2008年東京大学大学院医学系研究科博士課程を中退、医療法人社団 悠翔会 理事長に就任し、24時間対応の在宅総合診療を展開している。

