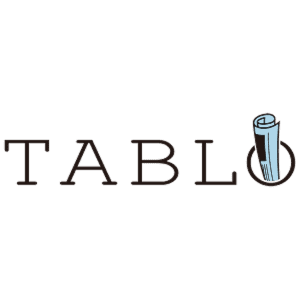日本各地にはさまざまな「奇祭」がある。三大奇祭は秋田県「なまはげ紫灯祭」、長野県「御柱」祭」、山梨県「吉田の火祭」と言われ、どれも数百年の歴史をもった伝統的な祭だ。
2020年、令和という新元号を迎えたこの年に東京であらたな奇祭が新たな広がりを見せようとしているのをご存知だろうか。
11月10日、中野区の川島商店街にわらわらと人が集まり始めていた。例年この時期になると川島商店街では、東京行灯祭が開催されており、この日も滲むように赤く光る行灯が夜空を染めていた。人波を掻き分けながら進むと、商店街の一角の広場に人だかりができていて、あらゆるお祭りの花形的存在である神輿がスタートを待っていた。
しかし、その神輿が他とは様子が違うのである。

鳥居にしめ縄は確かに神輿のそれだが、やけに明るい提灯はLEDが仕込まれたものだと想像が尽くし、そこに書かれた「奉納」などの文字は8ビット風のデジタル感がある。近寄ってよく見ると神輿の中には、何やら機械が搭載されている。

これが「仮想通貨奉納祭」の目玉「仮想通貨の着金に反応しバイブスをあげる神輿」である。神輿に搭載されているのはビットコインの受信機で、インターネットを通じて世界のどこからでもこの神輿に課金ができる。つまり、キャッシュレスで世界中からお賽銭を投げてもらおうという仕組みだ。課金されれば神輿のLEDがギラギラと光り輝き、担ぎ手や見るもののバイブスをあげるという。アートディレクターの市原えつこさんが発案しクラウドファンディングで集まった資金によって作られた。

18時過ぎ、巫女の装束を着た市原さんの掛け声とともに神輿がスタートし、商店街を進む。見た所、伝統的な祭の神輿を担いだことのないような人々が担いでいるため、速度が異様に早くなってしまい、そこはどことなく素人臭いが、この祭が続いていくことで安定してくるものだろう。掛け声は「せいや! せいや!」のようだが違う。よく聞くと「Payや! Payや!」という声とともに進んでいる。そんな中、世界のどこかから課金されたのか神輿がギラギラと商店街を照らすシーンもあった。

これだけならば、地に足の着いていない前衛芸術のいち表現に過ぎないが、商店街には地元の店がたこ焼きや焼き鳥などの屋台を出しており、そこを歩く人も老若男女様々で、古い祭の様相も残している。


おまつりの出店の定番でもある射的は、ここでも出店されていた。私たちが子供の頃に見てきた懐かしの射的とともに、タブレトッ端末にまとを表示するものや、真っ白いモニュメントにプロジェクションマッピングで表示された景品を射抜くような、現代にしかできない射的も見られ、両時代の端境にいることを実感した。

また、市原さんの作品である「喘ぐ大根」(触れると喘ぎ声がなる仕組みになっている)や、ロボットに天狗面をつけた天狗ロボットも展示されていた。

これは本来、天狗ではなく故人の顔を3Dプリントしロボットにつけ、故人の仕草や口癖を再現するようにモーションプログラムして、あたかも故人が憑依したように動かすという「デジタルシャーマン」として発表されたものだ。
確かに、大根は歓喜天信仰などにも見られる性的なメタファとしての信仰対象であるために「喘ぎ」に通ずるものであるし、デジタルシャーマンや仮想通貨の着金でバイブスをあげる神輿も面白い。
ただし、祭りは古来より、生きている人間が自然や祖霊や魂(たま)に「動かされる」かたちで発生している。それに対し仮想通貨奉納祭は、生きている人間が能動的に発信しようとしている部分がうかがえるために、祭の向こうに神や神を感じて生活している人を見ることはできなかったのが、個人的には少し物足りなかった。
とはいえ、伝統にアプローチする意図と地元の方々も巻き込んだ仮想通貨奉納祭はまだ始まったばかり。もしかするとずっと未来には「令和にはじまった伝統的な祭のスタンダード」として君臨しているのかもしれない。(Mr.tsubaking連載 『どうした!?ウォーカー』 第46回)