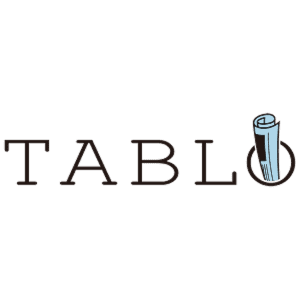写真はイメージです
※こちらの記事は『憑き物 「目の前に突きつけられたスマホの画面を見て聡子さんは目を剥いて絶叫してしまった!」|川奈まり子の奇譚蒐集三六』からの続きです
――考えても仕方のないことや。
動かなくなった車の中でいち早く冷静になり、すぐ横のガソリンスタンドに飛んで行ったのは聡子さんだった。
車をメンテナンスしてもらう間に喫茶店で休憩することを提案したのも、彼女だった。
車は、ガソリンスタンドのスタッフに後ろから押してもらいながら、姉の桂子がハンドルを操作して動かすことが出来た。車を動かす前に、母と娘の美和も、各々、バッグを持って車から降りたので、まずは2人を誘ってみたわけである。
「すぐ手前に茶房ナントカって店があったやん? 行ってみよう」
そのとき、姉がガソリンスタンドのスタッフを伴って3人の前にやってきた。すぐに、スタッフが車の状態を説明しだした。どうやら地元の人らしかった。
「まだ皆さん、いきしなにエアコンつけっぱなしで山道を上るさかい、オーバーヒートでエンコしちゃある方はここでは珍しないんよ。さーよ、なえやろな、警告ランプが点いてやんが、冷却水が空になっちゃある。オーバーヒートの初期症状に気づきやんちゃあったけ? 水温計がHの方へ進んだり、フロントからもじけたみた音が聞こえてきたり、臭いが……。そうじょなぁ、あがの鼻にも臭わねっしょ……まあ、他に原因は考えやんさけ……」
作業としては冷却水を補充するだけだが、エンジンを冷ますために30分程度、待つ必要があるとのことだった。
――峠道は涼しかった。それに母は近頃、エアコンを嫌う。せやから冷房は切っとったのや。
しかし、聡子さんたちは4人とも反論しなかった。
赤い女の呪いだ。聡子さんはそう直感していた。
みんなも同じ気持ちに違いないと思ったが、わざわざ口に出して言ってしまえば、さっきいったん薄れた恐怖が倍になってぶり返しそうな気がした。
「桂子ネエ、今、お茶しに行かへんかって話してたとこ」
「ええな。30分もあるんやし、ちょうど、ぼちぼちお茶したかったんやわ」
姉の桂子がホッとした表情で応えると、美和が言った。
「なら、すぐそこに、ナントカ茶房って書いた可愛い喫茶店があったから、そこにしぃひん?」
「おばあちゃんは何でもええで。……あら? また雨?」
母が掌を上に向けるのを見て、聡子さんが空を振り仰いだ途端、頬に小さな水滴が落ちてきた。
太陽は出ている。
「なかなか終わらん花嫁行列だこと。ぎょうさん狐さんがおるんやね」
母の呟きを聡子さんは聞き流した。なぜか急に苛立ちを覚えたので無視したのだった。
異様な天気、奇怪な写真、合理的に説明できない車のトラブルは――たまたまガソリンスタンドの前でエンジンが停止したことも含めて、得体の知れない事態が進行している証拠だという気がしてならなかった。
――ただの狐の嫁入りやあれへん。これは全部、繋がっとるんや!
聡子さんは、そう確信していて、母に対して、いや、姉や娘にも、「わかっとるくせに!」と叫びたい気持ちを抑えるのに必死なのだった。
高野山の町に現代的な飲食店が何軒もあることは、訪れるまで知らなかった。食事は奥之院の宿坊で取るつもりだったし、どうせ1泊しかしないのだからと、事前に調べてみることをしなかったのだ。
正直、もっと鄙びた、建物と言えば寺院しかないような山奥を想像していた。なにしろ、標高850メートルの山上にあり、さらに千メートル近い八つの峰に囲まれているのだから。
しかし、実際に来てみたら、山上に町が広がっていた。もっとも、ほとんどの建物は木造の二階建てだ。舗装道路の両脇に町並みを形成している家の多くは土産物店や飲食店。田舎には違いないけれど、想像していたより開けていたと言ったところだ。それでいて古き良き日本情緒も漂っており、そのせいか外国人観光客の姿も目についた。
高野山は約100年前までは女人禁制で、空海の母親も入山できなかったそうだが、人種や国籍を問わず、女性の観光客も少なくない。
そういう景色を見た後だったので、その店に入ってみたら、店内が一組の外国人観光客のカップル以外、女性客ばかりで占められていても、別段、不思議に感じなかった。猫をモチーフにした小物などを店内で販売しており、女性が好みそうなヘルシーな軽食と和洋折衷のデザートがメニューに並んでいたのだから、尚更だ。
「可愛いお店! また、友だちと来たいな」と美和が言った。
「とか言って、彼氏と来るつもりやな? アリバイ工作ならいつでも協力するよ」と桂子が揶揄う。
聡子さんは、美和がすぐに愉快な言葉を打ち返すもの、と、思っていた。
いつもそうなのだ。次姉の桂子は、隙あらば美和を恋愛ネタでイジるのだが、美和は毎度ノリ良く返す。
ところが、どういうわけか、今回に限って、娘は顔をこわばらせて、
「……そんなん、いひん」
と、一拍、妙な間を空けて、桂子に答えた。
――やっぱり、あんな写真が撮れたのは、美和が誰かの嫉妬を買ったせいかもしれない。
よく考えてみれば、あの写真の中で、赤い女を画面に映し出したスマホを掲げているのは聡子さんだが、その女が憎しみに満ちた眼差しを向けていた相手は、写真の撮影者である美和ということになるのだ。
――何か自分でも思い当たることがあるんじゃないかしら?
美和に直接、疑問をぶつけてみようか。聡子さんは逡巡しはじめたが、そのとき、彼から電話が掛かってきた。
聡子さんは「彼から電話や」と3人に断って席から離れた。
「はい、もしもし。ジョンのようすはどう?」
「ジョンは元気や。さっきヘルパーさんと一緒に散歩に行ってきたしね。そないなことより、着歴見たよ。どないした? 何ぞあったん?」
「……勘がええな。あのね、京都でね……」
聡子さんは彼に、太秦で厭な写真が撮れてから変な具合に車がエンストしてしまったことまで、つぶさに打ち明けた。
すべて聞くと、彼は言った。
「実はな、聡子ちゃんが電話に出た途端、全身、寒イボ立ったんや! せやから何ぞあったんやないかと思ったんやけど、そういうことか……。その写真は、すぐに削除したほうがええ」
「せやけど、美和が、お祓いを受けてから消さへんとマズいんやないかって」
「そないなことはおまへん。気に病みながら持ち歩いとる方が障るから、すぐに消しぃ! 忘れてまうのがいちばんや!」
わかった、と、聡子さんは応えた。
けれども、電話を切ってすぐに、自分のスマホに美和が件の写真を送ってきたことに気づいた。彼と電話で話している間に送信してきたのだ。
「私が怖がっとることを知りながら、送りつけてくるなんて、どういうつもり?」聡子さんは美和を問い詰めた。美和は悪びれたようすもなく、「彼に説明したらええと思ったの」と答えた。
「ママが、写真を見ながら、どこがどんなふうやったか、彼に説明してあげるって、自分で言っとったやろ?」
「あないな写真を? 事情がちゃうやん! 彼はすぐに削除せぇと言うとったで。……ほら見ぃ! 今、送ってきたのは消したから、美和も削除しぃ!」
「……今じゃなきゃあかんの?」
「そうよ! すぐやりなさい!」
「まあ、まあ、聡子、あんたも、そないに声を荒げんと! なんなん、こんなお店の中で、おっきな声出しぃ恥ずかしいやろ。たいがいにしぃや」
母になだめられて聡子さんは引き下がった。
美和はスマホをバッグにしまいこみ、それきり、この旅が終わるまで、聡子さんとは目を合わそうともしなかった。
――高野山の奥之院は、一の橋、中の橋、御廟橋という三つの橋が、三重の結界になって守られとってな。橋を三つとも渡ったら、憑いとる悪いもんが落ちるんや。
結局、奥之院のとば口に立ったときには午後4時を過ぎていた。一の橋に臨むと、旅の計画を立てる前に聞いた彼の言葉が鼓膜の奥に蘇ってきた。
――そうや。橋を渡れば、美和に憑いてるかもしれない悪いものも落ちるんや。
「みんな、橋のたもとで一礼してから渡るきまりなんやって。そうしたってな」
――弘法大師さまが迎えに来てくださっとるっちゅう話や。もう大丈夫や!
見れば、美和も深々と頭を下げていた。聡子さんは、少し安堵を覚えながら、ゆっくりと橋を渡った。
杉木立に囲まれているせいか、まだ9月だというのに、境内の空気は凛と澄み切って冷涼だ。一の橋とせせらぎを背にして石畳の参道を歩きだすと、橋を渡る前よりも身も心も軽やかになっていることに気がついた。
「なんか、気分がスッキリした感じがしぃひん?」と姉が話しかけてきた。
「疲れが取れたわ」と母が言った。「さっきまでくたびれて、もう宿に行きたいと実は思ってたの。それが、どういうわけか、急に元気になった。弘法さまのお陰かねぇ……。不思議なもんや」
気のせいと言われてしまえば、それまで。
そうわかっていても、実感として一の橋を渡る前よりも心身ともに疲労が快復したように思えた。
こんなにもご利益があるなら……と、聡子さんは、口には出さなかったが、美和のスマホからアレが消えているのではないか、と、あり得ないことを期待した。
奥之院の参道沿いには、歴史に名を刻んだ武将の墓所や墓碑、各時代のさまざまな供養碑が2万基以上あるという。
墓碑、供碑があると言っても、辺りには陰ではなく穏やかな陽の気が漂っていて、豊臣家や織田信長の墓所や上杉謙信・景勝の霊廟、弘法大師の石像の前では、明るい顔で記念撮影をしている人々が見受けられた。
中の橋は参道のほぼ中間地点にあり、平安時代にはこの下を流れる川で禊をした後、向こう岸へ渡ったそうで、手水橋と名付けられている。
聡子さんは一の橋からここに来るまでに、いくつか写真を撮っていた。もう美和に自分を撮らせるつもりはなかったが、美和の方からも撮らせろとは言ってこない。その代わり、中の橋を渡ると、母が全員そろった記念写真が欲しいと言い出した。
「もうじき5時や。日があるうちに4人並んだやつを撮ってもらおう。次の橋から向こうは写真撮影禁止やねんから、今のうちや」
それを聞いて、姉が「駐車場代が大変や」と、ぼやいた。
一の橋のそばに8台しか停められない有料駐車場があったが、最初はそこではなく、中の橋の近くにある無料の大型駐車場に車を停めるつもりでいた。
ガソリンスタンドを出る前に、みんなで話し合って決めたことだった。
ところが、一の橋の駐車場の前に差し掛かったとき、1台の車がそこから今しも出ようとするのが見えた……と、思ったら、桂子がそっちへハンドルを切っていたのだ。
そして、慌てて止めようとすると、「やっぱ、一の橋んとこから全部歩いた方がええんちゃう? モータープール代は、うちが持つよ」と言ったのだ。
「……何よ? 聡子ちゃん。今さらいちゃもんつけんなって顔しとん。せやけど、美和の解説やあんたの話を聞いて、中の橋からじゃ、お大師さまに出迎えてもらえへんのやないかと思ったねん。中の橋ん方から一の橋まで1キロも歩いて戻らせたら、かあちゃんにはキツイだろうし」
それを聞いて、生来、細かいことは気にしない性質で、今回もまるで平気そうにしていると思った姉も、それなりに懸念していたことがわかった。母が疲れたそぶりを見せないのも、御廟橋まで渡りおおせて穢れを祓うべきだと信じているからこそ、なのかもしれない。
――何考えとんのやら、わからんのは、美和だけや。
御廟橋も無事に渡り、弘法大師御廟の拝殿・燈籠堂で祈りを捧げた。
燈籠堂には無数とも思える献灯が天井から下がり、柔らかな光で堂内を照らしていた。その中には「消えずの火」や「貧女の一燈」があるとのこと。前者は、白河上皇が献じて以来、千年余りも燃えつづけている奇跡の炎であり、後者は、貧しい少女が養父母の菩提を高野山で弔うために自らの黒髪を売って購った燈籠だ言い伝えられている。
最後に、燈籠堂の裏にある、弘法大師御廟をお参りした。弘法大師は入定して即身仏となってからも、この御廟の地下で瞑想しており、地上への出入りも自由になさっているそうだ。
御廟に入ることは出来ないので、他の参拝客と一緒に、建物の外で手を合わせて拝んだ。
それから来た道を駐車場まで戻り、再び車に乗り込んで予約した宿坊へ向かったのだが、宿坊のある寺院に到着したとき、聡子さんは、だいぶ前から娘の声を聞いていないことに気がついた。
どうやら、口をきいていないのは聡子さんに対してだけではなく、奥之院の途中から、母や姉とも会話していなかったようだ。
宿坊の座敷に落ち着くと、ポツポツと喋るようになったが、いつもより口数が少なく、顔つきも沈んでいる。
「美和、なんやか暗いね。どうした?」
「別に。ぎょうさん歩いて、しんどいだけ」
「……ならええけど。あの写真は、やっぱり消した方がいいんとちゃう?」
「ママってば、そればっかり。私のスマホの写真やねんから、好きにさせてよ」
蠅でも追うような、うるさそうな表情で睨まれては、退散せざるを得なかった。
その後、翌日、大阪の家に帰宅するまでは、何事も起こらなかった。家に着く時刻を彼に知らせていたので、帰ると間もなく、ヘルパーが運転する車で、彼とジョンがやってきた。
ジョンは、千切れんばかりに尻尾を振りながら、車から飛び出してきた。まっしぐらに聡子さんに飛びついてくる。聡子さんが主に世話をしているので、これは予想通りだった。
ジョンの金色の毛並みに覆われた頭の中には、最初に聡子さん、次に娘の美和、その次が母、最後に姉の桂子という序列がきちんと刻まれていて、こういう場面でじゃれつく順番も定まっていた。
だが、ジョンは美和を飛ばして、母のところに跳ねていった。次に姉の方へ。
そして玄関ポーチまで走って、尻尾を振りながら家族が来るのを待っていたのだが、美和が近づくと、急に尾を尻に巻き込んで激しく吠えだした。
「ジョン! どないしたん? 美和ちゃんよ?」
いつもは大人しい愛犬に話しかけ、なだめようとして……よく見ると、ジョンは、娘の頭から数十センチ上の空間に視線を据えて、吠えかかっている。
「そこに何ぞいるん? ジョン、こら、静かにしぃ!」
――ジョンは静かになった。
吠えはじめてから1分足らず。キューンと一声、情けない鼻声を発したかと思うと、玄関ポーチのタイルの上に横倒しに倒れて、痙攣しはじめたのだ。
白目を剥き、すでに意識が無いようだった。聡子さんが膝の上に抱きかかえると、よだれの泡にまみれた長い舌がデロりと垂れ下がった。
すぐに動物病院へ連れていったが、そのまま意識を取り戻すことなく、2日後に息を引き取った。
聡子さんの彼は、美和さんに悪霊が取り憑いて、奥之院では一度は封じ込められたものの、再び力を盛り返していたのではないかと言っているそうだ。
「美和ちゃんには原因があらへん。4人の内で美和ちゃんがいちばん弱かったから、そいつは美和ちゃんを選んだねん。ほんで、ジョンを見ると、ジョンに移った。そこにおる中で霊力がいちばん弱いのがジョンやからね。ジョンは美和ちゃんより霊力が弱いから殺されてもたけれど、死ぬことで、憑きものも彼の世へ連れていってくれたんちゃうん? せやから聡子ちゃん、もう安心しぃや」
こう話して、彼は聡子さんを慰めようとしたのだった。
聡子さんは、しかし、彼の推理を信じていないのだという。
「なぜなら、美和はあの後も、なかなか写真を削除しようとしまへんでしたから。旅行から1年近く経って、盆の入りの頃に思い出して訊ねてみたら、目の前でスマホからアレを削除してくれましてんけど、どこぞにコピーを残しとるんやないだろうか……。口数は戻ったし、明るい顔を見せてくれるようにもなったんですけど、なんとなく、美和のようすには、未だに違和感があるんですわ。どこぞ変わってしもたような……」
こう聡子さんが心細げに訴えるのを聞いて、私は「やはり、美和さんには、どこかの女性に恨まれるようなことがあったんでしょうか?」と質問した。
「いいえ!」と聡子さんは強く否定した。
「あの後も訊いてみたんですけど、本人はきっぱり、無いと言っとります。それにまた、旅行前に何ぞ兆候があったら、私が気づいたと思うんですわ。せやけど、あらへんでしたし……」
色恋沙汰について、年頃の娘というものは上手に母親に隠し事をするものだ。
聡子さんにも、わかっているのだろう。その口調は明らかに自信なさげで、かえって突っ込みを入れることがはばかられた。
それは意地の悪いことだと思ったし、それに、私が会ったことのない美和さんというお嬢さんに対して、とても失礼なことなので。
「……きっと彼が正しうて、私が気にしすぎなんやと思います。かあちゃんも桂子ネエも、美和について、私が感じとるようなことは言ってまへん。ジョンが美和の憑き物を持っていってくれたから、ジョンがおらんこと以外は、すっかり元通りなんやんなぁ……?」
聡子さんの恋人は、近頃、「もう心配あらへんさかい」と言って犬を飼うことを盛んに勧めてくるという。
目が見えない代わりに霊感があるという、聡子さんの恋人。彼の言葉を補足すれば、「もう心配ない。なぜなら、憑きものは去ったのだから、再び犬が死ぬようなことはない」ということになるだろう。
彼を信じてみてもよいのでは、と、私は思った。
しかし、それは直に美和さんたちと触れ合って生活しているわけではない、見ず知らずの他人による、無責任な意見に過ぎないのかもしれない。聡子さんは、どうしても疑いを拭えずにいるようだった。
彼女は最後に、捉えようによっては、かなり不穏な心情を吐露した。
「母と姉も、美和の変わりように気づいておらへんのか、気づかない振りをしとるのか、彼の言うとおりや、と……。でも、私は、まだ次の犬を飼う勇気が出ぇへんねん。また犬があの子の頭上を見て吠えて死んだら、私は、みんなと一緒に暮らせへんくなるさかい、恐ろしうて……」(終)
(川奈まり子連載 『川奈まり子の奇譚蒐集』第三十七話)