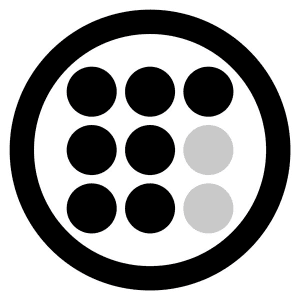マントル氏のPSAグレード10は世界に3枚存在、内1枚はダイヤモンドバックスのケンドリックオーナーが所持
野球ファンであれば1度は目にしたことはあるであろう「野球カード」。近年では球場来場者へ配布されたりする身近な存在。ブームに火が付いたのは1973年。この年から毎年プロ野球カードがスナック菓子のおまけに付くようになり、現在では1973年発行の長嶋茂雄氏のスマイルショットに数万円の値が付くことも。Full-CountではPSA Japanを運営する「Collectors Universe Japan合同会社」のアジア・オセアニア事業統括責任者を務めるアラム・トニーさんにインタビューを実施。アラムさんが語るカードの奥深さ、魅力的な一面とはどのようなことなのだろうか。
PSAとは、カード1枚1枚の真贋、状態を鑑定する会社だ。状態を10段階に分けたグレードを与え、カードを湿気やカビなどから守る特殊なケースに超音波で密閉した状態で送り返してくれるサービスを行っている。カードコレクターならば1度は目にしたこともあるだろう。また、スポーツのメモラビリアアイテム(ボールやユニホームなど)やサインの真贋の鑑定も行っている。アメリカでは1991年に創業し30年近い歴史を積んでいるが、日本支社が設立されたのは2018年とまだ日は浅い。
野球カードの歴史は古くアメリカでは1880年代にはタバコのおまけとしても登場、1930年代にはチューインガムのおまけに付くようになっていった。その後、形を変えつつ、現在ではTopps社などがパック売りで販売し人気を博している。アメリカでは日本に比べ、野球カードの価格が高騰することが多く、投資目的でカードを集める人も多いという。
中でも1952年Topps社製のミッキー・マントル氏のカードが2018年に10段階中9のグレードのものがオークションで約3億円で落札されるなど“夢”が詰まっている。アラムさんはもしこれのグレード10のものが出品されれば「1000万ドル(約10億7000万円)する可能性もある」と話した。現在マントル氏のPSAグレード10のカードは世界に3枚しか存在せず、その内1枚はダイヤモンドバックスのケン・ケンドリックオーナーが持っているとのこと。アメリカではカードショーなどに展示するために同カードを運搬する際にはこの1枚のためだけに現金輸送車を使うこともあるというから驚きだ。
日本では、71年からカルビー社がスナック菓子のおまけに付けた仮面ライダーカードが人気を博し、73年から野球カードがおまけにつくようになった。中でも長嶋茂雄氏が笑顔で写るカードは人気の1枚でオークションなどで数万円の値を付けることもある。グレードが日本のカードにも浸透すれば、米国のようになる可能性を秘めている。
「カードは1つの思い出」、「ホビーとしてスポーツ業界を盛り上げていく大切な要素」
自身も大洋ホエールズ(現DeNA)のファンでありコレクターだったと話すアラムさん。カードの真贋を鑑定するPSAに入社したのはオークションでのある出来事がキッカケだったと明かした。
自身がオークションで落札したサインボールについて「これって本物?」と思ったことから、その真贋を鑑定してもらおうとそういったサービスを日本で探すも1社も見つからなかった。アメリカでは既に数社が鑑定のビジネスを始めていたことから、自分が日本の第1人者になろうと思ったことがきっかけだった。日本にはそのようなサービスを提供する会社がないことや、自身が請け負うことなどを記し、複数のアメリカの鑑定会社に手紙を書いて送った。すると、PSAから返事があった。同じタイミングでアジア進出を考えていた同社と考えが一致し、アラムさんは資料を作って、アメリカに飛んだ。プレゼンも見事に決まり、仕事を託された。いちコレクターだからこその悩みからPSAと出会い、行動へ移し、それが実り“今”があると笑顔で語ってくれた。
アメリカではPSAによるカード鑑定は一般的で広く普及しているが、日本ではまだ浸透が浅い。しかし、アラムさんは「お気に入りのカードを最適な状態で保存したいコレクターは多いと思う」とし、ぜひ日本でもこの動きが広がってほしいと望んでいた。
「カードは1つの思い出となります。その時代をとっておくことにもなります。これは1つのホビーとしてスポーツ業界を盛り上げていく大切な要素だと思います。その点がまだ日本ではそこまで浸透していません。まだこれから伸びていく、伸ばしていければ良いところだなと思っています」とカードの魅力を語るアラムさんの目はいちコレクターの目になっていた。
これを読んだ皆さんの押し入れなどの中に、眠った昔のカードはないだろうか。もしかしたらそのカードが数年後には凄い価値が付いているかもしれない。そんな魅力が1枚のカードには詰まっている。(中村彰洋 / Akihiro Nakamura)