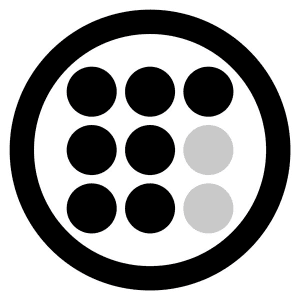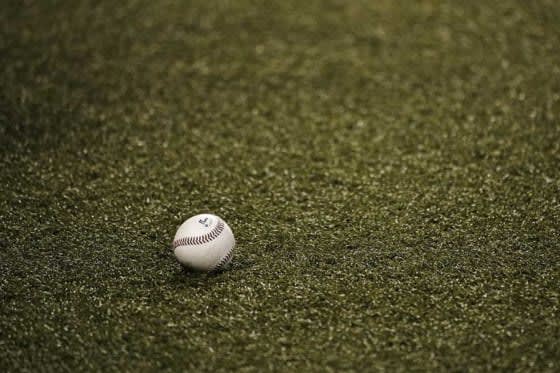
ルートインBCリーグの公式戦では、試合前に「“MIKITO AED PROJECT”」のアナウンスが
独立リーグのルートインBCリーグの公式戦では、試合前に「“MIKITO AED PROJECT”」のアナウンスがある。これは、2006年7月9日、新潟県糸魚川市の野球少年、水島樹人君が少年野球の試合前に心臓発作で世を去ったことに端を発している。樹人君はまだ9歳だった。現場にAED(自動体外式除細動器)があれば、救えていたかもしれない命だった。
樹人君の母親は、当時、開設準備中だったBCリーグ(現ルートインBCリーグ)に手紙を送った。
「新潟のプロ野球球団を応援したいと言っていた息子の夢を叶えてあげてください」
当時独立リーグ設立へ向けた動きが難航していた関係者たちは発奮し、そこから資金や支援者をさらに集めて、翌年のリーグ開設にこぎつけた。BCリーグ関係者は、樹人少年の遺志に報いようと「“MIKITO AED PROJECT”」を設立し、グッズを販売。野球少年たちが安心して野球に打ち込めるように、グッズの収益で地域へのAED寄贈活動を展開した。
13年が経過し、ルートインBCリーグは合計33台のAEDを自治体やスポーツ団体に寄贈している。
健康な青少年が、心臓振盪で亡くなる例は決して少なくない。野球の場合、打席に立っていた子供が死球を胸に受けたり、守備に就いていた子供が打球が胸に当たったりして、突然倒れこむ。その時には既に意識がない。自発呼吸もなくなっている。1分間で生存率が10%少なくなるといわれ、10分間手当てをしないと生存率は0%になるといわれている。
救急車が来るのは平均20分かかるといわれているから、それまでに手遅れになるケースも少なくないのだ。心臓振盪は投球や打球の強さとは関係がない。当たるタイミングが悪ければ、心臓が小刻みに痙攣を起こして体中に血液を送ることをやめてしまう。また、心臓振盪は持病のあるなしや体の強い弱いにかかわらず、誰でも起こりうる事故でもある。ボールが当たるだけではなく、選手同士が交錯して体の一部が胸に当たったり、ヘッドスライディングをするだけでも起こることがある。
こんな時にAEDがあれば、人工呼吸をして心臓マッサージをしながら、AEDで心臓に電気ショックを与えることで、心臓が再び規則正しい動きを取り戻し、呼吸も回復して助かることがあるのだ。AEDがなければ、心臓マッサージを繰り返すしかない。正しい措置法を知っていたとしても助かる率は非常に少ない。
少年野球にも広がる「AED」の設置
サッカークラブなどでは、AEDが設置されているところが増えている。JFA(日本サッカー協会)では、2017年から『スポーツ救命ライセンス講習会(BLSプロジェクト)』をスタートさせ、指導者にAEDの使用法の習得を広く呼び掛けている。
しかし、中学校以下の少年野球では、まだまだAEDの普及は遅れている。また野球指導者で、心臓マッサージについての知識がある人はまだ少ない。そういう状態では、事故が起こっても、救急車を呼ぶだけで、なすすべもなく子供が亡くなっていくのを見ているしかなかいのだ。
神奈川県下のある少年軟式野球チームは、入団者不足に悩んでいた。ある年、選手の父親が監督になったが、話を聞いてみると近隣での評判が非常に悪いことに気が付いた。それまでの指導者は給水時間を適切にとらなかったり、猛暑でも練習を続けさせたり、昔ながらの指導方法だった。また罵声を浴びせることもあった。このために「あのチームはブラックだ」といううわさが周囲に広がっていたのだ。
特に母親たちの拒否感が強かった。そこで新監督は、チームに諮って「AEDのレンタル」を決めた。月額数千円だが、監督、コーチで費用負担をすることにした。さらに、専門家による「AED講習会」を行った。講習会には選手の父母だけでなく、周辺地域の家庭にも呼び掛けて参加してもらった。これをきっかけにチームの評判は良くなり、入団者が少しずつ増えていった。このチームは今、体験会の際に「AED講習会」も行うようにしているという。
昨年から始まった「ぐんま野球フェスタ」の会場でも「AED講習会」が行われている。全国的な普及にはまだほど遠いが、少年野球の現場にも少しずつAEDが配備されようとしている。
わが子を少年野球チームに入れようとするお父さん、お母さんはチームに「AEDの用意はありますか?」と聞いてみるとよいかもしれない。それで、そのチームが「健康面に配慮しているかどうか」の一端が分かるからだ。(広尾晃 / Koh Hiroo)