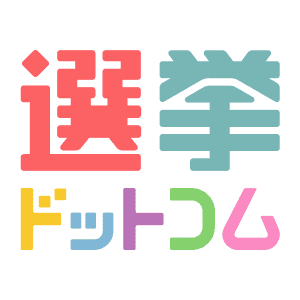家族の形や女性の活躍、少子化問題や憲法改正など、様々なテーマにもつながる「選択的夫婦別姓」の是非について、インタビュー形式で、さまざまな立ち位置の方の声を紹介する当連載。初回は、自民党幹事長代行・衆議院議員の稲田朋美さんです。防衛大臣を経験し、「保守派」として知られる稲田氏は、夫婦別姓についてどう捉えているのか?お聞きしました。
**

**
選挙ドットコム編集部:「選択的夫婦別姓」について、このところ話題に上ることが多くなってきました。これについて、ご自身のお考えをお願いします。以前は、夫婦別姓に反対のお立場で、最近賛成されるようになったと伺いましたが……。
稲田朋美議員:単純に夫婦別姓にすべき、同姓にすべき、という二者択一の議論ではありません。夫婦や家族のあり方も多様化する中で、それまでの仕事のキャリアが姓が変わることで途切れてしまう問題、女の子だけのご家庭で家名を継ぐ必要がある場合、高齢者同士の結婚など、いろいろな場面で夫婦の姓は問題になります。
でも自民党の中には、夫婦別姓について議論をすること自体が「けしからん」という考えの方がいます。私は、様々な意見を聞き、議論をしたうえで、特に女性が抱えている困難を解決する方法を見つけるべきだと思います。まずは自民党内でしっかり議論をする場をつくることが必要です。
選コム:議論することもはばかられる空気もある中で、あえてこの問題に積極的に取り組まれるのはどういった理由からですか?
稲田議員:この件について、平成27年に初めて最高裁判決が出ました。民法が選択的夫婦別姓を認めていないことが違憲ではないという、合憲判決です。しかし、判決をよく読むと、国会においてこの問題をきちんと議論すべきであるという最高裁のメッセージが込められているのです。
今の日本において、婚姻で女性が男性の姓に変えるのが96%以上です。人生100年時代において、50、60歳で結婚ということも珍しくありません。そのようなとき、自分が長年使ってきた姓を変えなければいけないのは、大変なことです。研究者の方で、それまでの旧姓での功績を継承できない問題やパスポートの表記の問題などもあります。最近ではカッコ書きで通称を表記できますが、それでもいろんな不便があります。
そもそも、女性が活躍し、多様性が求められる時代なのに、女性が姓を変えるのが当たり前という社会は実質的に平等とは言えないし、公平ではないのではないでしょうか。
選コム:結婚後も、職場などでは旧姓を通称として使用すれば良い、という意見もありますね。実際そうしている既婚女性も多いです。
稲田議員:たしかに通称が拡大すれば問題ないという考えもありますが、通称は通称にすぎません。また、一人の人が状況に応じて2つの名前を使い分けるというのは、社会を混乱させてしまうと思います。
例えば国会議員の当選証書は戸籍上の名前ですから、結婚して旧姓を通称で使っていたら、みなさんの知っている政治家としての名前と当選証書とが違うことになります。それが事務所に飾ってあったら「誰?!」ってなるでしょ(笑)。
カッコ書きで通称が書かれていたとしても、混乱を生じさせない解決策がないかなと模索しています。
選コム:夫婦別姓にすると、子どもの姓と親の姓が違うということにもなります。稲田議員: 私も以前、夫婦別姓を認めると親子の姓が異なることで家族の一体感が失われるのではないかと思っていました。でも家族の抱える問題は、姓によって解決できません。片方の親と子の姓が違っていても家族仲良くしている家庭はいくらでもありますし、実の親子で姓が同じでも虐待はあるのです。
また、子どもを持たない選択をする夫婦やそもそも子どもができない年齢の夫婦もあるわけで、もう少し柔軟な選択肢があっても良いのではないでしょうか。

選コム: 先ほど、そうした議論をすること自体がタブーという空気があるとのお話でしたが、なぜ議論自体がいけないと思う人がいるのでしょうか。
稲田議員: 私自身、最近、夫婦別姓に理解を示しただけで、「稲田さんは左翼になった」と批判されています。そういう人たちに対しては、イデオロギーの問題ではないんだ、と強く訴えたいですね。
要するに、「夫婦別姓を認めるのは家族解体運動だ」という固定概念にとらわれずにこの問題を解決すべきだと思うのです。本質は、どうすれば女性のみが社会的な困難を抱えることになっている不公平な日本の現状を変えられるのかということです。
例えば、民法に「婚氏続称制度」があり、離婚しても婚姻中の姓を名乗ることができますが、この場合民法上の氏は旧姓で、戸籍上の氏は婚姻中の姓となりますが、社会生活において使えるのは婚姻中の姓のみです。
それと同じように「婚前氏続称制度(仮称)」を創設して、民法上の氏は夫の姓(よって子供の姓は夫の姓である民法上の氏が原則)だが、社会生活においては旧姓(婚前氏)のみを使うということも考えられます。議論をすれば、様々な選択肢がうまれ、そのなかで最もバランスのとれた制度を創ることが可能です。議論すら許されないというのは思考停止であり、最高裁の要請にも応えていないことになります。
そもそも保守は多様性を認めることです。日本はさまざまな生き方を認めるしなやかな保守を目指すべきではないでしょうか。
選コム:女性議員飛躍の会という議員連盟の共同代表をされていますが、そこではそうした議論をされているのですか?
稲田議員:結婚後に夫が死亡したり離婚してひとり親になれば「寡婦控除」を受けられますが、未婚のひとり親には適用されませんでした。その理由は、未婚のひとり親に税制優遇することは事実婚を増やし、法律婚を破壊するという自民党内の根強い反対が長年あったからです。
女性議員飛躍の会では、この問題は法律婚を壊すとか事実婚を増やすとかいう家族のあり方が問われているのではなく、困難な状況のなかでひとりで子どもを育てている人を公平に扱うかどうかという法の下の平等が問われているのだと整理をしました。
最終的には男性議員も含め144名の賛同者を得て、「寡婦控除」はすべてのひとり親に控除を与える「ひとり親控除」となりました。これが、議連の最初の成功体験になりました。夫婦別姓問題についても、賛成反対両サイドから話をきくことにしています。
今後も固定概念にとらわれずに自由な魂で本質は何かを見極め、困難を抱えている人々の課題を解決するために具体的な提言をしていきたいと思います。そして私たちがめざしているのは、女性が活躍できる社会を創ることによって、日本の風景を変えるということです。
選コム: 大変お忙しいところ、今日はありがとうございました。