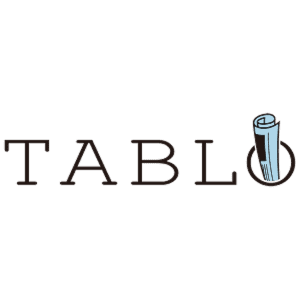この写真はイメージです
※こちらの記事は『憑きもの体験記1「ガラスに目を走らせると、自分の50センチ後ろに人の気配を放つ陽炎が映っていた」|川奈まり子の奇譚蒐集三八 | TABLO』からの続きです。
神社の洋室に現れた謎の侵入者
いつの間にか眠りに落ちて、タナカさんが寝る前に掛けたと思しき、アラームの音で目が覚めた。
頭痛は消え、身体を覆っていた違和感も消えていた。手を見ても、陽炎は見えない。
「彩乃ちゃん、おはよう。……ああ、頭が痛い!」
起きるや否や、タナカさんが頭を抱えてうずくまった。
まるで昨日の自分のようだ。……こちらは、嘘のように頭痛が治っている。
「先輩、大丈夫ですか?」
「ううん。大丈夫じゃない! ……頭痛薬、持ってる?」
急いで冷蔵庫からペットボトルのミネラルウォーターを取ってきて、鎮痛剤と一緒に手渡した。
錠剤を呑み下すと、タナカさんは、眉間に皺を寄せ、左右の拳でこめかみをグリグリと揉みながら、話しはじめた。
「なんかさぁ……怖い夢を見たんだよね。真っ暗な中、誰かが、うちの玄関のドアを開けて入ってこようとしてるんだ。ガチャガチャって、ドアノブが音を立てているから、隣に寝てる彼氏を起こそうとした。肩を揺すって、起きて起きてって大声でわめいたんだよ。でも、どうしても起きてくれない! ドアノブはいよいよガチャガチャと喧しく鳴って、ついに錠が壊された! ああっ、誰かが侵入してくる! ……と、そこで目が覚めた」
その「誰か」は陽炎のように透明でゆらゆらとした化け物だろう、と、想像しながら相槌を打った。
「怖いですね!」
するとなぜか、タナカさんは、この優しい先輩にしては非常に珍しいことに、酷く不機嫌そうに三白眼で睨みつけてきた。
「怖いですね? フン! 彩乃ちゃんのせいで本当に怖い思いをしたんだよ! あんた、夜中にトイレに行ったら、ちゃんとドア閉めてよね!」
「え?」
「さっき言ったように、真夜中に目が覚めたらさぁ……夢の最後に見た玄関のドアとまったく同じ角度で、ユニットバスのドアが開いてたのよ! もう、心臓が止まるかと思った! あとさぁ、私、あんたに風邪を伝染されたんだと思う。頭が痛くて仕方ないから、今日は休むって伝えておいて!」
いつもとは別人のような態度。「あんた」呼ばわりされたのは初めてだ。
理不尽だった。昨日の午後にホテルに戻って眠ってから、一度も目を覚ましたていないし、トイレもバスも使っていない。少なくとも、そうした記憶はない。
――でも、たぶん、先輩にあいつを伝染してしまったんだ。
タナカさんは、ひとしきり文句を言い終えると、蒲団を被って芋虫のように丸まったまま、うんともすんとも言わなくなった。
背中に向かって平謝りに謝り、神社の作業所に出勤した。
「タナカさんが休むとは、珍しいこともあるもんだ。君も昨日は早退だったし、この季節に風邪が流行っているのかねぇ……。弱ったな。もう平気なの?」
チーフに体調を訊かれて、「はい」と答えたのは嘘ではなくて、本当に何ともなかった。それどころか、いつもより調子が良いくらいだった。
「あ、そう。……そうだ、昨夜、おかしなことが起きたんだよ。男性スタッフが何人か、ここの洋室で寝泊まりしていることは知ってるだろう?」
「ええ。話は聞いてます。私はホテルで、とてもありがたいな、と。恐縮です!」
「いや、そういうことじゃない。それはいいんだ。そうじゃなくて……洋間に布団を敷いて雑魚寝している連中がいるわけだが、侵入者があったようなんだ」
「侵入者?」
「ああ。洋間だからドアに鍵が付いている。だから貴重品なんかもその部屋に置いて、夜中も内側から鍵を掛けて寝ている。ところが、午前4時過ぎに、そこへボーッとしたオッサンが入ってきたそうなんだ! 目の焦点が合ってなくて、物凄くぼんやりしたようすで周りを見渡して、「あ~、間違えましたぁ~」と言うと、部屋のドアを開けて廊下に出て行ったんだと! そこで、男連中はハッとしてね、すぐに後を追おうとしたんだが……」
「なんですか?」
「ドアに鍵が掛かっていたんだって!」
「……廊下に出てから鍵を掛けたんじゃないですか?」
「いや、そんな暇はなかったはずだし、鍵を掛ける音もしなかったんだって! でも、気を取り直して、即座に鍵を開けて廊下に飛び出したそうなんだ。だけど、廊下は静まり返っていた、と……」
夜、一人で寝ていると…
その日から、タナカさんとは別々の部屋に泊まることになった。
どうやらタナカさんが相部屋を厭がって、会社に掛け合ったようなのだ。
そこまで怯えさせてしまったかと思うと申し訳なく感じたが、不可抗力なので、何やら悲しかった。タナカさんからひと言も無かったことも、切ない。
新しく振り当てられた部屋はシングルルームで、狭いことを除けば、前の部屋と変わりがなかった。
ユニットバスの造りも、調度品やテレビやベッドサイドのラジオやアラームも、まったく同じだ。
午前2時頃にベッドに潜り込んだ。
サイドボードの明かりを消して、目を閉じる……と、マットレスの足もとが深々と沈んだ。
何者かが、そこに腰かけた。
ベッドの上に跳ね起きて、足もとを見た。
誰も……いや、陽炎のような奴がいるのかもしれない。
手探りでサイドボードの調光スイッチをひねって、明かりを点けた。
足もとの空間は、どこも歪んでも揺らいでもいなかった。
マットレスが沈んでいる感じも、いつの間にか消えていた。
そこで、再び部屋を暗くして、枕に頭を落ち着けた。そして目を瞑る……。
まただ! マットレスの端が沈んで、振動が伝わってきた。
片手を伸ばして調光器のツマミを回して明かりを点け、首をもたげて足もとを窺った。
何も無い。
そこでまた明かりを消して眠ろうとすると……ギッとマットレスのスプリングをきしませて、端に何かが乗ってきた。
仕方なく明かりを点けて足もとを確かめたが、先程と同じ。やはり何も変わったようすは見られない。ところが暗くして横になった途端に……。
これを何度も何度も、明け方まで繰り返す破目になった。
次の夜は、寝ること自体が恐怖だった。
見たくもないケーブルテレビの通販番組を点けっぱなしにしておいて、朝陽が昇るまで起きているつもりで、蒲団に入らず、ベッドの端に腰かけていたのだが、気づいたらベッドカバーの上に横たわっていた。
遮光カーテンの隙間が白く光っている。
無事に朝を迎えることが出来たのだ、と、胸を撫でおろした。
寝不足が幸いして、怖い思いもせず、いつの間にか寝落ちしてしまったとみえる。もしかすると寝過ごした可能性もあると思いついた、ちょうどそのとき、
「すみませぇ~ん」
と、間延びした声で呼びかけてきながら、誰かが部屋に入ってきた。
このビジネスホテルの客室清掃係だ。そう思った。
なぜなら、いかにもそんな感じがする中年女性の声だったので。
ここに滞在するようになってから何度も客室清掃係を見かけており、廊下で挨拶を交わしたこともある。客室清掃係は何人かいるようだが、全員が4、50代の女性だった。
だから疑いもせず、掃除に来たのだと考え、そして、ああ、やっぱり寝坊してしまったのだと確信した。
「ごめんなさい。もう少ししてからにしてもらえますか? すぐに出かけますから!」
ベッドの上から、ドアの方へ向かって大声でそう呼びかけた。
しかし、返事がない。「わかりました」とか「失礼しました」とか定型的な台詞が返されるものとばかり思ったのだが。
無言で、ズリッズリッと足を引き摺り加減に入ってきてしまった。
そちらを振り向くと、例の陽炎が揺らいでいた。
悲鳴が喉で膨らんだまま留まり、窒息しかけて眩暈を覚えた。ギュッと目を閉じると、間もなく、ドアの手前のクローゼットの方から、荷物を物色するようなゴソゴソという音が聞こえてきた。
――狭いシングルルーム。あいつを回避して外に逃げ出すことは不可能だ。
硬く身体を縮めて、冷静にならなくては、と必死で呼吸を整えた。叫んで飛び出したら、何をされるかわからないという気がしたのだ。
お願いだから出ていって! そればかりを強く念じた。
しかし、やがてそれは、ズルズルとカーペットに足を擦りつけながら、ベッドの枕もとの方へ接近してきた。
もう、死に物狂いで逃げるしかない! そう決意したのに。
「グエッ」
カエルそっくりの呻き声を立てて動作を止めたのは、突如として両手が首に掛かったからだ。
分厚い掌だが、芯に骨が無い。人の手ではないのだ。
天井に陽炎が揺れている。カーテンの隙間から差し込んだ光を綺麗に透過させながら、そこで空気の襞が蠢いていた。
酸素を求めて口を大きく開けた私は、きっと、餌をねだる雛鳥のようだろう。
あまりの苦しさに、視界が暗く閉じてゆく。
ついに闇に堕ちた、と思ったら、
「気をつけろよ」
と、聞き覚えのない男の声が、耳もとで。
そして首から手が離れた。
サイドボードでアラームが鳴って、目が覚めた。
時刻を確かめると午前7時で、いつの間にか蒲団の中に潜り込んでいた。テレビは点けっぱなしで、室内はどこも昨夜と変わりがなかった。クローゼットの中も調べたが、誰かに触られた形跡もなかった。
ドアの鍵も掛かったままだった。
――なんだ、夢だったのか。
大きく安堵して、自分の怯えようが何やら馬鹿らしくなり、さくさくと朝の身支度を整えた。
いつもより早く出て、駅前のコーヒーショップで朝食を食べていこう。
そんなことを考えながら、いつもの習慣で、出掛ける間際にベッドを軽く整えようとしたところ、白い枕カバーにポツンとついた赤い染みが目に入った。
10円玉ほどの大きさの、真っ赤な……女なら誰でもわかる、血の染みだ。
しかし経血ではなく、乾いた血でもない。
生々しい鮮血が、円く付着している。恐々と人差し指の先で触れたら確かに濡れた感触があって、指先に赤い液体が移った。
鼻を近づけて嗅いでみたら、金臭い。
間違いなく、これは血だ。
気をつけろという警句が鼓膜に蘇り、衝動的に枕を引っくり返してしまった。
赤い色が見えなくなると、いくらかましになったが、まだ恐ろしくてたまらず、藁にもすがる気持ちで、突然現れた血痕に合理的で科学的な説明を探した。
――怪我だ! 知らないうちにどこか切ったか何かして……。
しかし、慌ててバスルームの洗面台で頭皮や耳、鼻や口を見てみたが、かすり傷ひとつ見当たらず、鼻血や歯茎からの出血も疑ったけれど、どちらの粘膜も桃色に輝き、健康そのものであった。
次の仕事場でも続く恐怖
その後も神社の作業場での仕事が続けられたが、以降は何事もなく済み、秋口にはすべての工程が完了した。
タナカさんとの仲も元に戻った。タナカさんがあれから何か変事を体験しなかったか、それだけは気になったが、わざわざ突いてみるものでもないと自分に言い聞かせた。また不機嫌になられては損だ。
東京に戻ってから日を置かずに、今度は北海道の札幌市で同じような百貨店のパッケージシステムの開発プロジェクトのチームが再び立ち上げられることになった。
川越の神社に集ったのとほぼ同じメンバーと一緒に北海道に飛んで、仕事に取り掛かった。クライアントである百貨店の倉庫が作業場として用意されており、宿は札幌駅前のウィークリーマンションが指定されていた。
――こんどの仕事は、普通だな。
神社で作業させられたことと、陽炎に似た化け物に襲われたことには関係があると思われた。枕に残された血痕には、心の底から震えあがったものだ。
夢や気のせいでは済まされない、物理的な証拠が現れたことが恐ろしかった。
このまえは、異常な環境のせいで化け物と遭遇してしまったのだ。
今回は、ごく尋常に、倉庫で仕事をするのだから、怪しい出来事に見舞われることもないだろう。
そう思ったのだが。(3へつづく)