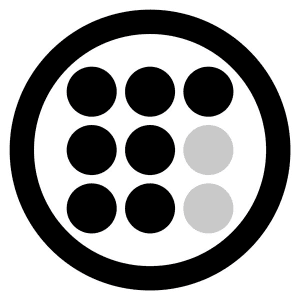2010年の日本ハム、2012年のオリックスは打点王輩出もチーム成績は低迷…
首位打者、本塁打王とともに、打撃主要3タイトルの1つと位置づけられている「打点王」。しかし、塁上に走者が1人もいない場合は、打者は最大でも1打点しか挙げることができない。打点という指標は、前を打つ打者、打線全体の機能性に少なからず影響を受けるものでもある。
そこで、今回は直近10年間のパ・リーグにおいて打点王を獲得した選手たちと、その所属球団が記録したチーム全体の打撃成績を見ていきたい。さらに、歴代のシーズン打点記録でトップ10に入った選手たちと、当時の所属球団の打撃成績についても同様に確認し、はたしてどれだけの相関性が見られるのかをチェックしていこう。
まずは、直近10年間のパ・リーグにおける打点王と、その所属チームについて確認したい。その結果は以下の通りだ。(所属は当時)

以下2つの表が示すように、チーム得点数の面では1位が3回、2位が4回と、打点王の在籍したチームは、リーグ内でも得点力が高い傾向にあった。だが、2010年の日本ハムは得点数リーグ5位、2012年のオリックスが同6位と、チーム全体が得点力不足に苦しむ中で打点王が孤軍奮闘するケースも存在した。

とりわけ、2012年のオリックスは打率、得点、安打、盗塁の4部門でリーグ最下位の数字となっており、李大浩の打点がチーム全得点の20.5%に達していた。特定の選手にポイントゲッターとしての役割を依存するチームが生まれることは往々にしてあるが、打点王に輝いた選手が所属するチームの打線がここまで苦しんだ例は珍しいだろう。
パ・リーグでは直近4年間、打点王が在籍したチームが優勝している
その一方で2014年以降の6年間においては、打点王が所属していたチームの得点数がいずれもリーグ1位か2位であり、近年における打点王と所属チームの成績には一定の相関性が見られる。直近4シーズンは打点王を輩出したチームがリーグ優勝を果たしており、打点王を擁するチームは攻撃面の機能性のみならず、チーム状態そのものが優れていたと言えそうだ。
続いて、歴代のシーズン打点記録のトップ10に入った選手と、その打撃成績についても同様に見ていきたい。その結果は以下の通りだ。(所属は当時)

1位の小鶴氏が所属した松竹、2位のローズ氏が所属した横浜は、いずれも当該年にリーグトップの打率と得点数を記録。この2チームをはじめ、打率の面でも10チーム中6チームがリーグ1位の数字を記録していた。やはり、得点数とチャンスメークの両面において、非常に優秀な打線を有していたチームが多かったことがうかがえる。

驚異的な打点数を記録しているポイントゲッターと相対する際には、相手バッテリーもピンチの場面でとりわけ警戒を強めるのが自然だろう。しかし、他の選手も総じて警戒が必要なレベルの強力打線を擁するチームであれば、勝負を避けられたり厳しいコースを突かれる可能性も減ってくる。
打点王がいるチームは総じてチームの打撃成績も優れている傾向が
それに加えて、上記の各球団の高いチーム打率に象徴されるように、チーム全体がチャンスメークにも長けているとあれば、より個人が打点を稼ぎやすくなるのも当然だ。傾向としては近年のパ・リーグと同様だが、歴代トップクラスの数字を記録した選手を擁するチームであれば、チーム全体の打線の完成度もそれ相応に高くなってくるのだろう。
打点王と所属チームの打撃成績には一定の相関性が見られたといってよさそう。さらに、歴代打点ランキングのトップ10に入った選手たちの場合は、その傾向がより顕著となっている。以上の点からいって、打点王と、その所属チームの打線全体の機能性には、十分に関連があると考えられるのではないだろうか。
また、先述の通りに直近4年間は打点王を輩出したチームがいずれもリーグ1位の勝率を記録しており、打点王が在籍しているチームは、打撃成績のみならずチームの順位も優れている傾向がある。これは歴代打点ランキングの場合も同様で、打点王を獲得する選手を輩出できるほどの打線を構築できたチームは、やはり成績面でもその恩恵を得られているようだ。
一種の縁起の良いジンクスともいえるこの流れは、果たしてこれからも継続していくのだろうか。近年は打線の機能性のみならず、チームの調子のバロメーターとしての側面をより強めつつある「打点王」の行方に、今後も注目していく価値はありそうだ。(「パ・リーグ インサイト」望月遼太)
(記事提供:パ・リーグ インサイト)