

今週は日11月18日にニューアルバム『Powers of Ten』をリリースしたDef Techのデビュー作を取り上げる。今年結成20周年、デビュー15周年のアニバーサリーイヤーを迎えた彼ら。本文でも少し触れたが、このアルバム『Def Tech』はチャート1位を獲得したばかりか、インディーズ作品ながらミリオンセラーとなるという、邦楽シーンにおける金字塔を打ち立てたと言っていい作品である。そこには彼らにしか発揮できないイデオロギーとメンタリティーがギュッと詰まっていた。
日米のハイブリッド@ハワイ
説明不要だとも思うが、Def TechはShenとMicroの2MCからなるユニットである。Shenは[中国生まれ、米国ハワイ州オアフ島育ち]で、[父の仕事の都合で毎年夏休みに日本へ遊びに来ていたことがきっかけとなって、日本での音楽活動を決心。20歳の時にハワイから来日]したという経歴を持つ。一方、Microは[東京都大田区蒲田出身]で、[実家はサーフショップで、幼少のころからよくハワイに行き、小学生の頃からサーフィンをたしなんでいたという]([]はWikipediaからの引用)。つまり、中国生まれの米国青年と日本の青年とがハワイが縁で出会った音楽ユニットということになる。このハイブリッドなパーソナリティーがサウンドにも反映されている点が、何と言ってもDef Techも面白いところではあるだろう。大きなアドバンテージだと言ってもいい。
そのユニークな音楽性はデビュー作『Def Tech』から十二分に発揮されている。まずリリック。歌詞にはShen、Micro、それぞれの母国語である英語と日本語が落とし込まれており、2MCが概ねそれぞれの言語で歌唱しているスタイルは特徴と言えば特徴ではある(※英語パートと日本語パートとを厳密に分けているわけではない)。ただ、それが昭和であったならいざ知らず、『Def Tech』がリリースされた2005年時点で、英語と日本語が混じり合った歌詞がことさら珍しいものではなかったことは言うまでもなかろう。そんな中で、強いて彼ららしいと言えるのは──それも、もはや2020年の現在ではそれもまた珍しいものではなくなったが、英語と日本語とが混じった中で押韻しているところだろうか。
《Def Tech sound Shen and Micro '/round singing on and on and on/地に足付け 頭雲抜け 進む前に前に前に/手をつなげば怖くないから/そこまでお前は弱くないから/でもいつまでも そばにいないから/Believe my way my way my way》(M4「My Way」)。
《なぁ みな 今手をつなげ/Let me see unity with your hands in the air》《無駄なことなんて無い ever little thing in life has meaning right》(M7「Consolidation Song」)。
《It's going down yo, we got to live now/聞け 心 体 頭/One love we fight for, we march to the end/感覚研ぎ澄まし 耳傾け》(M8「Emergency」)。
これによって日本語が英語っぽく聴こえるという効果が生まれているのだろうし(その逆は自分は英語ネイティブじゃないのでよく分からない…)、シームレスに英語詞と日本語詞を連続させていくのに押韻が重要な要素であることは疑いようもない。それよりも…というか、その押韻も含めて…というべきか、米国、日本だけに留まることなく、そのハイブリッド感を歌詞の内容で押し出している点は特徴のひとつと言えるだろう。
《This is an introduction to Pacific Island Music/Jump up and down, together get wild and lose it/This is an introduction to Pacific Island Music/Jump up and down, together get wild and lose it》(M1「Pacific Island Music」)。
《赤道直下 南の島々浮かぶ ジャマイカ ハワイ 沖縄/暑い太陽の下 毎日が夏 パラダイス/サマータイム 終わらない/止まらない時間を胸の中だけで少し遅め泳いでおいで/耳すまし聞こえてくる波の音 永遠を感じさせてくれるよ》(M2「High on Life」)。
《This is Jah Live, it's a ragga love/We all say, “Never give up the one love”/Hear the roots and rock it's Jawaiian new/Takin' the ragga vibe, givin' it back to you》(M6「Jah Live」)。
《2000年越えて 4, 5, 6年 経った今でも 何も変わらず/アメリカ中心に地球は動く/エイジア アフリカ ヨーロッパ フランス ジャパン/チャイナ ロシア アフガニスタンなど 貧富の差が/まだまだ たくさん 人びと 子供 苦しめ》(M8「Emergency」)。
M8「Emergency」はハイブリッド感を押し出したものと言い切れないけれども、その視点が米国、日本だけに限定されたものではないという点では、そのメンタリティーが通底していると言ってよかろう。Def Techはなぜこういう歌詞を書いたのか。それはメンバーのShenとMicroそれぞれの生い立ちが前述の通りということもあるだろうし、上記M8「Emergency」のリリックを見てもすでに答えが出ているとは思うのだけれど、そこは最後に述べるとして、いったん話題を、これもまたDef Techの特徴であるところの彼らのサウンド面へと移そう。有言実行というか(?)、どうやらサウンドを言語化、具象化したものが歌詞になっているようなのである。
彼らの思想を具現化したサウンド
[自らの音楽を「ジャワイアン・レゲエ(ジャパン+ハワイ+ジャマイカ)」という新しいジャンルとして位置づけている]というDef Tech([]はWikipediaからの引用)。ヴォーカルパートはどちらもラップがほとんどなので、“ジャパン+ハワイ+ジャマイカ”なんて言うと、俗に言うミクスチャーロック的なものを想像するかもしれないが、そういうラップロックやラップメタルではないし、ヒップホップともジャパニーズレゲエともちょっと違う。彼らの音楽は、やはり“ジャワイアン・レゲエ”としか言いようがない感じではある。あえて、もう少し突っ込んで分析するならば、J-POP、J-ROCKやハワイアンの手法でレゲエをやっているといった感じと言えばいいだろうか。
例えば、M1「Pacific Island Music」。ビートはわりと激しめなので、ここだけを聴いたなら、J-ROCKの雰囲気ではあるが、ベースはスラップも効いているので、そう単純ではないサウンドであることが分かる。ギターはスカのカッティング──いや、この音色はギターではない。ウクレレだ。楽曲の進行に伴って、そのカッティングも2、4拍が強調されたいわゆるスカビートに完全に準じているわけでもないし、意外とベースがスカビートを演出しているようなところも見えてくる。そこにキャッチーなメロディパートと、話すように歌うレゲエならではの歌唱パート、それぞれのヴォーカルが重なる。しかも、歌は英語と日本語が混じり合い、歌詞は前述の通り、このユニットのスタンスをそのまま表したものである。加えて言えば、サビの歌唱がカタカナ英語的…と言い切ってしまうのはやや乱暴かもしれないが、ネイティブスピーカーの発音ではない印象もある。少なくともこれは米国の歌であるとか日本の歌であるとかいう限定はなさそうだ。アルバム1曲目から自らの姿勢をズバッと出しているというのは何とも威勢がいい。デビューアルバムとして理想的な作りではないか。
M2「High on Life」のサウンドも象徴的だ。イントロはアコースティックギターから始まる。おそらくガットギターだろう。そこで鳴らされるのは沖縄音階だから、三線を使ってもおかしくないところだが、あえてそうしていないのだろう。ドラミングは極めてロック的だ。ヴォーカルはほぼラップではあるものの、メロディアスな箇所が多々ある。後半に進むに従ってレゲエ風味が増加。アウトロ近くでは、はっきりとこれはレゲエであると認識できるほどに展開していく。オキナワンで始まった楽曲がいつの間にかレゲエに変化──少し大袈裟に言えば、マジカルなナンバーである。M3以降も、M5「Quality Of Life」ではソウルミュージックのフィーリングがあったり、M6「Jah Live」では和楽器風の音を取り入れたり、M8「Emergency」ではアッパーでファンキーなノリを加えたりと、いずれもはっきりとジャンル分け出来ないユニークなサウンドが続く。
締め括りのインストナンバー、M9「Guidance. Micro's House@attic studio(Inst.)」ではそれが極に達するかのようだ。アッパーなトラックで、ドラムとパーカッションがグイグイと全体を引っ張っていき、リズムだけで見たらわりとブラックミュージックテイストが強めな印象ではある。そこに乗るのは、この時点でも十分にレトロではあったであろう雰囲気のシンセ。誤解を恐れずに言えば、初期YMO的な音である。主たるメロディーが中華風であったり、和風であったりするのもそう感じさせる要因かもしれないが、いずれにしても、レトロフューチャー感と、実在しないアジア感が混在している感じはとても面白い。そのうち琴や尺八っぽい音も聴こえてくるし、気づけばベース音はどこかサイケデリックであるなど、ハイブリッドと形容するに相応しいナンバーが生み出されているのだ。本作は[インディーズグループとしてはMONGOL800の『MESSAGE』に次ぐ史上2作目のミリオンセラーを達成。最終的に200万枚近く売り上げた]アルバムである([]はWikipediaからの引用)。ここまで述べてきたような、意欲的なサウンドで彩られたアルバムがダブルミリオンとなったことは、『Def Tech』の発表されたのが年間でミリオンセラーがほとんど出ないようになっていた時期であったことを合わせて考えると、それは音楽シーンの中で希望を見出すような出来事ではなかったかと、今さらながらに思う。
今も異彩を放つメッセージ性
さて、それでは、Def Techのふたりがどうしてそうしたハイブリッド感を押し出したのかと言えば、それは平和の希求ということになるだろう。それは筆者の想像ではあるけれども、それほど的外れでもなかろう。M8「Emergency」、あるいはM6「Jah Live」の歌詞を見れば分かる。John Lennon言うところの《Imagine there's no countries》《the world will be as one》辺りを具象化したものがこういうサウンドのなっているではないかと推測する。ただ──これは彼らの思想や活動が間違っているという意味ではなく、世界のあり様を総合的、俯瞰的に見た上での話だが、《2000年越えて 4, 5, 6年経った》どころか、そこからさらに14、15年経ってしまった今、貧富の差はさらに開いたと見て間違いない。ヨーロッパでは2030年に化石燃料車も全面的に禁止するという話もあるし、日本でも政府が温室効果ガスの排出量を2050年までに実質ゼロにすると表明したことから考えると、環境問題は決して好転しているとは言えないだろう。引き続き《やばい倍の倍 地球が危ない》(M6「Jah Live」)のである。また、M5「Quality Of Life」ではこんなことが歌われていたが──。
《今の今の今まで 女性は差別されてて/耐えて 堪え我慢して/乗り越えてきた流れ/変える時が来たんだぜ 今顔を上げ立ち上がれ/腕高く掲げ 女であることに誇りを待て/到底叶わぬ夢だと思ってもがっちり握りしめゆけ/女という字は祈る姿 形からできた文字/もし願いが叶うのならば大きなことを求めて/この奴隷制から逃げて見つけて/知らぬ未知の道を》(M5「Quality Of Life」)。
もう一度言うが、Def Techがこれを歌ってから14、15年経った。それなのに、政権与党の議員(しかも、これが驚くことに女性議員)が“女性はいくらでも嘘をつける”と発言するなど、ここで彼らが訴えたことが何も実現していない…と言っていいかどうか分からないけれども、少なくとも大きく前進したとは言えない現状ではある。もっとも、歌で主張したことが巷に大きく広がったとして、そこで綴られているようなことが現実になるわけではないことは、John Lennonの例を挙げるまでもなく、明らかなのだが、今も“Boy Meets Girl”や“Girl Meets Boy”ばかりが跋扈する(というか、もはやほとんどそれしかないように思える)邦楽シーンにおいて、Def Techが放ったメッセージは、今も異彩を放っているのは間違いない。
TEXT:帆苅智之
アルバム『Def Tech』
2005年発表作品
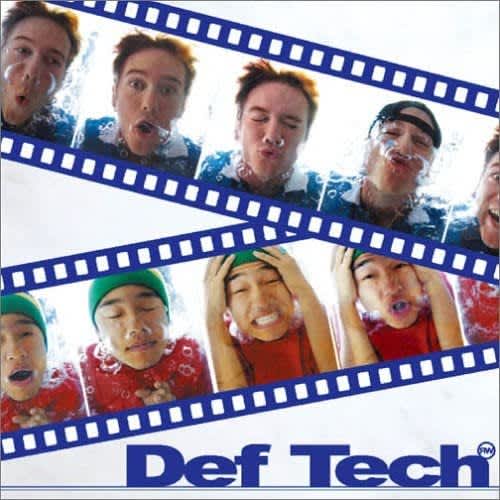
<収録曲>
1.Pacific Island Music
2.High on Life
3.Future Child
4.My Way
5.Quality Of Life
6.Jah Live
7.Consolidation Son
8.Emergency
9.Guidance. Micro's House@attic studio(Inst.)

